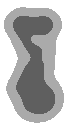| 今年はヴォルフガング・アマデウス・モーツァルトの生誕二百五十年の年であり、ロシアの作曲家ドミトリー・ショスタコービッチの生誕百年の年であり、精神を病んで自死してしまったロベルト・シューマンの没後百五十年の年にあたるらしい。もっとも世間的にはなぜかモーツァルト・イヤーなどと称して、モーツァルトばかりに脚光があたっている傾向にあるようだが。
たしかにモーツァルトは悪くない。私自身もミニコンポ・ステレオのタイマーをセットして、毎朝クラシック音楽で目覚めているのだが、最近はモーツァルトのディベルティメントばかりが鳴っている。以前はヴィバルディーの四季やシベリウスのヴァイオリン協奏曲、あるいはウインナーワルツの時もあったが、このところモーツァルトのままで落ち着いてしまっている。
モーツァルトの音楽を「癒し系」などと言われ出したのは、はたしていつ頃からのことだろうか。最近は何でもかんでもちょっと人気が出たりすると、「癒し系」などと呼びたがるようだが、少なくとも私がクラシック音楽に馴染みはじめの頃は、そのような言い方でモーツァルトを紹介したりはしていなかった気がする。
そもそもモーツァルトは今日ほどの持てはやされかたはしていなかったのではなかろうか。先日テレビの主にクラシック音楽を扱う番組のなかで、ヴァイオリニストの葉加瀬太郎が出てきて、モーツァルトのことを「世界的にもぶっちぎりの一番人気」などとコメントしていたが、以前はそのような言い方はされてなかったはず。
クラシック音楽に馴染みはじめの頃、それは私が中学二年生以降のことになるが、クラシック音楽といえば、やはりベートーベンだった。クラシックでよく聴く作曲家はと問われれば、誰もがいの一番にルードビッヒ・フォン・ベートーベンの名を挙げていた。なかには自分自身の音楽知識をひけらかすために、マーラーやドビッシーの名を口にする輩もいるにはいたが、ベートーベンを知らない音楽ファンなど誰もいなかった。その当時クラシック部門のレコードセールスは、「運命」と「田園」のカップリング盤がそれこそぶっちぎりのトップを走っていたのではないだろうか。
ことに第五番の「運命」は、クラシック音楽といえばこの曲みたいなところがあった。この時期私の受験勉強の時期にも重なり、どこまで確かな情報に基づくものかは分からないが、深夜受験勉強に疲れたあげく勉学を投げ出す気分に襲われる度に、「運命」のあのダダダダーンという冒頭の音楽をかけては悪しき誘惑を断ち切った、なんて話をよく耳にしたものであった。
おそらくはそういう時代だったのだろう。この時期、日本は後に高度成長期と総称された。戦争に負けたこともあって、追いつき追い越せのかけ声が響き渡り、何でもかんでも成長することが賛美され、頑張ることがそれこそ闇雲に奨励された時代でもあった。
たしかにベートーベンの「運命」は、執拗なまでにダダダダーンの音型を繰り返す音楽だが、聴きようによっては、頑張れ頑張れ頑張れ、と叫び続けられているようにも取れなくもない。
御多分に漏れず、私もクラシック音楽を聴き始めたのはベートーベンがきっかけだった。もっとも「運命」でも交響曲第三番の「英雄」でもなく、「田園」ではあったが。
クラシックなどにまったく興味のなかった生活だったが、ある日何気なくテレビを見ていて、田園風景を模したという第一楽章の緩やかな音楽が突如として頭のなかに棲みついた。洋画だったと思う。題名も内容も記憶にない。たしか大航海時代の船室のシーンだった気がする。何人かで作戦会議でもしていたのだろう、そこに「田園」の音楽が静かに流れていた。海洋の場面に田園交響曲とはどのような取り合わせなんだろう。とにかくそのメロディーを頭で反芻するうちに、すっかりクラシック好きになっていた。
私に「田園」をそれこそ毎日聴き続けた日々があった。高校二年の新学期から二学期にかけてのことだった。
一年生の時はそうでもなかったが、進級して新しいクラスに変わってから、クラスの者と口がきけなくなった。人と馴染むのに時間が要するタイプではあったが、とにかく誰とも交わることが出来ない。なぜか分からない。嫌われたり避けられていたわけではなかったはずだが、とにかく駄目なのである。
そのくせ異性のことばかりが目につき、そして好きになる。その頃の日記を読み返すと、おかしいぐらい異性の名前が出てくる。一人では勿論ない。二、三日で消える子もいれば、一ヶ月以上毎日のように名前が残っている子もいる。たいていは同じクラスの女子だったが、クラブの先輩の人や後輩もいた。背の高い子や笑顔のいい子、それに訳ありの少し謎めいた子まで、とにかくあらゆる異性が対象だった。その誰とも自分の意思を伝えたことはなかったが。
このように書いてしまうと女性への過剰反応が、あの頃の孤立感を際立たせた原因と取られかねないが、たぶんそれは違う。
日々、自分自身が変わっていっていることが感覚として分かっていた。自分の身体のなかに別の誰かが育ってしまっている、とでも表現すればいいのだろうか。身長が伸びているわけでも急に頭が鋭敏になったわけでもないのだが、説明のしようのない違和感だけが渦巻いていた。
そんな一人孤立感を深める私を救ってくれたのが、ベートーベンの「田園」だった。
それこそ毎日聴き続けた。帰宅すると食事もそこそこに自室にこもり、毎日同じLPレコードをターンテーブルに載せた。ソニーから出ていたレコードで、オーマンディー指揮、フィラデルフィア管弦楽団演奏のLPだった。名盤の誉れ高いブルーノー・ワルターのものでも、ベートーベンならフルトベングラーと言われていた人の盤でもなかった。今は忘れられた指揮者と呼ばれても仕方ない、そしてその当時でさえも、演奏内容そのものよりも、もっぱら音作りのきらびやかさで名を馳せていたオーマンディーのレコードでなければならなかった。
今思うとあれは実に不思議な、そして二度と経験することがない音楽体験だった。自室にこもり「田園」に聴き入ると、身体の中がしだいに暖かくなった。毎日である。それこそ癒されている、とでも表現すべき感覚。「田園」に身を委ねているときだけ、沈殿したような孤立感がどこかに行ってしまっているのである。
もしかすると「田園」という音楽がこの世になければ、私は暗く孤立感を持ったままの人間になっていたかも知れない。まあ、それは少し楽聖のことを持ち上げすぎかも知れないが、少なくとも精神過敏であったあの時期の私は、紛れもなくベートーベンのあの曲が救ってくれたのは確かである。
その後クラス仲間と交わりきれない時期は、秋の修学旅行をきっかけに、きれいさっぱりと縁が切れた。宿泊先のレクレーションで寸劇のメンバーに選ばれ、ヒロインのジュリエットを演じることになった。相手のロミオはもちろん女性で、この彼女は笑顔が印象的な異性として今も日記に名が残っている。ジュリエットの化粧を担当してくれたクラス仲間も、背が高くて憧れ続けた女性だった。
それからは、それまでの半年間が嘘のようにクラスではしゃぎまくった。そして、「田園」も聴かなくなった。その必要がなくなったのかもしれない。
今私の手元には、オーマンディー指揮フィラデルフィア管弦楽団の「田園」の盤はない。LPレコードからCDになってしまったせいもあるだろうが、なぜか見あたらない。ブルーノー・ワルターとフルトベングラーの「田園」はCDになっても持っている。が、こちらもめったに耳を傾けることはない。この文章を書くために久しぶりにフルトベングラーのCDを取り出して聴いてみたが、おそらくは五、六年ぶりの「田園」だったはずである。
|