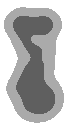| ヨーロッパ中世史研究者の阿部謹也さんが亡くなった。名著『ハーメルンの笛吹き男』を記した人である。
この本の出版は一九七四年であるらしい。家に本がないので、わたしがいつそれを読んだのかは不明である。おそらくどこかの図書館から借りて読んだのだろう。しかしその時の衝撃は今もはっきりと覚えている。小説以外の書物を「面白い」と思った、それが最初だったからだ。
『ハーメルンの笛吹き男』は、グリム童話でよく知られている。ネズミの害に悩むハーメルンの町に、ある日、不思議な男が現れる。男は報酬と引き換えに、ネズミを退治することを町の人びとに約束する。男が笛を吹くと、ネズミがゾロゾロついてきて、ネズミはみんな川に溺れて、町からいなくなった。男は約束どおり報酬を要求するが、町の人びとはあれやこれやと理由をつけて、支払いを拒む。怒った男が次に笛を吹くと、今度は町じゅうの子どもが男についていって、町から消えてしまった。というお話である。
このドイツに伝わる伝説を、丹念に古文書を読み、さまざまな角度から検証したのがこの書物である。伝説はどのようにして形成されたのか。書物を読みながら、その過程をたどることは、目からウロコが落ちる思いがした。緻密な文献検証の上に立ったいくつかの仮説は、実に説得力を持っていた。そしてなによりも、中世の庶民――名もなき人びと、のなかに物語を発見したことが、新鮮な驚きだった。学術書でありながら、たいそう「面白かった」のだ。
中世というのは、庶民に光が当てられた時代であると思う。日本においても、宮廷文学が絢爛たる花を咲かせた平安時代を経て、中世には今昔物語や宇治拾遺物語などの説話集や、御伽草子などが登場する。それによって、わたしたちは、ようやく庶民の暮らしや思考を想像することが可能になった。そしてヨーロッパ中世の庶民に光を当てたのが、阿部謹也のこの書物であった。
氏はその後、ヨーロッパ社会と日本社会を対比的に論じた『世間とは何か』を発表した。研究者として、二年間のドイツ留学を含め、長くヨーロッパ文化と関わってきた氏には、必然的に母国である「日本」を対象化することが求められてきたのだろうと、想像するに難くない。
氏は、日本でいう「社会」とはつまり「世間」であるという。氏によると、「社会」とは、理念や理想をその柱に持っているが、「世間」とは、金や名誉、義理などで成り立つものであるという。
確かに、職場であれ、地域であれ、わたしたちが所属しているのは「社会」というより「世間」であるなあ、と感じる場面は多々ある。世間に顔向けできないとか、世間の人がなんと言おうが、とか、わたしの親世代の人はよくそう言ったものだ。わたしの世代がそれを口にすることはもうあまりないけれど、本質的な部分で「世間」という感覚は生きていると思う。それは周囲と協調しながら暮らそうとする、日本人の知恵であっただろう。そして、PTAや地域の活動に参加して時おり感じる違和感の正体は、実はこれであったのだな、と合点がいく。「理念」がないのだ。エラそうに言うと……。と、こんなふうに一歩引いてしまうところが、やっぱり、日本人。「世間さま」を慮っているのだネ。
しかし、ことが地域コミュニティレベルで留まっているうちはまだしも、それが国家レベルになってしまうと……。「理念」の欠如は恐ろしいことになりはしないか?
その他、ときおり目にする氏の言説には、一本すっくと太い筋が通っているようで、その声高ではないが、鋭い批評精神を、わたしは敬愛していた。
その阿部謹也さんが、生涯深く関わった国、ドイツを、今度旅することになった。
飛行機嫌いで、海外旅行などわたしには縁がない、と思ってきたが、異なった風土、習慣を持つ土地への憧れは強い。なあに、ヨーロッパなんて、魔法の絨毯で、ひとっ飛び……。残念ながらハーメルンには行けないし、短い旅で何かがわかるとは思わないが、ドイツの乾いた冷たい風に吹かれてこようと思っている。
|