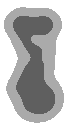|
�@���O�g�������̑T���̖��A�䌴���オ�\��ŒO�g�̊������͈��؏W���̋v���Ƃɉł��ł����̂́A���a�\�O�N�̏\�ꌎ�����̂��Ƃł������B
�@�����m�ł������ł���̋v���Ƃ́A�����̂Ȃ����܂ł͋߁X���ɂ��̖���y����ɉh�Ԃ�ł������ƕ������A���̂Ƃ��ɂ͂��ł��n�͖S���A�Ɖ^�͌X�������̈�r��H���Ă����B�Ƃ̔��T�͂��܂��ɕ��Ƃ̊i�����d�ċC�ʂ������A���ꂱ��ƉƂ̂���������@����邱�Ƃ��łɂ������āA����܂ł����������̂Ƃ͖����ł����������傢�Ɍ˘f�킹���B
�@���؏W���͘Z�\���˂���W���̂��ׂĂ��v���̐��ł��������A�l�X�͖��オ�ł����{�Ƃɑ��Ă͌h�ӂ����߂ċv�����~�ƌĂ�ł����B
�@���オ�������͍̂���̓��ɁA�撷�߂钷�V�i�̌፲�q�傩��v���ꑰ��S�N���j�����X�ƌ�蕷�����ꂽ���Ƃ������B��ςȂƂ���։ł��ł����Ɠ��S����������̂́A�����o�ɂ�đ�����ɋ߂�v�̑���Y�̗D�������B��̋~���ɂȂ����B
�@�`���ꂵ�ď\������o����������̂��ƁA�W�����̋v���Ƃ̎����c�Ɉ��̉ݕ������Ԃ��E�ւ��Ă͂܂荞�B�����Ԃ����ؒJ�֓����Ă���Ȃǖő��ɂȂ����ƂƂāA�W���͑呛���ɂȂ����B
�@�����Ԃɂ͕d�̈��������߂ɁA�C�R�W�̎����ԂɈႢ�Ȃ��A����͈�厖�Ƃ���ɁA�፲�q�傪���W���������B�W���̒j���������o�ŒE�ւ��������Ԃ������グ�����ƁA�፲�q��͉^�]��Ɠ��悵�Ă����j���Ƃ��Ȃ��ċv�����~�ւ���Ă����B
�@�ݕ������Ԃ͕��ߊC�R�H���̂��̂ŁA���s���ʂ���̋A�r�ɓ����ԈႦ�ďW���֓��荞��ł��܂����炵���B
�u����o���̋ߓ����s�����Ƃ��āA���̒J�֖������݂܂����B�c���r�炵�Ă��܂��\����܂���v
�@�^�]��Ƃ��ǂ����J�ɓ����������j�́A�H���̑��D�Z�t�Ŗ�c�ƌ������B
�u�܂��A����͓�V�Ȃ���܂������ƁA�Ȃɂ����\���ł��܂��ǂ������オ�肭�������ȁv
�@�v�X�̗��q�ɔ��T�͏�@���ŁA���k����ނ�����~�ɏ������ꂽ�B�����������邤���ɁA�߂��I��������Y���A��Ď��Ȃ�ʎ����ɂȂ����B��c�͑���Y�ƍ����Ȃ��̓�\����ƌ����A�b��͑o������̈͌�̘b�Ő���オ�����B���i�͊O�ł̕t�������̏��Ȃ��v�̊y�����Ȋ���A����͏��߂Ėڂɂ���v���������B
�@���̂��Ƃ����������ƂȂ��āA���̌����c�͏o���̋A��ɂ͓x�X�������悤�ɂȂ�A�҂����܂��Ă�������Y�ƌ�ɋ����Ă������B
�@���a�\�l�N�������Ă���܂��Ȃ��A����Y�͎��a�Ɗ�����ꂽ�x�a�������A�a�̏��ɕ����Ă��܂����B���オ�ł��ł��ĎO�����]�肪�߂�������́A�t���܂��O���̂��Ƃł������B
�@����Y����������̌��ɂ͔��T�̎�ɂ��A�a�����Ƃ��ꂽ��f�̋����������ƒ݂艺����ꂽ�B�����ɏo���������̂́A�ŕa��C���ꂽ����ȊO�͋ߊ��҂��Ȃ��A���܂ɖ���̓������������ɂ��Ă��A���Ԙb�����������ɋA���Ă������B�a�̓`�������ꂽ���T�́A�Վ�葧�q�̕a����̂����ɂ��邱�Ƃ���������A�قƂ�NJ�������Ȃ������B
�@����ȂȂ��ł���c�͏o���̋A��݂̂Ȃ炸�A�x���ɂ��킴�킴���߂��瑓��Y�̌������ɂ���Ă��āA���Ԃ̋�������a�l�̖����Řb������ł������B���ɂ͓�l�̒k���鐺���A���Ő��������Ă������ɂ����������B����ȂƂ��̕v�̏����́A�ƂĂ��Q������̕a�l�Ƃ͎v���ʂقǂ̊��C���������āA��������U���Ĕ��ނ��Ƃ��������B
�@�����Ƃ��Ȃ�A�������̎R�Ɨ����̒��H���O�l�����ɂ����B����ȂƂ��A�����̗��e�Ŕ�������c�Ɩ�����A�����납�琶�^�ʖڂȑ���Y������ɏ�k�������ď킹���肵���B
�@�[���߂��Ƃ��Ȃ�A���c��ɂ��ޑ���Y�̖����𗣂�ċA�H�ɂ���c�́A��e�Ō��������Ɂu�߂������ɁA�܂��Ē����܂��v�ƌ��t���Ȃɕʂ���������B�Z�����߂̍��Ԃ������Ă܂ŁA�킴�킴����Y�̌������ɗ��Ă�����c�ɑ��āA����͂��̔w���ɐS���Ŏ�����킹��̂������B
�@�L��ȋv�����~�̐��̊O��ɂ��鈢��ɓ��̂���������Q���A���낻��ӂ�������Ƃ����O�������̂��ƁA�����̌������ɑ����̗����畃�e�̗NJo���K�˂Ă��Ă��ꂽ�B�v���U��Ɋ���������e���������A�ꉮ�ɋ��锋�T�ɂ͉��悩�爥�A�����������ŁA����ɂƂ��ĕԂ��Ƒ���Y�̖����ɍ����Ă��̑����ׂ������ق��Ă����葱���A���̕�ꎞ�ɂӂ����ё����ւƖ߂��Ă������B
�u����Ȃ��킢�̂��A���܂������������ȁv
�@�ʂ�ۂɈꌾ�ꂭ�悤�Ɍ����c���ċA���Ă������e�̌��p�ɁA����͒ǂ��Ă����A�������ċ��������Փ��������ɂ��炦���B
�@�C����蒼��������́A�����̂悤�ɕꉮ�̑䏊�ł����炦������Y�̗[�H���g���ė���ւނ����Ă����B��قǂ��痼��Ŏx�����z�Ђ��������~����̓������A�Ȃ������̓��Ɍ����Ă��܂�Ȃ��s���Ɏv�����B���̕a�͎��{���Ƃ�̂��B��̗Ö@�ƁA���l���͂��Ă��ꂽ�Ă����V�̓��������炸�A�Ƃ��Ƃ��r�̒[�ɂ������܂��Ă��܂����B
�@�������q�f���������ƂӂƖڂ��グ��ƁA�r�̌����������甒���e��������������ƉM���Ă���B��U��̑̋�Ƀs���Ƃ������傫�ȗ����A�S�g�𔒖тɕ���ꂽ�ς�����B
�u�M���c�c�v����͎v�킸���ɏo���ċ��т����ɂȂ����B
�@����Ƃ��̔��ς̏o��́A�Z�̗c���̍��������B�܂������ł͌{�������邲�ƌςɏP�����Q�����o���Ă��āA�Ƃ��ς₵�����l�����ɂ��ώ�肪�����Ȃ��Ă����Ƃ��������B���������̐��Ƃł��鎛�̗��R�ŁA�q�A��̎��ς��t�ɏe�Ō����ꂽ�B�e�ς̂��ɁA���܂�ĊԂ��Ȃ��l�C�̎q�ς������B�����₦�₦�̐e�ςɗt���Ƃǂ߂̈��������������Ƃ������A�����Ȃ���e�̓���ɗ����͂������Čς��������̂����ゾ�����B
�@�v�������ʎ��ԂɁA�������������ӎu��r�������t�ɑ���A�q�ς͏������e�ςƂ��ǂ������킹�����l�ɂ���ĎE���ꂽ�B
�@�ς̎��[��S���ŊF�������グ�����ƁA�V���b�N���ĕ��S��Ԃł�������́A�������班�����ꂽ��̖݂̉A�ɁA������C�̎q�ς�����̂ɋC�t�����B���̎q�ς͕�e��Z�킪�E�����̂��A�������猩�Ă����̂��A�낤�����E���������q�ς����͘A��ċA��A��Ă邱�Ƃɂ����B�ѕ��݂������ڂɋ�F�������Ă������߂ɁA�M���Ɩ��t���ċ߂��̔_�Ƃ���R�r�̓����킯�ĖႢ�A�����ɐ��b�������B���̍b�゠���Ďq�ς́A���N��ɂ͗��h�Ȍςɐ������Ă����B
�@���Ōς������Ă��ẮA���̏O�Ɍ��������ʁA�Ƃ������e�̖��߂ŁA����͐S���������v���ŗ��R�ɃM����������̂������B�u�M���A�R�̉��ւ����ĕ�炷���A���߂Â����炠�����v��肩�������ɃM���͌����Ȕ���U���ĉ����A�܃��[�g����������ĐU��Ԃ�A���U�����ɃL�����ƂЂƚe������Ɩؗ��̖݂Ɏp���������B
�@�\�N���o���ċ��s�̏��w�Z�Ŋ�h�ɐ������������オ�A���Ɉ�x�͋D�Ԃ̉w����O�L���̓�������Ď��Ƃ֖߂����B���܂ɖ铹��������Ƃ�����A����Ƃ����̓o���������܂ł���ė��āA��������ɉf���锒���e��ڂɂ����Ƃ��A�v�킸�u���܂��M�������v�Ɩ₢�����Ă����B�M���͌����Ȕ���傫���U���ĉ����A����͉��������̂��܂�ɗ܂����̂��B���ꂩ��͓������Ă��瓻���z���܂�ɂ́A�K���M��������Ė���̂��Ƃ�t�������ꂸ�ɉƂ܂ő����Ă��ꂽ���̂������B
�@����ɂ��Ă�����̐��܂ꂽ�������̗����炱�̈��؏W���܂ł͑召�܂̎R���z���˂Ȃ炸�A�D�Ԃɏ��Γ�w�̋���������B�M���͂Ȃ�ƌ܂̎R���z���Ĉ��܂ŋ삯�����Ă����Ƃ����̂��A����Ȃ��Ƃ�����̂��낤���A���オ�s�v�c�Ȏv���ɂ����Č��߂�ƃM���͂����Ɛg��|���Ē�̖݂Ɏp���������B�M�����g��|���܂�́A�傫�����˂��^�����������܂ł�����̖Ԗ��Ɏc�����B
�u�ǂ����C����������A�Ђ���Ƃ��Ĉ��j����������v
�@���̂����ɋN���オ��������Y���[�H�̑V�ɂނ����A������Ȃ����������������։^�яo���ƁA����͋C�ɂȂ�Ǐ���ڂ����Ƒł��������B
�u�Ԏ����ł����̂��c�c�v
�@����Y�͔����x�߁A�j�����˂��o������������ɂނ����B���オ���������m��Ȃ��������ƁA���s�ɎY�w�l�Ȉ�@�����Ă��鉓���̐e�ʂ����邩��A�����ւ����Đf�Ă�����Ă����Ƃ������B
�@���̂��됊�オ�ڗ�����Y�͑�V�����ȓ���ŕz�c�̉����߂���A�~���Ă������܌��̂Ȃ������~�D�Ō܉~�ƌE�K�ʓ����o���Ė���̎�Ɉ��点���B���T�ɂ����Ă��A����Ȕ�p�ǂ��납���Ȃǂւ������Ƃ��������Ȃ����Ƃ��A����Y���킩���Ă���̂��B����̋����͂��ׂĕ�e�ɍ����o���Ă���Ȃ��ŁA�����Ə������ߍ���ł����̂��낤���B
�u�K���]������߂肪���Ɋە��֊���āA�o�^�[���Ă��Ă���v
�@�Ȃ��D�P�����ƒm���A�䂪�q�̊������܂ł͏o���������h�{��ۂ邱�ƂŐ����Ă������Ɗ肤�v�̎v�����A����ɂ͐Ȃ������B
�u���܂��������ւ��邿����ƑO�ɁA���Ȗ����݂��v
�u�ց[���A�ǂ�Ȗ��ł��̂��v
�u�Ȃ������킩��A�l���^�����Ȍς̔w���ɏ���Ă���B�ς͂��̐��������ŋ삯�Ă��āA�l���܂��U�藎�Ƃ���܂��ƕK���Ōςɂ����݂��Ă���A���Ȗ����Ǝv��v
�u�ق�܂ɁA���Ȗ�������͂�܂����Ȃ��A����łǂ��ւ����͂�����ł��v
�u�����A�����Ŗڂ��o�߂Ă���������Ȃ��A���̐��̋Ɋy�ւł��A��Ă����Ă����Ƃ������������m���v
�u�܂��A���̐���Ȃ�ăQ���̈������Ƃ��c�c�v
�@�v�̌��t��ł������Ȃ���ڂ𗎂Ƃ�������́A���{�̔����b�т������̕~���z�c�ɕt�����Ă���̂ɋC�t�����B
�@���J����������ɓ��̍����U��n�߂��l���\����̒��A����͏��̓�ԗ�Ԃɏ�邽�߂ɁA���I�̐l�蓻��a�c�̉w�ւƋ}���ł����B�Ƃ͑����̂܂��Â�������A�W���̈����R�w�ł̍u�̒��Ԃ琔�l�Əo�����Ă��āA���̗�����K���ɋ��s�ւ������Ƃɂ����̂��B�a�l��u���ďo������̂͋C�����肾�������u���̋@���A�������ւ͂�����Ȃ����v�ƌ�������Y�̌��t�ɉ�����A�������Ƃ����S�����̂������B
�@�a�c����D�Ԃœԋ߂������ċ��s�ɒ���������́A���w����������̒n�ʼn߂��������Ƃ������āA�������ƂȂ��ړI�̈�@�ւނ������B�{���ɂقNj߂��x��ʂ�ɖʂ����A�����ȗm�ٌ��Ă̕w�l�Ȉ�@�Őf�Ă���������ʂ͔D�P�l�����Ƃ������Ƃ������B�v�������Ă��ꂽ�Љ�����ǂ������V�̈�t�́A����Y�����j�̗×{���ł��邱�Ƃ�m��ƋA��ɑ�R�ȉh�{�܂��������Ă��ꂽ�B
�@���s�w�܂ŗ��ĉw�̎����\������ƁA����̕��m�R�s�ɏ��Ύl���܂��ɓa�c�w�ɒ����A��������l�蓻���ꎞ�Ԕ��������ĉz���Ă��[���̘Z���ɂ͋A���B�Ƃ��߂锪�����܂łɂ́A�[���ɊԂɍ������B���܂��炾�ƋD�Ԃ̎����܂ł��Ȃ�̎��Ԃ�����A����͉w�O�̊ە��S�ݓX�ւ������B����V���̃x���`�Ŏ����Ă����ٓ��̈���т�H�ׂ����ƁA�n���̐H�i�����Ńo�^�[�����B��@�Őf�Ñ���܂��Ă��ꂽ���߁A���̕��ő���Y�ɐH�ׂ����悤�ƁA���łɗg�����ẴJ�c���c�����B
�@�߂�̋D�Ԃɂ̂��Ă���̖���́A�v���Ԃ�̊O�o�ɂ���ꂩ�炩��Ԃ̐U���ɐg��C���Ă��炤��Ƃ��Ă����B�ӂƖڂ��o�܂��Ă����ǂ̕ӂ肩�Ƒ��̊O�ɖڂ����A�����藧�����J�Ԃ̉w�ɋD�Ԃ͎~�܂��Ă��āA�͂邩�����ŗ��ꂪ�����A�����Ċ������ł���B�ׂɏ�荇�킹����q�̌����ɂ́A������\���߂����ےË��̉w�Ɏ~�܂����܂܂炵���B���̂Ƃ��ԏ�������Ă����B�T���w�̃|�C���g�̌̏�ɂ��A��Ԃ̔������ł��Ȃ��Ȃ��Ă���Ƃ��ŁA���܂��炭�҂悤�ɂƌ����Ď��̎ԗ��ֈڂ��Ă������B�D�Ԃ̓������x��Ă��܂�x���Ȃ�悤���ƁA�������Ă��܂��Ă��瓻���z���˂Ȃ�Ȃ��Ȃ�A����͍��������ƂɂȂ����Ǝv�����B
�@����ƋD�Ԃ������o�����̂́A���ꂩ��O�\���������Ă���œa�c�̉w�ɂ͈ꎞ�ԋ߂����x��Ē������B������ɂ͂��łɕ�F���Y���Ȃ��A����͐l�蓻��ڎw���ċ}�����B�Â���̓������������A�Ƃ̔��T���x���A�蒅�����Ƃ̕������|�낵�����Ƃ������B
�@���łɉw�܂��̏��X�X�ɂ͖����肪�_���n�߂Ă��āA����Y����������̏��Ȉ�@�̂܂���ʂ�߂���ƁA���Ƃ͎���ɔZ���Ȃ�[�ł̂Ȃ�����l�ł����˂Ȃ�Ȃ������B
�@�₪�đ�������O��ēc����ɂ����钾�������A�����ɋC�����Ȃ���n�邱��ɂ͓��͊��S�ɕ�ꂫ���Ă��܂����B��������n��Ƃ�������͓��̓o����ł���A�R�ɕ�������ɂ�����������̐���������ؗ��ɎՂ�ꓥ�ݕ����铹�����łɖ�����Ă��܂��B���Ȉ�@�ɗ������Β��炢���ꂽ�낤�ɁA�C�����������ł邠�܂�ɁA�����܂ŋC���܂��Ȃ��������Ƃ��A����͂��܂���ɉ���B
�@�����`���ɂ��A���Đ퍑�̂��눢�ؒJ������Ƃ���v���ꑰ��T���Ɠ��荞�Ԏ҂�h�q���A���̐g������ĕ߂����ƁA���̓��Ŏa�ꂽ�B���̌̎�����A�����������Ăꂾ�����Ƃ����l�a�蓻�̈ł́A�Ö�̖����̂悤�ɖ���̂܂��ɗ����͂�����B
�@���������Ȃ���Èł̂Ȃ����A����o���̍��ɉ��x���T���]�т����Ăǂ̂��炢�������̂��A���낻��M�\�˂̂�����܂ł��Ă���͂����B�M�\�˂���͈�i�Ɠ����������Ȃ�A���悢�擻�z���̓�ɂ���������̂��B����炵�Ȃ���z�̊���@�����Ƃ��A�ڂ̑O�𔒂��e���悬�����B������Ƃ��Ĉłɖڂ����炷�ƁA�����e�͌܃��[�g���قǗ��ꂽ�Ƃ���ł����Ƃ���������Ă���B�Èł̂Ȃ��ɕ����o���悤�ɁA�����������ڂ����Ɣ����B
�u�M���c�c�v
�@�v�킸����̌������ďo���Ăт����ɁA����͂���ɓ�����悤�ɔ������������ƐU���Ėؗ��̈łɐg��|���B�e���ꂽ�悤�ɖ���́A�M���̔����e��ǂ��ċ삯�����Ă����B�w�ォ�畢���킳��ł̂Ȃ����A�������点�ĒJ��֊����ł�������ƒ��ӂ��Ȃ�����A����͌����B�ꂷ�锒���e���������܂��ƌ����ɒǂ����B��������M���͎��X�~�܂��Ă͌���U������A���オ���Ă��Ă���̂��m�F���Ăӂ����ы삯�o���B
�@�擱����M���������~�܂�ƁA�ˑR�Ɏ��E���J����������ɏ����ȓ������ꂽ�B�Ȃ�Ƌv���Ƃ̈ʔv���ł͂Ȃ����A����ɖڂ�]����Ɗቺ�ɗƂ̉Ƃ̘m��������������A���̂ނ����ɍ��X�Ƃ��Ėؗ��Ɉ͂܂ꂽ�v���̉��~������B�v�킸���g�̗܂�����̖j��G�炵���B
�u�M���A�������ɁA�������ŏ���������v
�@���オ�U������Đ���������ƁA�M���������悤�Ȏd���Ŏ���㉺�ɐU��A���̏u�Ԑg��|���Ăӂ����іؗ��̈łɋz�����܂�Ă������B
�@�Ƃ̒��ʂ蔲���ď�����̌˂��J����ƁA�K���܂��Ƃ͖߂��Ă͂��Ȃ��l�q���B�����������ʂ܂܂ɁA�}���ŗ[�т̕Ă��Ƃ��J�}�h�֎Ă����ׂ�Ɖ������B�A���҂���тĂ���ɈႢ�Ȃ��v�̂Ƃ���ւ����ƁA���������Ƃɖ����̎��v�͂܂����̌��̎����܂��ł͂Ȃ����B
�@���オ�T���w�̎��̂Œx�ꂽ���Ƃ�l�т�Ɓu�������͂��葁���߂�Ă悩�����̂��v�v�͑���������ق�������B����ɔD�P��������ƁA�G�ɂ��������̏���ق��Č��߂��B�����ׂ����r�Ƃ͑ΏƓI�ɁA���i�����Ƃ̂܂܂ňٗl�ɑ傫���݂���v�̏��������T�炩�猩�߂��B���܂ꂭ��䂪�q�̊������܂ŁA�����Ă�����̂��A����ȑ���Y�̎v�����`���悤�Ŗ���͊���Ȃ��Ȃ�u�[�т̂����炦�����Ă��܂��v�ƌ����A�������܂ꂸ�ɍ��𗧂����B
�@�M���͖�����������炻��āA�b�����꒼���ɋ삯�����ċv���̉��~�̗��R�܂ŘA��Ă��Ă��ꂽ�̂��B���̂��߂Ɏv���̂ق������߂�āA�Ӕт𐆂����Ƃ��ł����B����ŌƂ��߂��Ă��Ă��A�Ȃɂ��Ȃ�������Č}������B�M���͍������炪���ޑ����J�ɂނ��āA�R�����삯�Ă���ɂ������Ȃ��A�ꉮ�Ɍ������Ȃ������͍��X�ƘA�Ȃ�R���݂��ӂ�����B
�@�c�A���̂���ɂȂ�Ƒ���Y�͑̒��̗ǂ����ɂ͏�����N��������A�����ɏo�ĉ��~�̂܂��ɍL���鑁�c�̗ɖڂ��ׂ߂Ă��邱�Ƃ�����A�T�ڂɂ͉�����悤�Ȋ�]�����������B�O�x�̔тɃo�^�[��h���ĐH�ׂ�ȂǂƁA�w�߂Ď��{��ۂ����̂��悩�����炵���B�Ƃ��낪�����ɓ���Ƃӂ����ѓf��������Ԃ��āA���ɂ����܂܂̓���������悤�ɂȂ����B
�@�Ƃ̔��T�͖���̔D�P��m���Ă�����u��v�ȐԎ����Y�ނɂ͑̂�����̂���ԁv�ƌ��������A�Ȃ��C�������Ƃ��Ȃ������d����R�ł̐d���Ɏ����玟�ւƎd�������������B
�@���̍��̖���̗B��̊y���݂́A���Ɋ��x���K���X�֔z�B�v�ƒ�ŗ����b�����邱�Ƃł������B�X�֔z�B�v�͑���������a�c�w�O�̗X�ǂ֒ʂ��Ă��āA������킹��Ζ���̗��e�̗l�q�⑺�̏�b���ĕ������Ă��ꂽ�B�ݏ������Ȃ��Ƃ����C��������A�Ƃ��ɂ͒��b�Œk���邱�Ƃ�����A���ꂪ�܂����T�̋t�ɐG�ꂽ�B
�u�X�֕v�Ȃ�ǂƗ����b������Ƃ́A�͂����Ȃ��A�v���Ƃ̉ł��Ƃ����̂�Y���ȁv�Ɣl��A�ڂɂ́u�v���͎m���̉ƕ��A�����Ă���͑₶��v�ƌ����̂����Ȃ������B������~�ɕ����Վ�葧�q�̓f�����錌�́A���łɕ��L������Ă���Ƃ����̂ɋC�ʂ����͍��������B
�@�����͋��̋_���ՂƂ��������\�Z���̖�̂��ƁA�[�H�̑V���܂��ɍׂ��H���̔����x�߂�����Y�́A����ɂނ����Ďv���l�߂��悤�Ɍ�肩�����B
�u���܂�Ă���Ԏ��������������A�v���̐e�ʂւȂƗ{���ɏo���Ă��܂��͑������A��B�������j�̎��������A���܂��̎���Ƃň�ĂĂ���v
�u�܂������Ȃ艽������͂�́A�܂����܂�Ă�������q���悻�l�ւ���́A���A���̂Ɩ��Ȃ��Ƃ��v
�u�����������悤�ɂȂ�����A���̂������͂�̂��ƂŎq����Ă�͖̂������Ǝv���B�悢������������č�����̂�A���݂Ƃ��ẮA�j�̎q�Ȃ�v���̐��������Ă���v
�@���������I���Ƒ���Y�́A���f�����ʎ����̖�����u���������Ɍ��߂��B
�@�����̒��߂��A����Y�͚삵���f���̂Ȃ��Ŏ��B���N�O�\�B�����A����Ő��������Ă������Ɍ������āu�����͋_�������̂��v�Ɛ����������̂��Ō�̌��t�������B���オ�삯�����Ƃ��ɂ́A����̓f���ɐ��܂�������Y�̎��Ɋ���A��������悤�Ȑ�̖�����������芪���Ă����B
�@�v�̑��V�ɂ́A���������܂Ŗʎ��̂Ȃ������v���̉����̐l�X�炪���X�ɖK�ꂽ�B�������ł����̒���q�ł������Ԃ����v���̉��~�́A�v�X�ɉ������Â�����킢�ƂȂ����B�o�����ő��V�ɊԂɍ���Ȃ�������c�́A�������̖@�v�ɂ��������B
�@���V�����ނƍQ�����������ɂ����o�����B�㌎�ɓ���Ɩ���͂��̒n���̏K���ł���A�ł̎��Ƃŏo�Y�����邽�߂ɔ��T�ɉɂ�����B���T�͗����������̂́A�ƂƂ��Ă˂��炢�̌��t���������łȂ������B���Ƃ��甪�ΔN���̒�_��}���ɂ���Ă��āA����͗Ռ��̕����������đ������֖߂�A���̌����ɒj�����o�Y�����B
�@����̕��e�͔��T�̂��Ƃ֎莆���o���āA���̎|��`���������T����͉��̕Ԏ����Ȃ������B��ނ������ɕ��e�́A���܂ꂽ�q�̑\�c���ɂ�����A�c�̎u�m�ł������v���b�����Y�@�r�̖��O����ꎚ���Ƃ��ĉb��Ɩ��t�����B
�@���a�\�ܔN���������������ƂŌ}��������́A���ƂɋC����������̈ӌ��ŔN�������X�̈ꌎ�\���Ɉ��؏W���̋v���ƂɌ��������B�ϐ�̂��߂ɓ����z�����Ƃ͊��킸�A�����̔n�ԓ�������Ė߂��Ă����B
�u���͑�����̂��A����Y�Ɏ��Ƃ�̂͐F���ȂƂ������ŁA�痧���̔ڂ����Ƃ���͖��エ�܂��̕��̌����Z���Ⴀ�v
�@���T�͊��Ŗ�����}�������ǂ��납�A�S�ӓ��ɂ�����Ȃ������̊�������~�̉������猩���낵�Č������ƁA�҂����Ə�q�����߂Ă��܂����B���T�ɂ���Ζ���̂��Ƃ́A�łƂ����������������l�}�������炢�̎v���������̂��낤�B���q�������܁A����܂Ƃ��ȗc�q������Ė߂��Ă�������́A�T���������݂ł����Ȃ������̂�������Ȃ��B
�@���̒a������Ԃǂ��납�A������ق��̔��T�̑ԓx�ɁA����͉Ƃɓ��邱�Ƃ������̈�t�����]���邱�Ƃ����킸�A���������߂��Ă������Ƃ����̂܂ܗ������邵���Ȃ������B
�@�r���ɂ�����͂���ɂ��鈢�ؐ_�Ђ܂ł����Ƃ��A����͕��݂��~�߂��B���̊Ԃ̎v�Ă̂��ƁA�����ɑ��ݓ����ƎГa�Ɍ��������B�܂������̌�_����������ꂽ�܂܂̎Гa�̂܂��ŁA�w���̉b������낷���ΑK���̘e�ɂ����ƐQ�������B�v���Ƃ����Ƃɂ���Ƃ��g���Ă����A��̖T�ɗ��Ċ|���Ă������v���Ƃ̉Ɩ�����̓��P���L���Ԏ��ɂ���������悤�ɂ��Ēu�����B
�@�����Ă���q���ڂ��o�܂����Ă͂Ƃ̎v������A��͖炳���Ɏ�����킹�A�ǂ������̎q������肭�������A�Ƌ��̓��ŔO�����B�Q��˂��ɂ���܂ꂽ�䂪�q�̊������x���߂�����́A�v����U����ĎГa�����Ƃɂ����B
�@�������o��Ɩ���͈ꍏ���������؏W�����牓�����낤�ƁA���܂܂łƈ�]���đ����ŕ������B�W�����痣���Η����قNjv���Ƃ������Ȃ�̂��B�v����Y�̈⌾�����邪�A�b��͎����̑��q�Ƃ��ĂłȂ��A�v���Ƃ̂�������l�̐Վ��Ƃ��Đ��܂�Ă����̂��B������Ύ����̎�ň�Ă���A���T�̂��Ƃ֕Ԃ��̂����R���낤�B���̕������̎q�ɂƂ��Ă��K���ɈႢ�Ȃ��B
�@�������Ȃ瑺�A��N���������āA���T�̂��Ƃ֘A��Ă����Ă����ɈႢ�Ȃ��B���̎q�͋v���̌����p�����q�Ȃ̂��A����͕����Ȃ��牽�x�����������Ɍ������������B�����q�포�w�Z�̂܂����߂���ƁA�z��𑖂�R�A���̓��ɂނ��ď���̓����}�����B
�@�s���D�J�����������̊ԍۂɂ���g���l������A�����Ȃ荕����яo���Ă����B�l�����ɋC���Ƃ��A�x��@�̉��������ɓ���Ȃ������̂��B�@�֎Ԃ̃h���[������f���o�������C��S�g�ɗ��тȂ���A����͂��낢���ڂŒʉ߂��Ă�����Ԃ����߂��B
�@�ӂ����ѕӂ�ɐÎ₪�߂����Ƃ��A����͎��̉��ŐԎ��̋����������B�t�߂����܂킵�Ă�����炵���l�e�͂Ȃ��A�C�̂������Ɠ��̌��������ɖڂ����Ƃ��łɉw�߂��܂ŗ��Ă��āA���Ƃɂ͂��łɖ����肪�_��͂��߂Ă���B�܂������߂������炢�Ɏv���Ă������A����Ȃɂ����Ԃ��o���Ă���̂��B��u�u������ɂ��Ă����䂪�q�̊炪�����B����͂�����n�߂���̂Ȃ����ł��Ƃ��������삯�o���Ă����B
�@��l�O�l��������܂킵�Ă���Ƃ������̑������̋����͂��߁A�Ȃ▸�̌Öɕ���ꒋ�Ԃ������Â����ؐ_�Ђ̋����́A���łɑ��������ڂ��Ȃ��قǏ��ł��Ƃ�܂��Ă����B�K���ʼn䂪�q�̎p�����߂ĎГa���ΑK���삯���A�Â���ɂڂ��蔒���e�����Â��܂��Ă����B�܂�ŔE�ъ���C�����邩�ɁA����͐Q��˂��̗c�q�Ɋ��Y���Ă���B
�u�M���c�c�v
�@�����������܂ܐ�傷�����������Ƌ����������e�́A�̂�����Ɨ����オ��ƎГa���̐�̎Ζʂɒ��˂Ďp���������B
�@�Q��˂��ɂ���b�������A�v���Ƃ̖�O�ɗ��������Ă����������ĉ��~�̂Ȃ��֘A��ē������̂́A����Œނ�グ��������͂��ɂ���Ă����F���������B�F���͋v���̉��~�Ɉ�ԋ߂��Ƃ̎�ŁA��X�v���Ƃ̉Ɩl�ł������B���܂ł��A��������j�肪���Ȃ��Ȃ����v���Ƃ̎G�p���A���V�Ɉ����Ă���Ă���̂������B
�u���������A���Ȃ����đ���Y����̖Y��`���̂ڂ���A��Ė߂�₵���̂ɁA�剜���܂��̂킵��������݂܂��ŁA���������Ǝቜ���܂��Ƃɓ���Ă����Ƃ���₷�v
�@����Y�������ƈȑO�ɂ��܂��Ċ�ȂɂȂ������T���A�F���̌������Ƃɂ͖ق����������B����͂��̏�ɗ����킹���F���̂Ƃ�Ȃ��ŁA�ӂ����ыv���Ƃ̉łƂ��Ė߂邱�ƂɂȂ����B
�@����͖߂��Ă�����ꉮ�ɂ͏Z�܂킳�ꂸ�A����Y�����ʂ܂ŕ����Ă���������~�ŐQ�N���������B����̌����ɂ͑���Y�̎�����ς�炸��f�̋����͉�����ꂽ�܂܂ŁA�܂��x�a�̋ۂ��c���Ă������m��ʂƔ��T�͂�������苎��̂��ւ��A���g������ɂ͖ő��ɋ߂Â��Ȃ������B
�@�l�C�̎��a�������T�́A�\���Ɉ�x�̖��Ⴂ�Ɉ�@�ւ����̂��A�F���ɂ͗��܂��ɖ�������������B�l�蓻���z���A�����O���Ԃ̓��̂�����͓a�c�w�O�̏��Ȉ�@�֒ʂ����B
�@�܂��h�����ċv���Ƃ̎c�Ƃ��������吳��������܂ł́A���Ȃ̉ƂƂ͐e�ʂɓ������������ł������Ƃ��A����ȂƂ��납��@���̏��Ȍ[���Y�́A����̊���݂�ƕK���w���̓����̈炿��������Đf�Ă��ꂽ���A�����Đf�Ñ���Ƃ�Ȃ������B�v���Ƃ̓���ɒʂ���ނ͌Ƃ̔��T�̐������悭�m���Ă��āA���オ��サ����������ė��Ă��Ȃ��̂��@���Ă����̂��B
�@���ؒJ�ɉĂ��K�ꂽ������A��̍_�����Ă����B��e���Õz�ŖD���グ�������͂��ɂ����̂��B���̂��ƁA�C�R�ɂ��钷�j�̎O�Y�̖ʉ�ɁA���e�����ƈ���̗��ꂽ��̑O��Ƒ��ŁA���܂ł��������Ƃ�����B
�u���ꂿ��A�ǂ����Ă��O�Y�Z�����̖ʉ�ɂ��������ƁA����������������������v
�u���̎q���Ƃɂ���Ƃ��ɂ́A���ꂿ���������Ə����������Ă��̂ɂȂ��v
�@���������Ȃ�����A����ȕ�e�̋C����������ɂ͂悭�킩��B
�u����O�Y�Z������A�Z����炪�ʉ�ɗ���̂�m���Č��t���悤�Ɣ����Ă����炵����v
�@�_��͂��������Ȃ���A�����炩�����G�X�����݂����o������ɓn�����B��݂��J����ƁA�c���̊v�C�Ǝ�܂������Ă���B
�u�܂����܂ꂽ����̐Ԃ�V�ɁA�C�̑����q��v
�@�ق�܂ɂ��̎q�炵����A��\�̒���������������̂��̏t�A�C�R�ɓ���������ΔN���̒�O�Y�����͎v�����B
�u���A���ꂩ��A�M�������̗��ɂ����ꂽ�炵���A�ƌ�������A�M���͋��̈����R�ɐ��݁A�S�\�N�Ԃ����������Ă���Ƃ����Ìϔ��S�ۂ̌��������ς�����A��ɑ����J�ƈ����R�̊Ԃ����������Ă���ɈႢ�Ȃ��B���͂��̒��Ԃ�����A�r���ł�����Ɨ���������̂��낤�����āv
�u�܂��A�O�Y�ɂ���Ȏ��܂Ō�������c�c�v
�u�����������Ǝu�]���������āA�O�Y�Z��������A�{���ɂ��������m���ȁA�Ƃ����C�ɂ����邩��Ȃ��v
�@�_����S�����悤�Ɍ����̂��āA�ѕs�Y�݂����ȗ��s��ƂɂȂ��Ă��A�ƌ����Ă͏�����ǂ݂������Ă����O�Y�A�C�R�̂Ȃ��ł͏������ǂ߂Ȃ����ɁA���̎q�����Ă���ȁA����͖{�D����������ɉ��߂Ďv����y�����B
�@�x�a���҂̂��邤���͖K���҂��₦�Ă����v���Ƃɂ��A���N�ɂȂ��ēx�X���l���K���悤�ɂȂ����B���̖w�ǂ��g�傷�����́A�嗤�̐���։�������Ă�����҂������B�ނ�̖ړI�͑q�ɓ��荞�݁A���X���鍜���̂Ȃ�������{���������������Ƃ������B�����Ď荠�ȓ���������ƁA�������蓁�ɂ��Đ�n�g���Ă����̂��B���T�͂����������Ƃ��A�����̂��߂ɂȂ�Ȃ�Ɨe�F���Ă����B�Ȃ��ɂ͌�����ʊ�������ł���Ă��āA���炩�ɍ������l�ƌ������l�����q�̂Ȃ��֓����ĕi��߂����Ă��邱�Ƃ��������B
�@���܂��ܔ��T�̉��f�ŋv���Ƃ�K�ꂽ�A���Ȉ�@�̉@�����Ȍ[���Y�����̗l�q��ڂ̓�����ɂ����B��������w�����Ƃ̌����������ނ͈�҂Ƃ��Ă̐M���������������A����ŋ��y�j�����ƂƂ��Ă�����m���Ă����B�[���Y�͂��̏�ŁA�q�̒��̍����i������̎���ŕۊǂ��邱�Ƃ�\���o���̂������B
�u�ڂ�傫�イ�Ȃ�͂�����A�����ӔC�������ċv���Ƃ̗��j����������Ɛ������܂��v
�@�M�d�Ȏj���̗��o���뜜�����ނ́A���������Ĕ��T�����������ƁA����ɑq�̎������̑唼�ɂ�����唪�ԎO�䕪�̍������A����̑q�։^�э��ނ��ƂɂȂ����B
�u���炢���Ƃǂ��A��w�����n�܂�����A���k���F��Ȃŋc��m�b�����Y���܂̂���ւ��Q�肷�邱�ƂɂȂ����炵���ǂ��Łv
�@���������ĖF������э���ł����̂́A������\�l����᱗��~��̓��̗[���������B�܂����v���Ƃ̉��~���ɂ��鈢��ɓ��̂܂��ŁA���T��M���ɖ����ߗׂ̏��[�q���炪�~���ꂽ�S�U�Ɏԍ��ɍ���A�傫�Ȑ�����Ȃ����r�̂����a���Ă���Œ��ł������B
�u�Ȃ�ł��A���ꂩ��͖���������������Ƃ��āA�w�Z�̐��k���_�ЂɏW�c�Q�q���邱�ƂɂȂ��������ȁB����Ŋ������̊w�Z�ł͋c��m�b�����Y���܂̂�����A�Q�q���|�����邱�ƂɂȂ����炵���ǂ��B�ڂ��������܂�₵�����A����ŋv���Ƃ��܂��ċ��̓����J����܂��Łv
�u�ق�ɗ_��Ȃ��Ƃ���v
�@���������Čւ炵���ɊF�̊�����n�������T�́A�O�ɂ��܂��Č�r�̂������鐺����i�ƒ���グ��̂������B�G�̂����ɉb������点������́A����Y�̎��㏉�߂Ă݂��锋�T�̐��ꂪ�܂����\��Ɍ˘f���Ȃ���F�ɂ��Č�r�̂��������B
�@�₪�ē�w�����n�܂�ƁA�㌎����̎n�Ǝ��̂��Ə��w�Z�����L���ȏ�����ꂽ�v���Ƃ̕�n�ցA���@�Ɉ������ꂽ�w���̎Q�q�������Ȃ�ꂽ�B����ɖ���͂��̓����A��p�����Ƃ��đ����q�퍂�����w�Z�ɋ߂ɏo�邱�ƂɂȂ��͓�\���~�ł������B���X�ƕ����ɏ��W����Ă����j�������̌�����₤���߂ɁA������Z���̈ӌ��ł��̑��ł͐����Ȃ����w�Z���o������ɁA���H�̖�������̂������B
�@����̎����͈�N���Ŏ�������\���l�̊w�����������A�_�Ɋ��ɂ͗c����w�����ēo�Z���Ă��鐶�k�����āA����͂��̃I���c�ւ��Ȃǂ̐��b�ɂ��ǂ�����X�������B
�@����ł͖��オ�߂邱�ƂɂȂ�ƁA������ɂȂ�������̉b��́A���T�ƖF���̏��[�ł���R�g���ɑ�����邱�ƂƂȂ����B����܂ʼnb�����x�����������Ƃ��Ȃ��������T���A����������ւ̂��������Ƒ��̖ʓ|���݂邱�Ƃ��������̂��B�����Ƃ����ۂɂ́A�q��̖w�ǂ��R�g���C���ł������炵�����A�H�̔_�Ɋ��Ƃ��Ȃ�ΖF���̉ƂƂĔL�̎���肽���قǂŁA�ۉ��Ȃ��ɔ��T���݂�ق��Ȃ������B
�@���T�͉b�ꂪ�c��������ƁA������͂��Ȃ������B�e���������A��q��j�����Ƃ����Ă͗��ɂ��Ē�Ɉ����o���A���|�̕ڂŋ�����߂��q�̐K��ł��������B����Ƃ������ڌ������R�g�����u�^�Ƃ͂����A����ł͂ڂ���z�ǂ��v�Ɩ���Ɍ����t�����B����ƂĖ���͔��T�ɍR�c���邱�Ƃ��ł����A����ł͉b�ꂪ�s���ŏ��Ȉ�@��K�ꂽ�܂�ɁA���߂炢�����̂��Ƃ��@���̌[���Y�ɑł��������B
�@�b�����[���Y�͑����ɁA����Ȃ璋�Ԃ͂����֘A��Ă����ƌ����Ă��ꂽ�B���ȉƂɂ͌[���Y�̍Ȓq���q�ƁA��l���̗��q�������B���q�͉b����O�ΔN�������A�b��ƗV���ɂ͊��D�ł��낤�Ƃ����[���Y�̔��f�ł������̂��낤�B
�@���ꂩ��ԂȂ����Ė��オ�w�Z�߂ɏo����Ɍ���A�b������ȉƂɗa���邱�ƂɂȂ����B����̋߂鑺���̐q�포�w�Z�͏��Ȉ�@�Ƃ͈�L�����܂�̋����ŁA�b���w�������I���܂l�蓻���z���ĉw�O���X�X�̈�s�ɂ�����Ȉ�@�ɗ������A�q��a����Ƃ�������w�Z�}�����B
�@���Ȃ̉Ƃ͌[���Y�̕��e�̑�܂ŌS�����߂Ă����ƕ��ŁA���̂�����ɂ����ẮA���Ă̋v���ƂɈ������Ƃ�Ȃ��f���Ƃł��������B���ȉƂɂ͕��g�Ȃ鉺�j�ƁA�^�~�Ƃ����N�z�̏����������B���̍L��ȕ~�n�ɂ́A�ʂ�ɖʂ�����@�̌����Ƃ悭�����̍s���͂������������ʼn��܂�����s�ɁA�]�ˊ��Ɍ��Ă�ꂽ�Ƃ����ꉮ��������̓y�������R�ƌ����Ȃ��ł����B
�@�v���̔��Â����~�ɔ�ׂĐl�̏o����������A�b���a���ɖK�ꂽ����ɂ́A�����͕ʐ��E�Ǝv����قNJ��C�ɖ����Ă����B�ꉮ�̏�����������o��������Ɖb����݂āA�ljƈ炿�̒q���q�͂�����Ƌ�������������B
�u�܂��A���コ��A����ȂƂ��납�炨���₵�āB���ււ܂���Ă�����₷�ȁA�v���̂ڂ�����������炨���ꂵ���肵����A���̂킽���������܂��v
�@���s�ɐ��܂�炿�ł��ł����q���q�́A���̂�������a��ɐ��܂邱�Ƃ��Ȃ��A�ljƂ̍ȏ��炵�������Ƃ肵���������ŁA����Ɍ��ւɂ܂��悤�Ɍ������B
�u�����ȂɂԂ�R�ƈ炿�ł����̂ŁA�s�V���^���悤������Ɓc�c�v
�u��������͂�̂�A���Ȃ��������̂��^�����s�V������܂������ȁv
�@���߂ĕ\���ււƂ܂�����b��Ɩ�����A�q���q�͉����}������Ă��ꂽ�B�n���N�₩�Ɋ����̏����ꂽ�����̉A������`���������̗��q���A�q���q�͎菵�����ČĂъ��B
�u�v���̂ڂ�A�������璋�Ԃ̂��������a���肷�邵�A���ǂ����ėV��ł����悵�v
�@��e�̌��t�ɃR�N�������������q�́A�ْ������ʎ����Ŗ���̒����̑�������������Ƃ��܂܂̉b��̂��ւ����ƕ��݊���������ׂ̂��B
�u�����ŁA�������ւ����ėV�ڂ��v
�@�˘f����Ŗ�������グ��b��ɁA�q���q���b��������B
�u�ڂ��A�����͂Ȃɂ��C���˂��邱�Ƃ��炵�܂ւ�ŁA�������オ��悵�v
�@���̌��t�������Ĕ��ޖ���ɑ�����āA�b��͂���ƒ����̑����𗣂����B�u���ƂȂ��イ�ɁA����̂�Łv����͒E�������b��̌C�𑵂��A�U��Ԃ�Ȃ��痽�q�Ɏ���Ђ���Ă����䂪�q�ɂނ����Đ����������B
�u����������l�̊�F���C�ɂ���͂��ĉ��z�ɁA���T���܂͂��܂��ɋ��m�̉ƕ����d�āA�����ɂ��Č������������Ǝ�l����f���Ă���܂��v
�u����Y���S���Ȃ��Ă���Ƃ������́A�w�߂ċC��ɂȂ��낤�Ƃ���Ă���͕̂�����̂ł����c�c�v
�u���コ��A���Ȃ����̎Ⴓ�ŁA���ꂩ�炸���Ƌv���̂��Ƃ�w�����Ă���������H�v
�u�����A�����c�c�v
�u����A�]�v�Ȃ��Ƃ������Ă����Ċ��E�ǂ����B�ڂ��̂��Ƃ͂����Ƃ��a���肵�܂���������S���Ċw�Z�ւ����Ƃ���₷�v
�@�ԓ��ɂ܂荢�f�������̕\��ɋC�Â����q���q�́A�Q�ĂĘb�����点���B
�u�����y���̂ł�����l�Ɏ����Ă���܂��̂�B�������̂��ƋC�ɂ���Ƃ��Ă�����₷�ȁv
�@����̎������C�ɂ������q���q�́A�ʂ�ɖʂ�����܂ő����ďo�āA�b��̂��Ƃ𗊂ݓ������������ɂӂ����јl�т��B
�@���Ȃ̉Ƃ���w�Z�܂ł͏��̑��ŕ����Ă��\�ܕ����X���B���ȉƂ����肪���ɁA���ւ̑厞�v�̎w���Ă��������O�\���ɕ����ׂċ}�����ŕ�������̋���ɁA�q���q�̉��C�Ȃ����t���b�̗l�ɒ���ł����B
�@���オ��p�����Ƃ��ċ߂ɏo�Ă���ブ�����o���Ă����B���̊Ԃ̏��a�\�Z�N�O���ɂ́A�����q�퍂�����w�Z�͍����w�Z�Ɖ��̂���Ă����B
�@�l���̐V�w�����ނ����āA����͍�N����̎����オ��̓�N���̒S�C�ƂȂ��Ă������A����ł͍����Ȃ𑲋Ƃ�����̍_��A���̏t����R�A���T���w�̉w���Ƃ��ċߎn�߂Ă����B
�u��N�o������~���H�@��́A�@�֏��茩�K���������鐄�E��������Ă��ƁA�w�����猾��ꂽ���v
�@�n�߂ċ������������ɁA���̉b��̂��߂ɊG�{�Ɗʓ���h���b�v���A�킴�킴����̂���w�Z�܂œ͂��ɗ����_��́A����Ɋ��������ɕ������B
�u�悩�����Ȃ��A�_��@�֎m�ɂȂ�����A�ŏ��ɏ斱����D�Ԃɂ��ꂿ�����悹�Ă���v
�u��i�������s���}�s�A��Ԕԍ��R���s�w�ŋ@�֎ԕt���ւ��A���s�[�����Ԍ����@�֎Ԃ͔~���H�@�揊�������^�b�T�T�[�Q�O���斱�@�֎m�䌴�_��A�o���i�s�A�|�[�v
�@�_��͋@�֎Ԃ̋D�J�ق������^�������āA���ǂ��Ă݂����B
�@�_�����Ă��������̎l����\�����̂��ƁA���̓��̎��Ƃ͌ߑO���ŏI������B����̐��k�����Z�������Ƃ��A����͋����Ɏc���Đ��l�̎��������́A�ߕ��̂��낢��{�^���̂�����Ȃǂ����Ă���Ă����B�_��ƂɖZ�����e�����ɑ����Ďq�������̐g�̉��ɋC��z���Ă��̂��A��w�N�������t�ɂƂ��Ă͂������Ȃ����ł������B
�@�₪�ċ��c���Ă������k�������A���čs���ƁA����͐E�����ւނ������B���̂Ƃ��됰�V�����Ŏ��x���Ⴍ�A�Z�ɂ���E�����̂���{�قւ̓n��L�����������̖j�ł镗���u�₩���B�w�Z�̂܂��𗬂��c����̓S����n��D�Ԃ̋D�J�������A������Ȃ��ԉ��т����ĕ�������B�Ȃ�ƂȂ��e�C�����ɂȂ肩�����Ƃ��A���������獕�삪�����B�y�����������Ēʂ肷���悤�������ɁA�����~�߂����삪�����������B
�u���コ��A���̂������̘b�A�悤�l���Ă���͂�܂��������ȁv
�u�͂��c�c����͋����搶�̂��ӂ������Ɓc�c�v
�u����܂����ȁA�������̐^�ӂ��킩���Ă�����ĂȂ��悤�ł��ȁB���͖{�C�ŋ�S�N�̂������A�ȂƑ������v���Ƃ��A�����Ő�₵�Ă͂�����Ǝv���Ă���̂ł���v
�@�����Ȗ���́A�w��������j�̍���Ɍ��������邾���ł��Ј����������Ă��܂��B
�@�v���Ύl���̐V�w�����͂��܂�����T�Ԃ܂��̂��ƁA�o�����Ă��������Ȃ̋��t�̊�����a�c�w�O�̗����ł������B���삩�������Q���𐿂�ꂽ���A�c���b��������Ė�Ԃ̉��Ȃɏo�����ȂǁA���T�̗��������꓾������̂ł͂Ȃ������B
�@�ƂɋC���˂��ĕԎ����a�������݂�ƁA����͂킴�킴���̓��̂����ɋv���Ƃ܂ł���Ă����B�������āA�{���Ȃ�S�Z���k�ɂ��b�����Y�̕�Q�͖����̈���ł���ɂ�������炸�A���ʂɋ㌎�̖����ɂ����Q�肷�邱�ƂT�ɐ\���o���B
�u���܂������N�̐��_���q�������Ɋw���˂Ȃ��B����ɂ͋c��m�b�����Y�@�r���܂̂��̋Ƃ�m�邱�Ƃ���n�܂�܂��v
�@����͔��T���܂��ɔM���ۂ����u���͂Ȃ��玄�͋v���Ƃ̍ċ��̂��߂ɂ����o��ł���܂��v�Ō�ɂ͂��������Đ[�X�Ɠ����������B����̔M�قɋC���悭�������T�́A���삪�����ċ����𐿂�������̊�����o�Ȃ��ӊO�Ȃقǂ�������Ɨ��������B
�@�����ɎQ������������ł́A����͓������t��ɂ�錃��̈��A���Ђƒʂ肷�����������v����Ē����������B�x���Ȃ��Ă͏��Ȉ�@�ɗa���Ă���b�ꂪ�����肾�����肵�āA����ɖ��f�������Ă͂ƋC���������̂��B�Ƃ��낪�����̌��ւ��o�ĕ����n�߂�����̂��Ƃ����삪�ǂ��ė����̂��B��������ɁA����͖铹�͈Â����瑗���Ă����ƌ����B�铹�Ƃ����Ă��A�w�O�ʂŖ��Ƃ������Ă���̂Ŗ���͎��ނ���������͎�荇�킸�Ɍ�����ׂĕ����o�����B
�u������ς��ȁA�߂Ǝq��āA����ɉƂɂ��ǂ�Ό��i�Ȃ��ƂɎd���Ȃ���Ȃ��v
�u������A�����̉^���Ǝv���Ă��܂�����v
�u�ǂ��ł��A���̉^�������̖l�ɗa���Ă݂Ắv
�@�����~�߂����삪�A�����Ȃ����̗����Ɏ����������̂������ށB
�u�܂��A����k������c�c�v
�@������������L����������Ċ�����ނ��Ȃ���A����͂���������̂�����Ƃ������B
�u��k�ł͂Ȃ��A�s�т��̍���A�̂����Ďl�\��̂��܂Ɏ���܂œƐg��ʂ��Ă܂��������A��Ƃ̐g�ł��Ȃ��ɂ��v���Ƃ���g�Ŏx���悤�Ƃ��Ă��邠�Ȃ��ɋ���������܂����B���Ȃ������悯��A�l�͋v���Ƃ̖��{�q�ɂȂ��Ă������Ǝv���Ă��܂���v
�@�܂����s����̎G�݉�����l�e������A�Q�Ăč��삪���ꂽ�̂��K���ɖ���͕K���ŋ삯���B�₪�ď��Ȉ�@�̊ۂ��哔���݂����Ƃ��A�ق��Ƃ����v���ŐU��Ԃ�ƁA���������ɍ���̉e�͂Ȃ������B
�@����͂��̎��̂��Ƃ������Ă���̂��B�܂��������搶���炠�̂悤�Ȃ��Ƃ��c�c�A����͍��f������肾�����B
�u�����A�v���搶�����ɂ����Ăł������v
�@���v���ɒ��ޖ��オ�����Ċ���ނ���ƁA�w�Z�ɏZ�ݍ���ł��鏉�V�̗p�������Q�Ă��l�q�ŁA����̉Ԓd�̂��������삯����ł����B
�u�搶�A�w�O���Ύ��ǂ��B���ܒm�点���͂������Ƃ���ł����A���X�X�ɔR���Ђ낪������A���Ȉ�@����Ȃ��B�v���搶�A�����ɂڂ����}���ɂ�����������낵�������v
�@�p�����̘b���ς܂Ȃ������ɁA����͍Z��ɂނ����đ���o���Ă����B
�u�w�Z�̎��]�Ԃɏ���Ă����Ȃ͂��v
�@���Ƃ���p���������������Ă���邪�A����͎��]�Ԃɂ͏��Ȃ������B�Z����o���Ƃ���ցA�܂�悭�m�点�����ɏo�����鈢�؏W���̌x�h�c������Ă����B���Ȉ�@�Ɏq����a���Ă��邱�Ƃ�������ƁA�n���Ђ��|���v�Ԃɏ悹�ĖႤ���Ƃ��ł����B
�@�Ќ���߂��Ń|���v�Ԃ��~�낳�ꂽ����́A������ɗ������߂鉌�ɊP�����݂Ȃ���A�l�X�ł������������ʂ�����Ȉ�@��ڎw���đ������B���Ί����̖W���ɂȂ�ʂ悤�ɁA�ʂ��ʍs�~�߂ɂ��鏄���ɂ́u���̂Ȃ��Ɏq��������v�Ƌ���ŕ����̃��[�v������������K���ŋ삯���B
�@���䖲���ŏ��ȉƂ̋߂��܂ł���ƁA�ꉮ�̂�����̋�ɉΒ������̂��݂����B�T�C�����̉��Ɣ������ł��炳���Ȃ��A���ꂼ��̒n��̈�@���Z�������l���̌x�h�c�̒j�������A�|���v�ԂƂƂ��ɖ���̘e��ǂ������Ă����B
�u�b����A�b����v
�@���R�Ƃ������͋C�̂Ȃ��A����͉䂪�q�̖������ё������B
�@���Ȉ�@�̑O������ɂ����|���v�Ԃ��A�g���鉊�ɖ���̋߂��܂Ō�ނ��Ă����B�R����������Ȉ�@�̕��삯�������A�x�h�c���̈�l���C�t���Đ��~�����B
�u���̉ƂɎq���������ł��B�����Ă��������v
�@�Ȃ̐g�̊댯�����䂪�q�̈��ۂ��C�����A�삯�o�����Ƃ��������x�h�c�����w�ォ������Ƃ߂�B�����Ăт�����x�h�c�̃��K�z���̋��тƉE����������l�X�̂Ȃ��A����͕��S���ē��[�ɂ������ޒq���q�Ǝ���Ȃ����q����Ƀ^�~�������삯������B
�u�����܂��A�����̉b��́A�b��͂ǂ��ɂ����ł��v
�u���ꂪ�A�ꏏ�ɓ������̂ł����A���̊Ԃɂ��������āA���ܕ��g��T���ɂ���Ă��܂��̂�v
�@��ЂƂ������Đk���Ă���q���q�́A����������̂�����Ƃ������B������^�~�������Ęb�������p�����B
�u�ڂ��͂ǂ��₩�̒j�̐l�ɔw�����āA���������������₵����v
�u�j�̐l�āA�ǂȂ��ł��v
�u�����A�C�����]���Ă܂����������ɁA��͂悤�o���ĂȂ��̂₯�ǁA����܂茩�������ǂ�����v
�@�^�~�̌����ɂ́A�������Ȉ�@�܂Ŕ����Ă���Ȃ����悤�Ƃ��ċC�t���Ƃڂ��̎p���݂��Ȃ��A�Q�ĂĂӂƐ���݂�Ɠ����o�����ȉƂ̐l�����̈ꑫ����A���m��ʒj���b���w�����ċ삯�o���Ă����Ƃ����B�����ɕ��g�����̂��Ƃ�ǂ������A�������ē����܂ǂ��l�X�̂����������蔲���Ă����j�̑��͑����A�r���Ō��������Ƃ����B
�@�q���q�����ƕʂꂽ����͉䂪�q�̎p�����߁A�l�X�̂�������N�ނȂ��q�˂ĕ��������A�N�������������̔���̂�����t�Ŏ�荇���Ă����҂����Ȃ��B�C���t���Ɖw�߂��̐��H�[�܂ł��Ă����B�U��Ԃ�Ɖw����ܕS���[�g���قǗ��ꂽ���X�X�́A�������艊�ɕ�܂�Ă����B����ɂ́A�������珤�X�X�����ނ悤�ɔ���R���ɂ���щɂ�鉊���݂����B�ΐ��ɑj�܂�ď��Ί����͍�����ɂ߂Ă��āA�|���v�Ԃ̐����ƂȂ鏤�X�X�ɉ����ė����c����̐��ӂɂ��ߊ��Ȃ��炵���B���H�t�߂ɂ́A�Ȃ����ׂ��Ȃ�����鐔�\�l���̌x�h�c���炪�A�R�������鉊�ߗ��������Ă����B
�@���̎��������u�搶�v�ƌĂԐ��ɐU������A����̒S�C�̋ʈ�a�q�Ƃ����q���Ԃ���悤�ɂ����݂��Ă����B
�u�搶���E�`�̉Ƃ��R���Ƃ���v
�@��������Ŗ�������グ��q�̊�͕|�낵���قǂɈ�����A�ڂ̑O�̋��|���瓦��悤�Ƃ��邩�ɁA�Ȃ�������ɂ����݂��Ă���B�r�����ł��邱�̎q�̉Ƃ͏��Ȉ�@�̐^�������ɂ���A���łɔR�������鉊�̂Ȃ��ɂ����Č��ɂ߂����Ȃ��B����͂����Ă�錾�t���Ȃ��A���Ⴊ�ݍ���ŕ������߂Ă�邵���Ȃ������B
�u�搶�A�ڂ��Ɖ�Ȃ��������A���Ȉ�@�݂͂ȏĂ��������ƁA����������r���Ōx�h�c�̐l���b���Ƃ������ǁv
�@����܂ŋC�t���Ȃ��������A�b���������Ċ��������Θa�q�̕�e���B�Ȃ��Ε��S�����\��Ȃ�����A���オ���Ȉ�@�ɑ����Ă���b��̂��Ƃ��C�����Ă���Ă���B���Ԃ��U��Ɓu�w�O�ɂ��傤����Ȑl�����Ă������A���ɂ����Ă݂���v�ƌ����B
�u���ꂳ��Ɛ�ɗ���Ƃ�v����͘a�q�Ɍ����܂߂āA���̐e�q�ƕʂꂽ�B
�@�w�O�܂ł���ƁA�Ă��o���ꂽ�l�X�ł������Ԃ��Ă����B�w�O�͏�荇�������Ԃ������ƕ����]���ł���قǂ̍L�ꂾ���A����̎҂����C�~��݂ЂƂƂ����L�l�Œn�ʂɍ��荞��ł����B���̂Ȃ��𐔐l�̏������A�����ɐg���̍s���s���҂̗L����q�˂ĉ���Ă���B����͉䂪�q�̏��������߂āA�K���Ől�X�̂�������D���ĕ����q�˂����N����������ɐU����肾�����B�r���ɂ��ꂩ�����Ƃ��������B�u�o�����I�v���̕��Ɋ���ނ���ƍ_��w�����������ċ삯�Ă���B�_��͋Ζ������ŋA�肩���Ă�����A�S���d�b�œa�c����Ύ���ƘA�����������B�Q�Ăĉ����܂ł���ƋD�Ԃ̉^�s�͂����őł����Ă��āA���������ƂɂȂ����Ǝv���Ă���Ƃ���A���傤�Ǖې�������a�c�w�֗l�q�����ɂ����Ƃ��낾�����̂ŁA���̃g���b�R�ɕ֏悵�Ă����ƁA�����ɂ���Ă������R����C�ɒ������B
�u�_��A�ǂȂ����傤�A�b�ꂪ�������̂�v
�@����̌��t�ɁA�_��̊炩�猌�̋C���������B�u�o�����A�����v�������͂₢���A�Ќ���̕��p��ڎw���ċ삯�o��������܂��_��̌��ǂ����B
�@�ӂ����щЌ���܂ł���ƏĂ��������Ɖ��̎c�[������A�����h���L���@�E�������B�܂����������ĔR���������Ă���Ɖ�������B����߂��点�����[�v������������A�Ȃ��֓��낤�Ƃ����r�[�ɏ����ɐ��~���ꂽ�B���ǂ���T���Ă���Ɩ�������Ă���Ƃ��Ēʂ��Ă��ꂻ�����Ȃ��A�ƂĂ����Ȉ�@�̂�����ɂ����͖̂����Ǝv�����B
�@�r���ɂ�����l�̎��ɁA�߂��̒j�����̘b���������������B
�u���̔w�ɗc���������݂��đ����Ƃ��Ȃ�āA����Ȏ�������̂��̂��v
�u���猢��Ȃ��낤�A���̌����Ȕ��͌ς���v
�u�b�ɕ����A�����R�̔��S�ۂɈႢ�Ȃ��̂��v
�@����͎v�킸�_��̊������ƁA�_����܂����������B
�u���̂��A���̘b�͂ق�܂Ɍ���͂������Ƃł���납�v
�@�ߊ���Ė₢������_��ɒj��͈�u���b�Ȋ���������A�Ȃ��̈�l���ڌ������Ƃ��̗l�q�ӂ��Ɍ��n�߂��B
�u�̐����́A���ɂ������Č������Ȃ����Ŏ肪������B��U�����܂łЂ��������Ă����Ƃ�����A�c����w���ɏ悹�������傫�Ȍς����H�̌�����𑖂��Ă�̂����������̑��̑����̂Ȃ�́A���Ƃ�܂ɐ��H���痣��ēc���̌l�`���ɎR�����삯�����Ă����A�����Ƃ����܂ɎG�ؗт̂Ȃ��֖z�荞�݂��������v
�@�j�̘b���I���ʂ����ɁA����͐��H�ɉ����ĕ����o���Ă����B
�u�o�����A���܂�����ǂ��Ă�������v
�@�_��̐��ɖ���͗����~�܂�B�ς��z�苎�����Ƃ����G�ؗт͖���F������ʂɂ͂т���A���i�͓���l�����Ȃ��Ƃ��낾�B����ƂĐl�蓻�ւނ����ɂ́A�R�������鏤�X�X�̂Ȃ��������˂Ȃ炸�A���܂͐��H�����Ƀg���l�������Ƃ���̓�����A�n�ԓ��ɏo��̂����ؒJ�ւ͋ߓ����B�_��͂����̂Ƃ�����l���Ă���̂��B�����������؏W���̌x�h�c���ɁA�b��̍s���s����`���đ{���𗊂�ł���Ƃ���Ɋw�Z�̗p����������Ă����B
�u�v���搶�A�ڂ�����Ăǂ������v
�@���]�Ԃ��~�肽�p�����́A������݂�Ƒ吺�ŋ��B
�@�p�����̘b�ł́A���l�̈�l�����ؐ_�Ђ̋����ɂ����藧�吙�̍��{�ŁA�����Ă���b����������Ƃ̂��Ƃ������B
�@�m�点�ŋ삯���ĉ䂪�q���Ђ��ƕ������߂�����́A�b��̈ߕ��ɕt�����Ă��鐔�{�̔����b�тɋC�Â����B������w����������̎w��������_��́u�����{�E�Y�������ɂ����c�c�v�ƙꂢ�Đ�債���B
�u�M���c�c�������Ɂv�䂪�q���~���Ă��ꂽ�̂̓M���ɊԈႢ�Ȃ��A�嗱�̗܂�����̖ڂ��炠�ӂ�o���B
�@�����̏��a�\�Z�N�l����\�����̐V���́A�R�A���a�c�w�O�t�߂̉Ђ��X�I�ɕ��B����ɂ��ƏĎ��Ɖ���S��\�Z���A�Ȃ�тɔ�щɂ��R�т̉Ќ\�����Ƃ�����ł������B
�@����ɋL���͉Ђ̌����ɂӂ�A�����̒�������a�c�w���\�O�\�����ɔ��Ԃ������s�s���̗�Ԃ��A���W���閯�Ƃ̗����ʉ߂��Ă��������̏\����ɁA���H����قNj߂��X�Ǖt�߂���̎肪���������Ƃ������ƂŁA�����͏��C�@�֎Ԃ̔����ɂ������Z���ƕ��B
�@���������w�Z�ɒʂ����k�̉Ƃ��A�������Ă��o����Ă����B����̎�������w���ł��A�a�q���܂߂ĎO�l�̎����̉Ƃ���Ђ��Ă����B�Ă��o���ꂽ�l�X�ɂ͈ꎞ�I�Ȕ��ꏊ�Ƃ��āA�a�c�w�O�Ɍ������Ԋ��B���ق�������Ă����B������͕t�߂̍z�R����Y�o����A�}���K���z�̒����l�����œ��키���B���ق��\�������苏���Ԃ��̈�т́A�h�����ĉ��Ă��܂ʂ���Ă����B����͑��̋��������ƂƂ��ɁA��Ђ������k�����̗l�q���݂ɂ܂�����B
�@�ē����ꂽ�����̉����J����ƁA����̂��ƔR�������錻����A�䂪�q��T�������Œ��ɏo������a�q�̕�e���A������݂Đ��������Ă����B
�u��قNj����搶�����݂��ɂȂ�A�v���搶�̂ڂ�����ł���ꂽ�Ƃ��A�ق�܂ɗǂ������ǂ��Ȃ��v
�@����ĂČ������̌��t���q�ׂ悤�Ƃ������ɁA��e�͐�ɉb�ꂪ�����ł��������Ƃ����ł��ꂽ�B
�u�Ȃ�ł��̕��̂Ȃ����A�����Ȏq���w���ɂ����݂����^�������ς������čs���̂������l������͂��āA����͈����R�̔��S�ۂɈႢ�Ȃ��A�����Ă��炢�\�ł���A�ق�܂ɂ���Ȃ��ƁA����܂��̂��납�v
�u�����c�c�A���A���ꂩ���Ђ������k�ɂ����ẮA�w�Z�̕��ł��A�ł������̕X�͂͂���ƁA�Z���搶�̂����t�ł����v
�@�M���̂��Ƃ����܂�b�������Ȃ��̂ƁA�����Ă������{�ʂ̗d���b�̎�ɂȂ邾�����Ǝv���A����͌������̌��t���q�ׂ�Ƒ��X�ɁA�܂����肽�����ȕ�e�̂��Ƃ��������B
�@�ʂ̗��قɂ��鑼�̓�l�̐��k��K�ˁA�������Ɩ���͋A�r�ɂ����B�w�O�܂ł���ƋD�Ԃ���~��Ă����_��Ɖ�����B��e����̌��ÂĂ�`���ɁA�r�����Ԃ����̂��Ƃ����B�Ƃ��낪���̍_��̂��Ƃ���A��c�������Ă���ł͂Ȃ����A�E��Ƀg�����N����������c�́A������݂�ƕЎ��g���Ĕ��B
�u�����́A�����������Ƃ�܂��A���̂��т͑�ςł����˂��A�����Ԃ�Ƌ����ꂽ���Ƃł��傤�v
�u�܂��A��c����A�܂��ǂ��Ȃ��ꂽ�̂ł��v
�@����������_��̕����A��l�̊������ׂȂ���s�R������Ă���B
�u��̍_��ł��A������͕��ߊC�R�H���ɂ��߂̖�c�����v
�@����͋v���U��ɉ������c�Ɍ˘f���Ȃ���A�ӂ�����݂��ɏЉ���B��c�͈�������o���������Ƃ��ŁA�V���̕ő��m��A�r�ɖ���̗l�q��m�肽���č~�肽�����ƌ������B
�u���ꂿ��ȁA�b���a�����Ă����Ƃ����̂��Ȃ�����A�߂���ς�납��A�����ŗa�����Ă���Ă������āv
�@�����Ȃ���_���e�̌��ÂĂ�`����Ɓu�������A���q�����a���ċ߂ɏo���Ă��̂��A����Ⴀ��ς��ȁv�ƕ���ŕ�����c�����S�������ɑ��Ƃ��������B
�u�v���̂��`�ꂳ��́A���܂��ɕ��Ƃ̊i�����d�Đ����Ă͂鉻�݂����Ȑl�₩��A�ǂ����q��͖����ł���v
�u�_����B���j�̕Ȃɉ��ł����肷����v
�@����Ɍy�����߂��Ď��␂߂�_��ɁA��c�̓A�n�n�Ə����B
�@�w�Z�֖߂�Ȃ���Ȃ�Ȃ�����́A���S�ɏĂ����������X�X�̂Ƃ�������ɉ˂���a�c���̂Ƃ���ŕʂ�邱�ƂɂȂ����B��l�͂��ꂩ��Ă��Ղ����ɍs���炵���B�ʂ�ۂɖ�c�͖�����Ăю~�߁A�H��Ńg�����N���J����ƁA�Ȃ�����r㻂����o���A���`�ꂳ�܂ɂƍ����o�����B
�u���̂���A���コ��Ɂc�c�v
�@����ׂ̂ėr㻂����������ɁA��c�͉����ʂ̎���݂������o���B
�u�܂��A���ɂ܂Łc�c�v
�u���C�ɏ������ǂ����A�킩��܂��c�c�v
�@�������݂��J����ƁA���N���[���������B�����������̏������@����肽�w�w�l��y���x�̍L���ɂ������ŋ߂ɔ������ꂽ����̐V���i�ŁA����ȓc�ɂł͂ƂĂ���ɓ���Ȃ��i�����B
�u���������ǎ��ɂܑ͖̂Ȃ���A����ȍ����Ȃ��́v
�u����ȑ�U���Ɍ���Ȃ��ł��������B�ق�̈��A����̂���ł�����v
�@���������ċ��ݍ��݁A�g�����N�̊W��߂Ă����c�̎���Ƃ܂ł��Ԃ��Ȃ��Ă���̂����āA���̐l�͖{���ɐ��^�ʖڂȂЂƂȂ�A�Ɩ���͎v�����B
�u�o�����A���ϕi�Ȃ������Ƃ��Ȃ��̂��B��������Ɩ�낽�炦���̂Ɂv
�@�T�œ�l�̂������݂Ă����_������͂��ށB�����A���̎q�́A�ƍ_����ɂ�ޖ���Ɂu�����ł���A�p��~�����Ȃ��ł��������v�����̂��g�����N����ɂ�������c�����B����͋��k������c�ɗ�������A����݂���̂Ȃ��Ɏ��߂��B
�@��ɂ����č_������킽��n�߂�Ɓu����ł́v�ƌy����߂��Ė�c�����Ɍ������ĕ����o�����B���̂Ȃ��قǂ܂ł����A�����~�܂��Đ�ʂ��w���Ė�c�ɉ�����b��������_��A���Ȃ��悤�ɋ��̗�������g�����o���Đ��ʂ�`�����݂ޖ�c�̉���B���m��ʓ��m�ł��A�j�͂����ɂ�������������̂ȂB��l�Ƃ��܂�ŋ��m�̊ԕ��݂����ƁA�Ȃ��ΑA�ގv���Œ��߂Ă���ƁA��c���U��Ԃ��Ė���Ɏ��U�����B�Q�ĂĖ���͂�����x���J�Ȃ����V��Ԃ��A��l������n���ďĂ������������̂������Ɏp���B���܂Ō��������B
�@�a�c�w�O�̉Ђ������Ă���A��N�߂����o���Ă����B���̉Ђ̏o�Ό����͎R�A�{���̐��H�ƉΌ��̌����̋������킸���\��E�܇b�Ƃ����߂����������Ƃ���A��̌��ŗ�Ԃ̔����ɂ����͋^�����Ȃ������Ƃ���A����S���Ȃ��瑽�z�̌���������Ў҂Ɏx����ꂽ�B���̂��߂ɕ����͂߂��܂����A���ȉƂɂ����Ă��Ă��������Ɖ����@�̍Č����قڊ������Ă����B���̈���ŋv���Ƃ����Ȃ̑��։^�э��܂ꂽ�����̌Õ����ȂǍ����̕i�X���A��u�ɂ��ĊD���ɋA���Ă��܂����̂�����܂ꂽ�B
�@����͉Ђ̂��ƁA�������̎��Ƃ̕���̂��Ƃɉb���a���Ă������A�ӂ����щ䂪�q�����Ȉ�@�ɗa���邱�Ƃ͍l���Ă��Ȃ������B���Ƃɖ߂�������́A�����̂������b���a�����Ă����悤�ɗ��e�̂܂��ō��肵���B����ɂ���Ώ����ł�����A�e�̌��ň�Ă��Ȃ�����s���ɂ��������̂��낤�A�������킸�Ɉ����Ă��ꂽ�B
�@���̐܂�ɕ��e����A�O�Y���q���͂̔ɋ@�֕��Ƃ��Ĕz���ɂȂ��Ă��邱�Ƃ����ꂽ�B���̎q���q���͂̏���ɁA�Ɣ�䍂��Ă݂����A�q���͂��������Ƃ��Ȃ�����ɂ͑z�������Ȃ������B
�u���߂�₷�v
�@�x���Œ�̑��Ђ������Ă�������́A�����Ȃ萺���������Ċ���������B�ɂ��₩�ȏΊ�̍��삪�A����������Ă�����ւ���Ă���B����͍ŋ߂ɂȂ��āA�����v���Ƃ�K���悤�ɂȂ��Ă����B�i�ʂɏ��p������킯�ł��Ȃ��A�������T�̋@�����f���ɂ���ɂ������A����͓��S�ł͍��삪�K��Ă��邱�Ƃ����������B
�u���コ��A�����ł��v
�@����͉E��Ɏ���������݂��A����ɂ������ē��ӂ��Ɍ������B�����Е��̎�ɂ͍�����V�����ɂ���̕c�������Ă��āA�����オ�荘���̂�������ɋ����̎���݂���������Ɓu���`�ꂳ��͂����邩�v�Ɩ₢�����Ȃ���ꉮ�Ɍ��������B
�u����ɂ��́A����ł������܂��B���̂��т͌I�̕c�����������܂����v
�@���삪�ꉮ�̉����ɂނ����Đ���������ƁA���~�̏�q�������Ĕ��T������o�����B
�u���܂���I�̕c�āA�܂�����ǂ����v
�u����͑哌���푈�����I�����ĉ��N����낵���̂ŁA�����~�̒�ɂ��A�����悤���Ɓc�c�v
�@�O�N�̕��Ɏn�܂����A�V���Ȑ�̏������F�O�����c�ł��邱�Ƃ��A����͂����Ƃ��炵�����������B
�u����Ȃ�A��������̉�������ɐA���Ă�����₷�ȁv
�@���������ĉ������猩���낵�����T�́A����ǂ͖���̎�����݂ɖڂ����u��ɉ��������Ă���̂��v�Ɩ₢���������B
�u���A����A���܂��܋�������ɓ���܂����̂ł��������܂����v
�@���オ�����J���O�ɍ��삪�������B
�u����͂܂��M�d�Ȃ��̂��A�����搶�ɂ͂����Ȃ���A�����b�ɂȂ��ėL��������܂��v
�@���t�̒��d���Ƃ͂���͂�ɁA���T�̍��������ڂ͗�߂Ă���B�v���Ƃ̉ƕ����炷��A�����Ƃ����ǂ�����Ȃlj��قǂ̎҂��Ƃ����v�������肪���T�̕\��炤���������B
�u�����A����ł͌I�̖�A���ɂ����܂��v
�@����͖����U������Č����Ɛ�ɗ����ĕ����o�����B�r�����̕��u�֊��A����m�����d���Ńc���n�V�ƃX�R�b�v�����������Ă���ƈ���ɓ��ɂނ������B����͎��Q���������ŁA�����Ă��Ȃǂ����点�[�т�H�ׂĂ�������Ȃ̂��낤�B����͂��Ƃɂ��ĕ����Ȃ���A���̎����v���������ŋC���d�������B
�@����ɓ��܂ł���ƍ���͔��T���猾��ꂽ�ʂ�ɁA�����t���ƂȂ��Ă��邵������̐^������������̒n�ʂɌL���������낵���B�����֗Ƃ̖F�����������Ɨl�q���M���ɂ���Ă����B
�u�₠�F������A����͑哌���푈�����I�ł��v
�@�߂Â��Ă����F����ڕq���݂č���́A���T�Ɍ������̂Ƃ��Ȃ����Ƃ��������ɌJ��Ԃ��Č������B
�u�ڂ����傫���Ȃ��ďo�������₵����A��n�Ŏ蕿�����Ăēd���ʐ^���V���ɍڂ�܂��킢�A��������ቜ���܂̂Ƃ���ɂ��V���L�҂����āA�E�m�̕����A�Ȃ�ĐV�����������܂����v
�@�F���͑傫�Ȑ��Ō����I���Ɛ����ɏ��u�A�z�Ȃ��Ƃ������v������܂����ď��������Ă��B����͂���ȓ�l�̉�b���܂��Ɂu���̌I�̎������邱��ɂ͓��{�����������߂āA�푈�͏I����Ă��܂���v�Ƌ������B
�@���̔N�̏H���ɎO�Y�펀�̌��͂������B�m�点���Ď��Ƃ֖߂�������́A�⍜�̓��������̔��Ƒ���{�鍑�C�R�ƋL���ꂽ�����X�������O�Y�̈�e���܂��ɓ˂��������܂܂ŋÎ������B���a�\���N�Z���Z���펀�ꏊ�͓쑾���m�C��Ƃ��邾���������B���N��\�O�B�Y�t���ꂽ�����t����ǂ�ł��A�T�ŚT��グ��_����ԉ��̒�O�̂悤�ɂ͕s�v�c�Ɨ܂��킩�Ȃ������B��̂̂Ȃ����V�͌����̂悤�Ɏv�����A�Z���̒����ɕ����т����߂��O�Y�����̐l�����������������ׂ���ŁA���܂ł����ւ���k�E�b�ƌ��ꂻ���ȋC�������B
�@�䂪�q�̉b��́A�ߏ��̎�w��������Ă���Ƃ��ŁA��e�͈⍜���҂��Ă���́A�����ƐQ���ʼn点���܂܂炵���B�����ɂ��Đ�������������Ɂu�O�Y������ł������v�ƂԂ₫�z�c�������グ�Ċ���B���Ă��܂����B����ɖK���ߗׂ̐l�X�̉��ɂ����肫��̕��e�́A������݂āu�߂������v�Ɛ��������Ă������̂́A��ꂫ�����l�q�������B������܂����e����`���������ŁA����q�̐ڑ҂ɒǂ�ꂽ�B
�@����̋q���r�₦�Ĉꑧ�������ɂ́A��ח��Ƃ��̗z�͎R�A�ɓ��蔖�ł��Y���Ă����B��e�̂Ƃ���ւ����Ċ���݂�̂��h���āA����͖��̍��Ɏg���Ă��������ւ���Ă����B
�@�S�̒��̉����������������v���ł���ƁA�ӂƕ����̋��ɂ�����~���ɖڂ��������B�Ƃ��o��܂ŎO�Y�������Ǝg���Ă������̂������B����͂ɂ�����ƁA���̏�ɒu���ꂽ�{���Ă������̏����{��������B��C�ʼn��ꂽ�\�����J��ƁA���ꂼ��̕ł̒[�ɉ��M�̏������݂����Ă���B���̎q�͖{�C�ŏ��������ɂȂ���肾�����̂�A�O�Y�̕M�Ղ�ڂłȂ���Ȃ���A�s�ӂɎO�Y�̎v���o����݂��������B
�@�n�R���䂦�ɁA�g���x�߂�ɂ��Ȃ�������e�ɑ���A����������Ȃ��̂ɁA�����������炢���ʓ|���݂�����ꂽ�O�Y�B���d�������������Ȃ���A���̋��Ŏ��̌o�̂��Y��ď�����ǂ݂ӂ���A�L��U��グ����e�ɒǂ��������Ĕ��̂Ȃ����܂���Ă����O�Y�B���s�ɏo�Ă���ƕK���ۑP�ɂ��A�߂�̋D�Ԓ��܂ł��{��Ɏg���Ă��܂��A�悭���w�Z�̊�h�ɂ܂ŋD�Ԓ��̖��S�ɂ���Ă����B���オ���O�g������ł́A�������肵��Ǝ��B������Ӗ���������Łu�ǂ������v�Ǝ���ƁA���␂߂Ă��܂舫���Ȃ��̎��̎O�Y�̊�B����炪����̏o�����̂悤�ɁA����̔]���ɕ����ԁB
�@���C�Ȃ������ɖڂ����ƁA�͎R����͂�����̒u���̖T�炩�甒���e�������Ƃ���������߂Ă���B����̖ڂ���A��x�ɗ܂����ӂ�o���B�M���c�c�A���e�����������̂��܂��̔߂��݂��A�p�����������ǎ��ɂ͂��܂ɂȂ��Ė{���ɂ킩������c�c�B�ЂƂ���E�̔Z���������O�Y�A�@�֕��Ƃ��ċ���ȍq���͂̊͒�ŐL�ѕ���̕E�ʂ̂܂���ł������ɈႢ�Ȃ��B��ɂ��������{�̕\�����A����̖j��`��������܂��G�炷�B�M���A���܂��͋����Ȃ��A���ɂ͂���Ȕ߂��݂͑ς����悤���Ȃ��A�S�̂Ȃ��Ō�肩������A�����e�͂�������݂߂Đg���났�����Ȃ������B
�@�O�Y�̑��V�����܂��āA����͍Q���������v�����~�ɖ߂��Ă����B����͏\���̎n�߂ɍs����A�^����̏����ɒǂ��Ă������炾�����B�^����͍����w�Z�̒P�ƍs���Ƃ��������A�����̘V��j�����o�̑����^����ł������B���������N�̉^����͗�N�ƈ���āA���k�����t�����ʂȎv�����������B
�@����Ƃ����̂��A�^����Ȃǂ̒��S�I�ȒS����ł���N�c���̖w�ǂ��o�����Ă����Ȃ��ŁA�c�����҂����̂�����ɗǎ��̃}���K���z�������邱�Ƃ���A����̍̌@��ɒ��p����Ă��������Ɏ�҂⓭������̒j�����̎p�͎���Ɍ������Ȃ��Ȃ��Ă����B
�@����ł͊������������w�Z�ɂ����Ă��A�Z���ɋ����̍���������ΎႢ�j�����t�����͏o�����Ă����A���l���鋳���͖�����p�������ӂ��߂Ă��ׂĂ������ŁA���͂�w�Z�Ƒ����Ƃ̍����^����́A���ꂪ�Ō�Ƃ����̂��N�����̎v���ł������̂��B
�@����ɂ͔�펞�ɉԂ�A����Ƃ͉����ƁA�Z���ɂ���Ԓd��Ő�����ăJ�{�`���Ȃǂ̖���͔|���邱�Ƃ����コ�������A���^���ꂪ���ɂ����Ƃ��킩��Ȃ������B
�@�ċx�ݑO�̐E����c�ɂ����鍕��̒�ĂŁA���N�̉^����畐���̋����̉��Z�������Ȃ����Ƃ����߂�ꂽ�̂��B����͂��̒�ĂɂЂǂ����������u����������Ȃ��Ă��A���łɏォ��̖��߂ʼn^������R�������̍V�g�̏�Ƃ���Ǝw��������v�Ƒ��̋������玨�ł����ꂽ�B
�@�^��������܂肠�ƂɍT�������̗[���A���オ�w�Z����߂��Ė��������Ȃ�A���ɗ����T�̈ٗl�Ȃ��ł����Ɏv�킸�ڂ������藧��␂B�Ȃ�ƌm�Ò��юp�̔��͓̂㓁���g���A���R�Ƃ��������������Ă���B
�u���`�ꂳ�܁A�܂����ł��́A���炢���X�������Ɓv
�u��������A�㓁�̎w���ɂ������ƂɂȂ����łȁB����Œ��������������Ă������m�Ò��������Ă݂��Ƃ���A���ɂ��I���Ă����悤�����v
�@���T�͍��̏��q�̌т̐����A�܂�ň��������Č����Ȃ��猾���B
�u�����̒��ǂ����Ȃ��A�����w�Z�̗p�������A�Z���搶�̐e���������ĖK�˂Ă����ł��炵���ł���v
�@�����ւЂ������Ɗ���o�����F�����A����ɔ��T�̂��ł����̎����b���������B
�u�Z���搶����c�c�v
�u�ւ��A�^����ŏ��q���k�̓㓁�̌P����������炵�����B����ő剜���܂ɋ����̎w���ɂ��Ă���Ƃ��̗v��������炵������v
�u�^����܂łɁA�����\�������Ȃ��̂Ɂc�c�v
�u�����ǂ��������A�Q�Ăē㓁�t�͂̎��i���������́A�剜���܂̂Ƃ���֗���ł����Ƃ������Ƃ炵������v
�u���`�ꂳ�܁A����ȋ}�Ȃ��Ƃ��������đ厖���܂��v
�u�������疈���A�l�͎Ԃ��}���ɂ������邢�����Ƃ�v
�@�F���̂͂Ȃ������Ă��A�܂����M���^�̕\��̖���ɁA���T�͂܂�ł��Ȃ������Ɍ������B
�@�����̂��ƁA�ꎞ�Ԗڂ̎��Ƃ��I���ĐE�����ɖ߂�������́A�����킹�������̍���ɁA���T�ɋ}�ȓ㓁�̎w�����˗��������₤�Ă݂��B
�u�����搶�A���ǂ��̂��`�ꂳ�܂ɁA�㓁�̎w���𗊂܂ꂽ�͖̂{���ł����v
�u�����A���q�̓㓁���������܂�����Ă����̂́A���͂̍����w�Z�ł͖{�Z�����ł��B���R�͓K�Ȏw���҂��݂���Ȃ��܂܁A�����܂ł����Ƃ������Ƃł��B�������^����ɒj�q�̏e���p�̏W�c�P��������̂ɁA���q�̓㓁���Ȃ��ł͊��D������B�����Ŕ��T���܂Ɉ˗��������Ƃ�������ł��v
�@����͂��������Ȃ���n�Ƃ̏����炳���ƁA�v���o�����悤�Ɂu�l�͎Ԃ𗊂�ł����˂v�ƌ����p�������̕��ւ����Ă��܂����B
�u����A���R�l����肩��A���ꂽ����v
�@��l�̉�b���Ă��������t�̂Ȃ��ł͈�ԔN���̋������A����̊���݂��əꂫ�Ȃ��狳�ȏ������e�ɕ����ďo�Ă������B
�@���̓��̌ߌ�̎��Ƃ̐܂�ł������B���k�̈�l�ɍ���̋��ȏ���ǂ܂��Ȃ���A����͊��̂�����������Ă��ĂӂƑ��O�̉^����ɖڂ����ƁA�ܔN���ȏ�̏��q���k���|����ɂ��Đ��Ă���B�m�×p�̓㓁���Ԃɍ���Ȃ��������߁A�}���e���ɉƂ����������Q�������Ƃ������Ƃ������B�d��ɂ͔��������Ɍm�Ò��p�̔��T���A��܂��߂ɓ㓁�̍�@���������Ă���̂��݂����B���k�̓ǂނ̂ɍ��킹�Ėڂŋ��ȏ��̎��ʂ�ǂ��Ă��Ă��A�����O�ɖڂ������Ă��܂��B�㓁�������鐶�k�����́A���炭���߂Ăł��낤�㓁�̌^�̐����ɁA���������Ɍ�����q������A�����Ȃ����ɃL�����L�����Ƃ���������A���������Ȃ��l�q�̎q������B
�@���̂������k���n�ʂɍ��点�āA���Z���n�܂����B�u�G�C�b�A�C���b�[�v�Ɣ��T�̍b�������тɋ߂��C�������������A����ƌ����������܂܈��R�Ƃ��Ă݂Ƃ�鐶�k�����A���̉��Ƃ���Ⴂ�Ȃ悤�Ȋ��m���ɁA����͎v�킸�N�X�b�Ə����B�r�[�ɂ܂�肩�琶�k�����̏��������������B�C���t���Ă݂�Ɩ��㎩�g�����̊Ԃɂ����ӂɊ���Ă��āA���k�������S�������ɋߊ��^����̌��i�߂Ă���̂��B�Q�ĂĐ��k�����ɐȂɖ߂�悤�ɐ��������Ă���Ƃ��������B�^���ꂩ��R���p�̒j���������Ă����B
�u������A���܂��牽�����Ƃ�̂����v
�@�j�q�̖؏e�ɂ��A�e���p�̎w���ɂ��Ă���L���Ƃ������R�l�̒j�������B�j�͂��̓��A���߂Ă����Ȃ���㓁�̋������݂ɂ��Ă����̂��B�����鎙����Ȃɂ����āA����͌����Ɏӂ邵���Ȃ������B
�@�������A���ꂾ���ł͂��܂Ȃ������B���ی�ɍZ���ɌĂꂽ���オ�Z�����ւ����ƁA���̎L���������B�����������ɍZ��������Ɍ����Ђ炢���B
�u�����̑����琶�k�����ƁA�㓁�̋������݂ď����炵���ł��ȁA��̂ǂ��������Ƃł��v
�u�\����܂���B�㓁�̑���ɐ|���������̂ł�����A���c�c�v
�u�����Ƃ��A�܂��������ǂ̏d�傳���킩���Ƃ��B���p�̋������݂ď��ȂǁA�����́A���̂悤�Ȕ�������������Ƃ�̂��v
�u���̕����猵�d���ӂ��������܂��̂Łc�c�v
�@�Z���͑吺�Ŗ����{�肠����L����������ɂȂ��߂āA���̏�����߂悤�Ƃ��Ă���B�R���̋��ɗ��͂�������邱�̐l���́A�@���قǂ̌��͎҂Ȃ̂��A�Z���̂ւ肭�������ԓx���܂��ɁA����͓��𐂂�Ȃ��������Ȃ��Ƃ��v���Ă����B
�@�Z���̂Ƃ�Ȃ��ɂ�������炸�A���X�ɔl�������т�����̂ɑς�����������́A�A��Ă��C��������������ł����B�Ȃɂ������Ă�肳�ꂽ�̂��V���b�N�ł������B��������l�������Ă���킯�ɂ͂������A�����̂悤�ɗ[�M�̎x�x�ɕꉮ�̑䏊�ւނ������B����ƁA���ԂɗƂ̖F�������Ă��āA���z�c���Ȃ�ׂ������ɉ点�Ă��锋�T�𝆂̑̂�ł����B����͋������݂ď������Ƃ��A�����ł��܂��{����̂��ƕ������������B
�u�܂��A���`�ꂳ�ܑ��v�ł����v
�u�ȂɁA�㓁�������ɂ����͂�����͂�낵���ǁA�Ƃ��ς����炫��߂��ł��킢�ȁv
�@����̖₢�����ɁA�F�������T�̍��̂������̏d��������悤�ɉ��������݂Ȃ��猾�����B
�u�ɂ��Ȃ��A���݂��������������ȁA�����v
�@���T�����������グ�A��������߂Ď���Ɓu���A�����������v�F�����Q�ĂĎ�̂�������Ďӂ��Ă���B������@�ɑ䏊�֍s�����Ƃ������T���Ăю~�߂��B
�u����A���܂����̋����𑋂��璭�߂āA���k�ƈꏏ�ɂȂ��ď������āv
�u���ꂪ�A���`�ꂳ�܂������ɋ����悤�ƂȂ����Ă���̂ɁA���k�����̎����Ă���͓̂㓁�̑���ɒ|�Ƃł͂���܂��B����ł́A���������̓㓁�̋������܂�Ŗ�e�̒ǂ��o���݂����ŁA�݂Ă��ĉ������m�Ɏv���Ă��āc�c�A�\����܂���v
�u�F���A���������A����͖�e�̒ǂ��o���⌾�����A�N���Ă����v����ȁA�ق�܂ɔn���ɂ������āv
�@���T�͐��k���������K�p�̓㓁���������ꂸ�ɁA�|�Ƃő�p�������Ƃ��]�������������炵���āA�{��͂����ς�Z���Ƌ����̍���ɂނ����Ă���悤�������B
�@����ɂ��Ă���e�̒ǂ��o���Ƃ́A��Ȃ���I���Ⴆ�����������̂��B����͕Ă��Ƃ��Ȃ���A���T�̓{��̂Ƃ�������邱�Ƃ������ꂽ���ƂɈ��g�����B���̂�����̏K�킵�ŁA�_�앨���r�炷��e��ގ�����̂ɁA���ɏt�����ɐ��l�̎q���炪�W�܂��Ē|�Ƃş��ނ��@���Ė�e�n�ɒǂ��o���ĕ߂܂���A��e�̒ǂ��o���͌������Ė��������̂��B
�@�����ɂȂ��Ă����T�̋@���͂Ȃ��炸�A���オ�o�����悤�Ƃ���ƍZ���ɓn���Ă���ƕ�����������B�w�Z�ł͐E�����炪�����Ȃ�ꂽ�ۂɁA����͍Z���ɔ��T���炱�ƂÂ���ꂽ��������n�����B
�u���ς�炸�̒B�M�ł��ȁv
�@�Z���͕����̂Ȃ��݂ɖڂ�ʂ��A�Ԃ₢���B���T�͂Ȃɂ��ɂ��ĕϑ̉�����p�������A������������ɂ͕ϑ̉����͋��Ȃ��̂ł������B
�u���́A����ł͐��k�����C�ɂȂ�܂����A���T�͂�ɂ������ƁA����搶���S�����w�Z�ɂ��������ɂ����Ă���͂�܂��ĂȁA�Ȃ�Ƃ��㓁�𑵂��邱�Ƃ��ł��܂�������v
�@�����t����ǂݏI�����Z���́A���K�l�z���ɖ���̊�����߂Č����u�����������̂��Ƃ��A���T�͂�ɒm�点�ɂ�炵�܂���v�Ƃ����킦���B
�@�S�����w�Z����㓁����o���Ă�������̓w�͂ŁA�Ȃ�Ƃ��@�����Ȃ��������T���������A�Z�N�����獂���Ȃ܂Ō\�l�قǂ̏����k�ɁA���߂ē㓁�̎������������邾���ł���V�Ȃ��Ƃ��B�ƂĂ��^����܂łɂ͖����Ƃ����̂��A�����I�Ȍ`�𐮂킹�Ă���邾���ł��悢�A�ƍZ�����痊�ݍ��܂�Ăӂ����ш������̂������B
�@�^������͗�N�̂��Ƃ��������o�̂��肳�܂��������A�^���ꂪ�J������Ĕ��ɂȂ�Ƃ������Ƃ��\�ɂȂ��Ă��āA������͊���o���Ȃ��V�l�܂ł�����Ă����B����ɂ͌S����x�@�����ɍ��R�l���\�ƁA���o�̑������܂��ߔN�ɂȂ����̂������B
�@�^����I����Ĉ�T�Ԃ��߂������̕��ی�̂��ƁA�����̐��k�̈�l���E�����ɂ���������Ăтɂ����B�Z��܂ł����ƊO�ɕ��������Ȑ��k�����Ɏ��͂܂�ď��^�̉ݕ������Ԃ��~�܂��Ă����B
�u�₠�v���ɗ����Ă�����c����������Ĕ��B
�u�܂��A��c����A�����͂܂��ǂ��Ȃ������̂ł����v
�u�͂͂́A�s�ӂɉ��������Ă��Đ\����܂���A����������͂Ȃ������̂ł����A���s�܂ōs���Ă̋A��ɋ߂���ʂ������̂ł�����v
�@���̂�����Ɏ�����A�����Ƃꂽ�悤�Ȏd���Ŗ�c�͂��̒j�̎q�̓��ł��B
�u��c���킴�킴���̐E��Ɋ���āA���܂���o����̂Ƃ���֍s�����Ljꏏ�ɂǂ���A�ƗU���Ă���͂��Ăȁv
�@����ǂ͏���Ȃ���_���������Č������B���̓�l���̊Ԃɂ��S�₷���Ȃ��āA�Ɩ���͂�����ƕ��ꂽ������Ă݂����B
�u���傤�lj����Ζ�������������A���̎��Ԃ������܂��w�Z�ɂ���͂��Ƃ��ē����Ă܂���₵���v
�@����ǂ͍_��A������Ƃ��ǂ��Ď�������߂Ă݂���B��c�͍H���̊ē��Z����A�o���̍ۓ��ʂɂ��̃_�b�g�T�����g����������ƁA���ʐF�ɓh��ꂽ�{���l�b�g��@���Ă݂����B
�@��c�̎����Ԃɕ֏悵�ĂƂ��ɋA��邱�ƂɂȂ������オ�A����Ȃɏ�荞�ނ̂�҂��A�^�]�Ȃɍ�������c���u������v�ƌ����Č�����|���Ă���G�X�����݂����o���Ė���̕G�ɒu�����B�܂���������A�ƊJ���Ă݂�ΐΌ��ł͂Ȃ����B���̂Ƃ���G�݉��̓X���ł��A�ő��ɂ��ڂɂ�����Ȃ��Ȃ��Ă���Ό��Ɂu�킠�A���ꂵ���v����́i�폟�j�ƃ��b�e���ɏ����ꂽ�Ό���@��Ɏ����Ă����A������k���Ŗڂ��ׂ߂��B
�@������ł͍_��ƈ��؏W���A�鐔�l�̐��k�������A����������Ȃ���ב�֏�荞��ł���B
�u����K�\�����Ԃ�ŁA�ؒY���J�}�����Ƃ��A�������C�R�H���̎����Ԃ�Ȃ��v
�@����o���Ǝ����ԂȂǖő��ɏ��@��̂Ȃ��A�q�������̒e�b���������������B����ɍ_��܂ł���X�Ƃ��āA�ב�̂����ł͂��Ⴂ�ł���̂��݂Ė���͋�����B
�@�n���h��������Ȃ����c�́A���̓T�����`�[���̓�p����ɓ���������A�����͂��邽�߂ɗ�����������Ƃ�ł��������B
�@�Ƃ����̂����T�͓㓁�̎w������قNJ������̂��A�^��������Ɠ㓁�����̎w����f�����B�����������̒ɂ݂͂����܂�Ȃ��悤�ŁA��������炸�F�������T�̘r�⑫���𝆂݂ɓ��Q���Ă���̂������B���������Ζ���͂��̗l�q���A������Ƃ�����݂����߂Ė�c�ւ̎莆�ɏ����L���Ă������̂������B�����甋�T�̂��߂ɁA�T�����`�[����p���킴�킴�͂��Ă��ꂽ�ɈႢ�Ȃ��B����͂���Ȃ��Ƃ�����������ɁA��c�ɋC�����킹���Ƃ��܂Ȃ��C�������B
�@���ؐ�ɉ˂���v���Ƃ̐�p���A�̂��ċv�����̂Ƃ���Ő��k�������~�낷�Ɓu�݂�ȁA�܂��悹�Ă�邩��ȁv�_��ב䂩�狩��ł���B������Ė�c�͏��Ȃ������ɂǂ��Ɏ~�߂܂��傤�Ɩ₢�������B����͂��̂܂܋���n���Ė�̘e�ɂ���A���Ă̔n�q����̚��֎~�߂�悤�Ɍ������B
�@�Ԃ��~�肽�O�l���ꉮ�ɂ����ƁA���T�͖���̂�����ɂ����c�ɍ_����݂ċ�������������B�����A�킴�킴�T�����`�[����p��͂��ɂ��Ă��ꂽ���Ƃ�m��Ƃ���������сA�����Ղ��悤�ɂ��Ď�����̂ɂ͖����������Ƌ������B����ɔn�q����Ɏ����Ԃ��~�߂Ă��邱�Ƃ�������Ƃ������Ȃ瓹���s���҂�����A�悭������Ƌ@���̂悢��������B��c�ɗ[�т�H�ׂĖႤ�悤�ɂƁA������������Ɏx�x���������A�_��ɂ͖F���̂Ƃ���ւ����Ē�ɂȂ��Ă���`�������Ŗ���Ă���悤�ɁA�������̊`�͊Â�����Ɨ��B���َq�̑���ɋ��������Ȃ̂��B
�@��c�͋��k���č\��Ȃ��ŗ~�����ƌ����Ă���A����ɓ��ւ��Q�肵�����Ɛ\���o���B����͓���Ȃ��S�������ƁA���T�͂܂��܂��@�����悩�����B
�@����͖�c���ē����āA�L��Ȓ�̈���Ɍ�����ɓ��ւނ������B��c�͓r���̒r�ɉ˂���Α���̑��ۋ���n��Ȃ���u���h�Ȓ낾�A�����������̂��v�Ɗ��Q�����悤�Ɍ������B
�u���͓̐̂�\�O�����̌��������ԁA���s�ȉ��~�������Ƃ������Ă���܂��v
�@���オ������ƁA���T�̎g���ŗƂ֊`��Ⴂ�ɍs�����_��A���̊Ԃɂ��߂��Ă��Ęb�ɉ�������B
�u���҂ǂ��̖��̐Ղ����Ƃ����A�Ȃ��o�����v
�@��������͂���Ȃ��_��̐��ɁA���������T�ɂł������ꂽ��ƁA�ɂݕt�������ɁA�_��̓y�����Ɛ���o����������߂��B��c�͂���ȓ�l�̂��Ƃ�����āA�n�n�n�Ə����ŏ����B
�@����ɓ��ł͖�c�ɏ]���A�_����_���Ȋ�Ő������������B
�u�ق��A�哌���푈�����I���v
�@��c�����̌I�̖̍����ɓY����ꂽ�A�̕����𐺂��o���ēǂB���N�̏t�ɍ��삪�A���������ɁA���łɈꃁ�[�g���قǂ������I�̖͂���ɐL�тāA���܂͖���̔w��𗽂��قǂɂȂ��Ă���B
�u���́A���ɎQ�����Ă��܃h�b�N���肵�Ă���쒀�͂̏�����炻��ƂȂ��������b�ł����A�O�Y����̏�́A�w�x�̍Ŋ����킩��܂����v
�u�����A�{���ł����c�c�v
�@����ƍ_����𑵂��ē����A��c�̂��ƂɊ��B
�u�傫�Ȑ��Ō����Ȃ����A�ނ�̘b�ɂ��ƃ~�b�h�E�G�[�̍��ł́A�䂪���̘A���͑��͑��Ȃ�ʔ�Q�������炵���v
�u�O�Y�Z�����̏���Ă����w�x�����̂Ƃ��Ɂc�c�v
�u�Z���ܓ��Ɏn�܂����퓬�ł́A���̓��̂����ɉ䂪���̎O�ǂ��̋�ꂪ�������ꂽ�Ƃ̂��Ƃł��v
�@��c�̘b�����͎���ɒႭ�Ȃ�A����ƍ_��͂���ɖ�c�̖T�Ɋ��݂��Ɋ�������킹�Ď��������Ă�B
�u��e�����w�x�͉Ђ��N�����������ł����A���̋�ꂪ�����Ƃ��͑̂��X������Ȃ��ł��퓬�s���A������Z���Z�����g�n�w�̏̂Ȃ��Ђɂ��唚�����N�����Ƃ̂��Ƃł��B�߂��ɂ����쒀�͂ł́A�����Ōh��ł����Ē��݂䂭�̍Ŋ��𑒑������Ƃ������Ƃł��v
�u���������c�c�v
�@�����ꂢ�ĐO�����_��A�T�̂�������̊������ʼn��x���@���A���̖ڂ���͑嗱�̗܂��j��`�����B
�u�ł��ȍ_��N�A�G��ꃈ�[�N�^�E�������������̂́A�w�x�����ї������͏�@�ł������������v
�u���́A�~�b�h�E�G�[�͂ǂ̂�����ɂȂ��ł��傤�v
�u���{����l��L�����藣�ꂽ�A�쑾���m��ƕ����Ă���܂��v
�u�O�Y�͂���Ȃɉ����܂ōs���Ď��̂ł��ˁc�c�v
�u���݂܂���A�l�̗]�v�Ȓ���ŁA�_��N����コ����ӂ����є߂��܂��Ă��܂����悤���v
�@��c�͎���̌��t�ɂ��A��l�������߂��܂��錋�ʂɂȂ������Ƃɍ��f�̕\����B���Ȃ������B
�u��c����A�ӂ邱�Ƃ͂���܂����A�O�Y�Z�����̏�����w�x�͓G�̍q���͂���������蕿�����Ă����A����ɎO�Y�Z�����̐펀�̏ꏊ���킩���Ă悩�����A�Ȃ��o�����v
�@�_��͏��̍b�ŗ܂��ʂ����A��c�Ɩ���ɘb��������B
�u�C�ɂ����Ȃ��ł��������ˁv����͏�������c�ɘl�т��B
�u�ቜ���܂��v
�@���̂�������݂�ƁA�[�˂̉���������F����������֕����Ă���B
�u��قǑ剜���܂̎g���Œ킳�`�����ɂ܂���ꂽ��ŁA���������܂����B�v�����������Ԃ��n����̂����āA�������c���܂����݂����Ǝv���܂������A����ς肻���ł��������v
�@�����Ȃ���F������Ɏ������ĂɎR������������ڊ`�������o���A�_���������L�ׂĎ�����B�F���͑����āA�����Ԃł���悤�Ȃ��q�͑��ɂ���܂���łȁA�ƌ����ď����B
�u���������R�g���Ɉ��Q�̏����\���ł������������܂��ŁA��c���܂͂����݂ɂȂ��Œ��x��낵�����Ɓv
�u�L��������܂��A�ł����C�����Ȃ����ł��������v
�@��c�͂�����ɋ��k���Ă������A�F���́u�Ȃ�́A�Ȃ�́v�Ə��āA�ӂ����ю���֖߂��Ă������B
�@�ꉮ�ɖ߂�ƁA��c�͖���ɂ����d�ɐ���������������Ɛ����A���Ԃֈē�����Ƃ��łɔ��T���������A�ނ͈������ĕ��d�ɂނ����������Đ��������������ƁA����Y�̈ʔv�ɒ����������Җڂ��Ď�����킹�Ă����B����ɂ��̂��Ƃ��A�v���Ƃ̉ƌn�ɂ��Ē��X�Əq�ח��Ă锋�T�̂Ȃ��Ύ����b�ɂ��M�S�Ɏ����X���Ă���B�ǂ��܂ł���V����������Ȗ�c�ɁA����͉��߂ċC�^�ʖڂȐl���ȂƎv�����B
�@�ꎞ�Ԃ��肪�o��������A�F�����傫�ȕ��C�~��݂������Ă���Ă����B���C�~���Ƃ�Ɩ~�̏�ɕ~���l�߂��w�t�̂����ɂ́A�܂���������Ɠ��C�̂������オ����������\�����\����Ȃ��ł���B
�u�킠�A���傤�Ǖ���������Ƃ����v
�@�T�ɂ���_��̖�c�������������\���Ɏ���o�����Ƃ���l�q�ɁA����͎v�킸�ɂݕt���ē������Â������B�_��͎�������߂ăy�����Ɛ���o���B���̗l�q���݂Ė�c�͏��Ȃ���܂��_��Ɋ��߁A�����������Ɏ���Ď|�����ɐH�ׂ����A�Ō�Ɍ܂���c�����\����|�̔�ɕ��œn���ƁA���h�̂�����Ԃ��낤�ƌ����āA�厖�����ɎG�G�̂Ȃ��ɂ��܂����B
�@���a�\���N�̐����͍~��̂Ȃ��ɖ������B�f���I�ɍ~�葱����͏��̓��ɓ����Ă��~�܂��A��N�ɂȂ����ɂȂ����B���̂��߂ɉהn�Ԃ̒ʍs���ł����ɍ̌@�ꂩ��̃}���K���z�̔��o�ɂ�������肪�����Ă����B���ꂩ��̈˗��ŌܔN���ȏ�̐��k�������A�����瓹�H�̐Ⴉ���̋ΘJ��d�ɏo�Ă��������ƁA����̎��l�N���͌ܔN���ƍ����Ŋw�Z���̐Ⴉ����Ƃ������Ȃ��Ă����B
�@���k�����ƂƂ��ɁA����̓n��L���ɐ������ݐς�������������������B�w�Z�̕\���ւ���Z��ɂނ��āA����a�����{�����Y���܂��̐ϐ�������Ȃ���A�ӂƍZ��̕����݂�ƍ_��̎p���������B����̎p���݂���ƉE����������}������_��ɁA���̐�̒����ǂ������̂��낤���ƁA����͉��b�Ȏv���ŖT�֊���Ă������B
�u�_��A����Ȏ��ԂɁA�܂��ǂ�������v
�u�o�����A������Ƃ����b�ł��ւv
�@�����Ŏ����Ԃ���j��^���Ԃɂ��A�O���̌��ɐ�����т�t�������_��́A�����̐ϐ�C�œ��ł߂Ȃ���A������Ɛ\����Ȃ������Ɍ����Ė���̊���M���B
�@�Z��ł̗����b���ȂƗp�������֘A��Ă������Ƃ���ƁA�_��͎��Ԃ��Ȃ����炱���ł����ƌ����B
�u�o�����A���܂܂Ŗق��Ă������ǁA����C�R�Ɏu�肵�����v
�u�_��A���������Ă�́A���܂��\�Z�ɂȂ����Ƃ���A����ȋ}����ł��A�����ɂ����͓̂�\�ɂȂ��Ă���ł����̂ƈႤ�́B����ɋ@�֎m���茩�K���������O���Ȃ���A�w�������E���Ă������鎖�ɂȂ����ƁA���̂܂����������Ċ��ł����������Ȃ��́v
�@���܂�Ɏv�������Ȃ��_��̌��t�ɁA����͂����킸�����ɂȂ��Ė₢���������ɂ͂����Ȃ��B
�u���ǂ����Ă��O�Y�Z�����̋w���Ƃ肽�����A���������₨�ꂿ���Ɍ������甽�����͕̂������Ă��邵�A���\�y�̈����o������ق��Ĉ�ӂ������o���Ė���֍s�������v
�u����ȁc�c�v
�@���̂Ƃ����k��̊����������肻�̕��֊���ނ���ƁA����a�̂܂�������Œj�q���k�炪�ፇ����n�߂Ă���B�V�c�̂��^�e������Ă������a�̎��͂́A���|���ȊO�͕��i�߂Â������ւ����Ă���B
�u������A�Ⴉ��������A����a�̂����痣��Ȃ������v
�@����͐��k�������ꊅ���Ă����āA�ӂ����э_��Ɍ�������B
�u���@�֎m�ɂȂ�̂��u�]�������ƈႤ�́A����œS���ɓ���������ȁA���C�����̋}�s��Ԃ����������^�b�T�T�`�@�֎Ԃɏ斱����̂�����āA���Ƀ^�R���ł���قǕ�������Ă����̂Ɂv
�u�o�����A���܂ł��̘̂b����ƁA���܂͐V�^�̂b�T�V���}�s��Ԃ������Ă�̂�A�ȉc�S�������Ă̍����\�@�֎Ԃ������Ƃ�v
�u����Ȏ��ǂ��ł������̂�A���́A�����@�֎m�ɂȂ�̂��~�߂āA�Ȃ��u�肵�Ă܂ŕ����ɂ����Ȃ�����̂������Ă�̂�v
�@���̎q�͉����l���Ă���̂�A�����ʂ�Ƃ��Ă�肽���قǂ̏Փ���}���Ė���͍_����ɂ݂����B
�u�킩���Ă���A���ǂ���O�Y�Z�����̋w�Ƃ�ȋC�����܂�̂�A�C�R�ɂ����ēG�̍q���͉��ǂ��������ă��[�Y�x���g�̕@�������ւ��܂��Ă������v
�u�O�Y�̋w���Ƃ邢���C�����͗��h�₯�ǁA��\�ɂȂ��Ă���ł͂�����́A�v���~�܂��ւ�́v
�u�������߂����Ƃ�A�ꌎ��\���ɕ��ߊC���c�ɓ��������܂��Ă�A���Ă݂��A�o������炢�����Řb������A�q���牽���Ƃ��Ɗ���Ă��Ă邪�ȁv
�@�C���t���ƐႩ����ƂɖO�������k�炪�A���������ɓ�l����芪���Č��グ�Ă���B
�u�o�����A���܂Ƀ{�E�Y�̗l�q�����ɋA������ȁA���s����v
�@�_��͂��������ƁA�����Ɣw���ނ��ĕ����o�����B
�u�_��A������Ƒ҂�����v
�@���Ƃ�ǂ������悤�Ƃ�������́A���͂��k��ɑj�܂�Ă��̏�Ō����邵���Ȃ��B�����Ƃ����ł����̂ɁA�ӂ����ь������~�肾������̂Ȃ��A�_��̌��p�͂��̊D�F�̌i�F�̂Ȃ��ɂ���������Ă������B
�@����ɓ����̂�����������낻��t���ɂȂ肩��������A���ߊC���c�ɂ���_���t�����͂����B���x�O�o���ɖ�c����ƌk���ނ�ɂ������A���̊O�o�����ނ�ɂ����\�肾�A��c����͒ނ肪��ŁA�ȑO�ɂ��a�c�ւ���ꂽ�܂�ɓc����̋��e�̔Z���̂ɋ����A������l�ł��̂�����̌k���֒ނ�ɂ������Ɩ��Ă����A�ȂǂƏ�����Ă������B
�@���������ƁA���̂܂��ɓ͂����_��̎莆�ŁA���x�O�o���͑ދ��ō���A�����������ςĂ���킯�ɂ������Ȃ��A�ȂǂƏ����Ă������̂��A����͖�c�Ɏ莆���o���ē`���Ă����̂������B�O�o����҂����˂ėV�s�ɒʂ��N���̕����ƈႢ�A�V�т�m��Ȃ��_��ɂ��Ă݂�Ό��m��ʓy�n�ł͂����Ƃ�����Ȃ��A�����ʐ^����ςĂ���킯�ɂ������Ȃ������̂��낤�B��c���Z�������Ԃ������Ă܂ŁA�_��̑�������Ă���Ă���Ă���̂������������B
�@����͊w�Z�ւ���X�ւ̌ߌ�̏W�z�ɊԂɍ��킹�邽�߁A���k���������O�ɏo�Ă��钋�x�݂̂������ɁA�S�C�̋����ł������������������B�����Ɉ����������I���M��u�����r�[�A������肪�L�тĂ�������グ��ꂽ�B�����ĐU����A���̂܂ɓ����Ă����̂����삪���グ�����������������ƒ��߂Ă���B
�u�����搶�A�����Ȃ����ł����v
�u�C�R�H���̐E�H���Ƃ��Ɋւ�荇���̂́A�ǂ��������̂ł����ȁv
�u�����搶�A�����Ȃ�A�ǂ��������ł��傤���v
�u����A���ꂮ����R������v���Ƃ̖���������邱�Ƃ̂Ȃ��悤�ɁA�F��ȉ\�����Ɗw�Z�Ƃ��Ă��s���_�Ȃ��Ƃł�����ȁA�܁A�V�k�S�Ȃ���̒����ł��v
�@����͂��������ƁA�������|�C�Ɩ���̊��̂����ɓ����Ԃ����B
�u�����搶�A��c����̂��Ƃ������Ă�����̂Ȃ����ł��B���̕��͂���Ȃ����ł͂���܂���v
�u�����ł��邱�Ƃ�l�͋F�肽���v
�@����̍R�c�ɁA����͂��������c���ċ�������o�Ă������B���f���Ă����������������A����̌��t�ɉ��������Ȃ��̂�����������́A�������Ɠ����ɏ�Ȃ��Ďv�킸�܂��o���B�n���J�`��ڂɂ��ĂȂ��瑋�ӂɗ��ƁA�Ђ���ƐL�т��g�}�g�̉A�ɔ����X�q�������Ă���B
�u�v���搶�A�C�ɂ����͂�������낵���ŁA����͋����͂�̓i��������A�܂��ɂ��H���̂����������ԂŖK�˂Ă���͂����Ƃ���������ł������A���̂Ƃ����w�Z���Ȃ�ƐS���Ă���A����U���o���ɂ���Ƃ͂��������A�����Ă��炢�����œ{���Ă͂�܂����������Ȃ��v
�@���̊O���������̂��������p�����́A�Z�ɂɉ����ĐA�����Ă���A�Ė�̎��������Ȃ���ꕔ�n�I���݂Ă����炵���B�ȑO�ɖ�c���H���̎����Ԃŗ���������܂�̂��Ƃ��낤���A���̂��Ƃ����삪�{���Ă����Ȃǂƕ����̂͏��߂Ăł������B
�u�����͂�}���ǂ��������ȁA���܂܂łɂ��Ⴂ���̐搶���������ɂȂ邽�тɉ��₩��Ƃ���܂�����v
�u�����牽�ł��A�����搶�����̂悤�Ȏ҂�ɂ́A�Ȃ���Ȃ��Ǝv���܂����ǁv
�u�����͂�͏��Ƀ}���߂��āA���̍ł��܂��ɂ��Ƃ�Ȃ��ƁA�����ς�̉\�ł���v
�@�p�����͖ڂ���炵�Ă��������Ԃ߂悤�Ƃ��Ă��A���i�͂����тɂ������Ȃ�����̉A�������������B
�@����Ȃ��Ƃ������Ă���O�������o���A�w�Z�͉ċx�݂ɓ����Ă����B�����Ƃ��ΘJ��d�œc�̑����Ȃǂ̔_��Ƃɓ��������㋉���ׂ͂ɂ��āA����̎��O�N�����w�N�̐��k�́A�w�Z�Ŏ��炵�Ă���e��R�r�̉a�ɂ��鑐����ƁA�{�̐��b�Ɍ��œo�Z���Ă����B�����̓����͊ώ@�p�Ƃ��������A�������R�r�������ẮA�w�Z���O�ɂ����ĉ����������邽�тɁA�H�p�Ƃ��ċ������̂ł������B
�@����͂�����Ƃɂ����k��̂��߂ɓo�Z���邱�Ƃ����������A���i�̓��͖F����R�g����ƂƂ��ɁA�~�̂������ɕ����d���o���R�d���ɏo�����邱�Ƃ����������B
�@����ȂȂ��A���܂��ܓo�Z���Ă��������\�O���̂��ƁA���Ƃ̕��e����d�b���������Ă����B�x�ɂŖ߂��Ă����_��A��c��A��Ă����Ƃ����̂��B��l�͑������}���ނ�ɏo�����Ă��邻���ŁA����ɂ��߂��Ă��Ƃ������̂������B�_��͖�c�̂��Ƃ��A������悭�m���Ă�������ƏЉ���炵���B�����Ȃ茩�m��ʐl����A��Ă����A���e�̍��f�Ԃ肪�ڂɕ����ԁB
�@�ċx�݂��������͊w�Z�ɂ͏o�Ƃ��Ǝv�Ƃ������A����܂œd�b�������ɂ����b�オ�������ƁA���e�͌����u�D�Ԃ̎��Ԃ��킩���A�w�܂Ō}���ɂ������̂��v�ƌ����ēd�b������B
�@�_��͂܂��������Ė�c���Ƃ��Ȃ��ċA�Ȃ����̂��낤�A�O�Y�̏��~�ł�����A����͕�Q������˂đ����֖߂��Ă݂邱�Ƃɂ����B
�@���̓��̂����ɖ��オ�������̎��Ƃɖ߂蒅�����Ƃ��́A�����Ă̓������łɕ�ꂩ���Ă����B�ނ肩��߂����_��Ɩ�c�͂��łɈꕗ�C���тĊ����Ȃ������̂��A�J�������ꂽ�{���̉������痁�ߎp�Ŗ�����}�����B���������������c�̕G�ɂ́A�Ȃ�Ɖb�ꂪ���傱��ƍ����Ă�������݂Ă���A�܂��A���̎q�l���m������Ȃ��ŁA�ӊO�Ɏv���߂Â��ƁA
�u�{�E�Y�A����Ƃ��ꂳ���ꂽ���v
�@�_��̌��t�ɖ�c���u�ǂ����A���ז����Ă��܂��v�Ɣw�������߂Ĉ��A�������B�v���U��ɉ������e�ɔ�т��Ă��邩�Ǝv�����b��́A���オ��������L�ׂĂ���c�̋��ɂ����݂��A���������点�Ă��܂��B
�u�������Ȃ���A�a�����ςȂ��́A�ق����炩�������Ȃ��v
�u����Ȍ��������āc�c�A�����Đ���t����Ă����Ȃ��v
�@�o��̂�����Ƃ����y���ɁA��c���u�n�n�n�A�_��N�ɗU���ă��}���ނ�ɂ��܂����B�����Ƃ���ł��˂��A���̏㗬�ɂ͎R���������ċ������Ȃ��v�Ƙb��������ď���Ƃ�Ȃ��B
�u���݂܂���v����͖�c�ɘl�тȂ���_������ڂ��ɂނƁA�ނ͂̓y�����Ɛ���o���Ď�������߂��B
�@�䏊�ւ����ƕ�e���ڂ��݂������Ă��āA������݂�Ɓu�悤�߂����Ȃ��v�Ɗ������Ɍ������B
�u����A�O�Y�ɋ����Ă��A���̎q�͂ڂ��ݍD��������������v
�@���������ĕ�e�͑傫�Ȃڂ��݂��M�ɓ�̂��A����Ɏ�n�����B�ڂ��݂̎M�����������~�ւ����ƁA���d�ɂ͖�c�̎�y�Y�Ǝv���銱���o�i�i�������Ă���B���̖T��ɂڂ��݂̎M���Ȃ�ׁA�X�C�ɉ��Ɛ����������ĎO�Y�̐^�V�����ʔv�ɗ��炵�Ď�����킹���B
�@�O�Y�A�����S���Ȃ��Ă���A�͂��N���߂��Ă���������B�_��͂��̋w�����āA�C�R�Ɏu�肵�ĕ����ɂ����Ă��������B�O�Y�A���������₨�ꂿ���ׂ̈ɂ��_�������Ă���Ă�c�c�B�Â��ɔ��ވ�e�ɁA����͋��̂����Ō�肩�����B
�@�_������ɓ����Ă��āA����̖T��ɐ�������Ƃ��Ȃ��悤�ɗ��炵�č�������B
�u�_����Ȃ��c��������A�ꂵ�āA���������₨�ꂿ���h�����Ă���ƈႤ�́v
�u�܂����瑐���J�ցA�ނ�Ɉē����܂��Ɩ��Ă����A���x�O�������o������U���\�����A���イ�킯��v
�u���ɂ́A��������v
�u�o�����͖�c����̂��ƁA�ǂ��v���Ă���̂�v
�@�����オ�낤�Ƃ������ɁA�_��ۂ�ƌ������B
�u����������Ǝv���Ă��邯�ǁA���ꂪ�ǂ��������v
�u�o�����A���ꂩ�炸�����Ƌv���̉Ƃ�w�����Ă����C�Ȃv
�u�}�ɉ��������o���̂�c�c�v
�@���̎q�͉������������A����͍_��̊���݂߂��B
�u�o�����A��c����ƍč������炦���̂ɁA�b������ꂩ��͕��e���K�v�ɂȂ��Ă�����v
�u�_��A������A����Ȉ�l�O�Ȃ��Ƃ������悤�ɂȂ�����B����ȐS�z���Ă����ł�������v
�@���������o���̂₱�̎q�́A����͂܂��������������ȍ_����ɂݕt����ƁA���̂܂܍��𗧂����B���̕��Ƃ��Ȃ�ƁA���R����̕��������Ɛ���������{���ł́A��c�����C�悭�b��̑�������ėV��ł���Ă����B
�@�₪�Ēh�Ƃ܂����I���ĕ��e���߂��Ă���ƁA�F���[�H�̑V�ɂ����B�H���ł̓��z���Ƃ�����y�Y�̃r�[�����c�ɒ�����Ȃ���A���e�͓������x�������Ėڂ��ׂ߂Ă���B
�u���コ�����t�ǂ��ł��v
�u�܂��A������ɒ������đՂ��܂��v
�@��c�̎肩��r�[���̕r�����A�t�ɖ�c�̃R�b�v�ɒ����ł��B�_��͑O�ƈꏏ�ɂȂ��āA�v���U��̂��y���ł���ڂ��݂�j�����Ă���B���Ԃɓ�l���ނ��Ă������}���̉��Ă��ƈ��ƍ̎ϕ������̂����₩�ȑ������сA���e��o�킪������킹�Ĉ͂ސH��́A����ɂ͖Y�ꂩ���Ă����Ƒ��̒c�R�������B
�@�����͒��߂��ɂ͔��Ƃ����_��Ɩ�c���A����͎��̗��R�ɂ���O�Y�̕�Q��ɏo�������B���e�͍���ɑ����ĒI�s�ɏo�����Ă���A�ꏏ�ɂ����Ƃ�����e�͒��̌{���̉Ԃ���܂��đ��˂��B��ւƑ����}�ȎΖʂ̓����A�������p�̍_����ɊF�����ɂȂ��ēo���Ă������B
�u�������߂��Ȃ��A���コ��͂���Ȃ����Ƃ���ŁA���܂ꂽ�̂ł��˂��v
�@��n����͐^���ɍL����W���������낹�A�������璩���̍��ԂɌ����B�ꂷ��ƁX�┒������k���̗���ɁA��c�͂������Q�����悤�ɐ����������B
�u�R�Ɛ��܂���A����Ȃӂ��Ɍ����đՂ��ƋC�p���������ł���v
�u�l�����R���ƒ��挧�̂قڋ��ɂȂ�R���̐��܂�ł�����A����ȕ��i�͖��ɉ��������v
�u��c����͉��R�̏o�g�Ȃ̂ł����v
�u�����A�����Ƃ��قƂ�NjA�邱�Ƃ͂���܂���B���������̐܂�ɂ͋A�Ȃ������łɓ���������܂������A���̎��̒��Ԃ̂����O�l���펀���܂����B�H���ɋ߂Ă��ĕ���Ə��ɂȂ����l�́A�Ȃ��ނ�ɐ\����̂Ȃ��v���ł��v
�@����ɖ�������Ă��āA�ቺ�ɍL���锠��̂悤�ȕ��i��]�݂Ȃ���A��c�͂���݂�Ƃ��Č������B
�u�o�����A�M���̐��͂��̂����Ƃ����̕���Ȃ��v
�@��e�ƂƂ��ɁA��̂܂��ɔɂ��̎}���Ă����_��w�ォ�琺���������B�䌴�Ƃ̕�n���炳��ɓo��Ǝ���X�̏Z�E�̕�����ԕ�n������B���̉��ɂނ����āA�͂��ɏb���炵�����̂��T���Ɣɂ���̂Ȃ��ɕ���Ă���B���̐�ɂ͈�ЂɏH�t�������J�����������K������͂����B
�u�M���Ƃ����̂͂��̎R�ɐ��ޔ����ςŁA�Ȃ�ł��E���ꂩ���Ă����q�ς��A�܂������������o��������Ĉ�Ă���ł����A�R�ւ������Ă������������ɂ��Ă��āA�a�c�̑�̂Ƃ��ɂ̓{�E�Y���̂Ȃ�����~���o���Ă��ꂽ��ł��v
�u�ق��A�ʔ������Șb���ȁv
�@�_��Ɍ����āA�݂̉��ɖڂ����Ȃ����c�������B
�u��c����͋Z�p�҂�����A����Ȕ�Ȋw�I�Șb�͐M���͂�ւ��v
�u����A�l�̋����ɂ�����ɗ�炸�ς�K�ɂ܂��d���b�́A�����ς�����܂�����v
�@�����A�_��͉��ł������Ă���ɁA����͉��ƂȂ��C�p���������Ȃ��Ė�c�̖T�𗣂�āA�O�Y�̕�O�ɋ���������ׂĂ����e�̂��֊���Ă������B�O���߂��𗬂����艱�ɋ���ł��āA�����������_���ɂ����n�߂��Ƃ��������B
�u�_��A�O�Y�ɐ��͂����Ă���ł���v
�@����܂ŖفX�ƁA�Ԃ�����|���̐������ւ��A�g���Ă����{���̉Ԃ�V�����}�������Ă�����e�̐����Ȍ��t�ɁA�_��͋h�������悤�ɕ��ۂ��������܂ܕ�e���݂Ă���B������܂��A���ɂȂ���e�̋����꒲�ɋ������B
�u�̂��O�Y�A�[���C�̒�ɒ���ǂ�̂ɁA�������͂悢�̂��v
�@��e�͍��N�̏t�Ɍ��������O�Y�̐^�V������������悤�ɂ��Č�肩���A����Ă�����@�����Ƃ肻��ŕ��@���n�߂��B
�u�O�Y�Z�����݂Ă���A�����C�R�ɓ��������A�G�̍q���͂����ǂ����߂ČZ�����̋w���Ƃ��Ă�邩��ȁA�݂ĂĂ����ȁv
�@�_��������p�Ōւ炵���ɕ�Ɍ�肩����T�ŁA�O��������������Đ_���Ɏ�����킹�Ă���B�����������킹�Ȃ���A�Y�������̉������݂����ɂ݂������A��̍b�ł����Ɩړ���@���U��Ԃ�A�w��Ŗ�c���Â��ɍ��������Ă����B
�@���N�͓�w�����n�܂��Ă��A��N�̂悤�ɏH�̉^����̗\��͑g�܂�Ȃ������B�Z�ɂ�Z��̂܂��̋n�𗘗p���č���n�߂��؉�������ɍL�����A���܂ł́A�ق�̋͂��ȋn�������k����A���k�����̎�ɂ���ĊÏ����Z���Ȃǂ��A�����Ă����B�Z��̕Ћ��ɂ͔͑�ɂ���m�◎���t�Ȃǂ��͂��܂�Ă��āA���͂�^���ꂻ�̂��̂����ɂȂ�������B
�@����ȂȂ��ŁA�Z�ɂ̂�������ɔ���R�̎Ζʂ��J�����ăq�}�Ƃ����A����A���邱�ƂɂȂ����B�Ȃ�ł����̐A���̎�����A��s�@�p�̖�������Ƃ̂��Ƃ������B�E����c�ɂ����āA�Z�����ォ��̒ʒB�Ƃ��āu��X�I�Ƀq�}��A����^���𑣐i���邱�ƂɂȂ����v�ƕ����̂́A��펞�ɍՂ�Ȃǂƕ�����Ă���ꍇ�ł͂Ȃ��ƁA����̏H�Ղ�����~�߂ƂȂ����\�����̂��Ƃ������B
�u���łɍZ��ɂ͐A���邾���̗]�n���Ȃ��A���̎R���ł��J�����邩�v
�@���̍Z���̔��Ă��āA��̍~��Ȃ������ɊJ�����Ă����āA���t�̎펪���ɊԂɍ��킹�悤�ƁA�ϋɓI�Ɍv��������i�߂��̂͋����̍��삾�����B
�@�������ď\�ꌎ�ɂȂ�ƁA���悢�搶�k�������J����Ƃɋ��o������������Ă����B
�@�����Ȃ̐��k�����́A�~��ɔ����ċ����ŕ����d�X�g�[�u�̐d�����ɑ����L�̎R�ɏo�������B���̂��߂ɘZ�N���ȉ����J����Ƃɓ�������邱�ƂɂȂ�A����̎��l�N�����A���̈ꎞ���ڂ���Q������悤�Ɏw�������ꂽ�B
�@�E����c���I���ċ����Ɍ������Ȃ���A����̋C�����͏ł�Ɏ������v���ɂƂ���Ă����B���̂Ƃ���ۊO�̋ΘJ��d�����Ɏ��Ǝ��Ԃ�����āA�v���悤�Ɋw�K���i�߂��Ȃ��̂ɔY��ł����B
�@�����̂悤�ɒ����琶�k�������J����d�����ɓ��������Ȃ��ŁA���Ƃ��ǂ�ǂ�x��Ă������ƂɂȂ�B�ߑO���ɕ�d�������I���ċ����ɖ߂��Ă������k�����́A����Ȃ��J���ɔ����Ă��āA�ߌォ��̎��Ƃ͕��ǂ���ł͂Ȃ������B�N�������ĎO�w���ɓ���A����ǂ͐Ⴉ����ƂȂǂɂ��A�����ł̎��Ǝ��Ԃ�����邱�Ƃ��\�z����邾���ɁA����̎v���͐[���������B
�@����ł��ꎞ���ڂ���̕�d�����͂Ȃ����낤�ƁA���ɎZ���Ȃǂ͌ߑO���ɁA������ꎞ������������̎��ƂɎ��Ԋ���g��ł������̂����A�����Ȃ�Ƃ͗\�z�O�������B
�@����͍��Ɋ|���Z�̎��������ƁA��l�����d�ɗ��������Ɍ������Ė������������B��Ȃ������������҂́A���̂܂܊J���Ɍ����킹���B���₩�c���ĉ������҂ɂ́A�����Ȃ��������K���ė����̏h��Ƃ����B�قƂ�ǂ̖�肪�����Ȃ����l�̎҂͂��̂܂܋����Ɏc���Ė���͎��Ƃ𑱂����B
�@���̊O���A�Z�ɗ��̟�̖�Ζʂ֊J���Ɍ��������k�����̗����āA���k��͗��������Ȃ��l�q���B
�u���̊O�͋C�ɂ�����ƁA���ꂪ�����Ɖ�����悤�ɂȂ��Ƃ��ȁA�����l�ɂȂ��Ă��獢�邱�ƂɂȂ���v
�@���k�����B���Ă���ƁA�L���𐠂�X���b�p�̉����߂Â��Ă��A�����̌˂����\�ɊJ����ꍕ�삪�����Ă����B
�u���Ƃ����Ă���Ƃ��낪����ƕ����Ă���A����͂ǂ��������Ƃł��v
�u�����搶�A�O�\�������P�\�����肢���܂��B���܊|���Z�̊�b���o���Ă����Ȃ��ƌܔN���ɏオ��A�Ȃ��̂��Ǝ��Ƃ��Ȃ���Ď��c����Ă��܂��܂��v
�u�w�Z�͂��Ȃ��ɂ��̂悤�Ȃ��Ƃ͗���ł��܂����A�����ɐ��k�S����A��ĊJ����Ƃɉ�����Ă��������v
�u�ł����A���߂Ċw���̑S�����A�|���Z�̊�b���o���Đi�������Ă�肽���̂ł��v
�@�~��̎����܂łɗ��R�̐����J������ƂȂ�A�������̂悤�ɒ�����ΘJ��d��Ƃ��������낤�B����͂�����悤�Ȏv���ŁA�����̍���ɑi�����B
�u�������l���A���Ȃ�������Ȃ��Ƃ��l���Ȃ��Ă����A�E����c�Ő\�����킹�����Ƃ������Ǝ��s���Ă����悢�̂��v
�@����͂��������I����ƁA���k�����Ɍ������āu���܂������A�����ɋ������o�č�Ƃɂ����Ȃ����v�����������Ŗ��߂������B
�@�����Ɩ���̂������݂Ă������k�����́A����̈ꊅ�ɂ���Ăċ��ȏ��⒠�ʂ����ɂ��܂����݈�Ăɋ�������o�n�߂��B
�u�����搶�c�c�v
�u���܂͔�펞�Ȃ̂ł��B���̐푈�ɏ��ĂA������ł����͂ł��܂���v
�@����͂������c���ċ������o�Ă������B��������X���b�p�̉��ɖ���͋C���̂ӂ�����Ȃ��܂܍���@���Ă���ƁA�O�Ő��k�����̑�����������B�₪�ĘL�����삯�Ă��鑫�������āA�ܔN���̒j�q���k����э���ł����B����̎����́A�j�q���k������������ƒm�点�ɂ����̂������B�����Ă��̐��k�̂��Ƃɂ��ċ������o������́A�p�������̂܂��Ő��l�̐��k�Ɉ͂܂�Ă��鐶�k�̂Ƃ���ɋ삯������B��@���������t�����E����x���Ă���q�́A��Ԃɍ��ɏ��������������ĊJ����Ƃɉ����ׂ��ŏ��ɋ������o�Ă��������k�������B
�u�����芙�ł�����Ɛl�����w����������炵�������ŁA���~�߂����Ă����܂������A���܂�����Ȉ�@�֘A��Ă����܂���v
�@�n�ʂɓ_�X�Ƃ��錌�����݂ĐF����������ɁA�p�����͐���������ƁA������������k�����]�Ԃ̉ב�ɏ悹�čZ����o�Ă������B
�@�C���Ƃ�Ȃ���������́A���R�̊J���n�ւ����Ă݂ċ������B���k�������k�����Ƃ��Ă���ꏊ�́A�F���⊝���������Ă��邤���ɁA���k��̔w��قǂ̟��������Ƃ���ɖ��Ă��āA�z���͂��Ă������������A�ƂĂ���w�N�̐��k��̎�ɕ��������ɂ��Ȃ������B
�u�搶�A�����ɋC�����Ȃ�A���J�f������łȁv
�@�i�^�ş��蕥���Ă������k���A����ɂނ����ċ��ԁB
�u���J�f���h�����Ă����A坂����邩���m��A�F���C��������v
�@�����ɗ�������đ傫�Ȑ��Ő��k��ɒ��ӂ𑣂��Ă���ƁA�������ꂽ�Ƃ���ŘZ�N������Ƃ����Ă��āA������ē��Ă����L����������݂ċ߂Â��Ă����B
�u������������k�̒S�C�́A���܂����v
�@�����̂��ƂȂ��狏�䍂�ɂ��̂������L���ɁA����͈ޏk���āu�͂��v�Ə��������Ȃ����B
�u���k������������Ƃ��ɁA���܂��͋����ɂ������������ȁA����ŁA���t�Ƃ��Ă̋߂��͂����Ă���C�����v
�@�L���̓{�萺�ɁA����܂ł�����Ă����B�L���Ƃ��Ȃ��ɃQ�[�g���������������͒n�����܂Ōł߂Ă���B
�u���k�͉E�l�����w�����䂵���̂����A�l�����w�͏e�̈������������厖�Ȏw���B���̕��������ƂŁA�������̐��k�������Ƃ��Č䍑�ɂ�����ł���悤�ɂȂ�����ǂ�������肩�A���t�Ƃ��Ė����ɒl���邱�Ƃ������v
�u���ケ���������̂̂Ȃ��悤�ɁA�������\���n���܂��̂Łv
�@�܂������Ă�L�����܂��ɁA�������Ȃ���ĕ����������A���̂������ɍ��삪�����ē���B
�u�������A���܂��̂悤�Ȏ҂ɁA���̏�����S����������C���Ēu���͖̂�肾�B�����������t�̕��ł��Ȃ��A���������Ƃ̑䏊�ɔ��������āA�J�}�h�̉̔Ԃł����Ă���悢�̂��v
�@�L���͍���̎��Ȃ��ȂǁA�\�����ƂȂ������l�|�����B
�u�F�Ȃɂ����Ƃ�A��Ƃɂ��ǂ�v
�@���̊Ԃɂ��A�܂����͂�ł��鐶�k���������삪�ɂݕt���Ĉꊅ�����B������܂����������v���������ɂ��炦�Ȃ���A��l�Ɉ�������ƁA���k��̂��Ƃ�ǂ��Ă��̏�𗣂ꂽ�B
�@���̓��̗[���̂��ƁA����͊w�Z�̋A��ɏ��Ȉ�@��K�ꂽ�B�ҍ����ɂ͏\�l�قǂ̋q���������A��t�ɂ����q���q��������݂�ƋC�𗘂����ė\��q���Đ�ɌĂѓ���Ă��ꂽ�B
�@�f�@���ɓ���������́A���Ɍ������ăJ���e�̋L�������Ă����@���̌[���Y�����������Ȃ�A���k�̉���̂��Ƃ�u�˂��B�S�z��̖���ɁA�[���Y�́u���^�������Ȃ���A�\��������Ύ���v�Ƃ��Ƃ������Ɍ������B
�u���������Ă��A�S�C�̈������������̂ɁA�w�͂����Ɠ����ł��傤���v
�u�S�C�̈��������Ɓc�c�A�N������Ȕn���������Ƃ������Ƃ�̂��v
�u�������̎q�̎w�������ʂ��߂ɁA�����ɍs���Ȃ��Ȃ�悤�Ȃ��Ƃ�����A�S�C���t�̎��͖����ɒl����Ǝ����܂����v
�u������Ƃ��������̂��B�����琶�k����������ǂ��o���A�J����ƂȂǂ������邱�Ƃ̕����ǂ��ɂ����Ƃ�B�w������낻���ɂ��āA�����h����킯���Ȃ��̂��v
�@�[���Y�̕��S������������ɑ傫���Ȃ�A�q���q���f�@���Ɋ���̂������Ă����Ȃ߂��B
�@���k�̉��䂪�厖�Ɏ���Ȃ��������ƂɁA�����Ȃł��낵������͋v���U��ɐl�a�蓻���z�����Ɠ����}�����B
�@��������͖���̊뜜�����Ƃ���ɁA���k��͒�����J����Ƃɓ�������āA�����Ŏ���Ƃ͋ɒ[�ɍ������X���������B
�@����Ȃ�����̕��ی�̂��ƁA����͒����班�����C���Ȃ̂������āA�E�����ɋ��c��Z�����疽����ꂽ�K���ł̌���������Ă����B�����֗p�������A�d�b���������Ă���ƒm�点�ɂ����B�d�b�͖�c����ŁA���ܓa�c�w�O�̗X�ǂ���d�b�������Ă���ƌ����B�v���U��ɕ�����c�̐��ɁA���ׂŏd���������C�����e�B�}�ɂ܂���������A����A�w�O�ɂ������łɏ��Ȉ�@�ɂ���ĕ��ז�𗊂����A����͋}���ʼnw�Ɍ��������Ƃɂ����B
�@�Z����o���Ƃ���ŁA�܂�悭�猩�m��̑��̒j�����]�ԂŒʂ肩����A���̉ב�ɏ悹�Ė�����B������ւ����Ƃ����j�̎��]�Ԃɕ֏悵���������ŁA�a�c�w�ɂ͎v������肩�Ȃ葁���������B
�@�w�ł͂����Ƃ��Đl�C�̂Ȃ��ҍ����ŁA��c����l���݂Ȃ��Ƀx���`�ɍ����Ă����B�u�₠�v��c�͖�����݂�ƏΊ�ŗ����オ��A����̎��������ƈ������B���ꂪ���܂�ɂ����R�ł��������߁A�����̊Ԃ������Ė���͖�c�̎�̊��G���m���߂��B
�@��c�͏o���̋A��Ɋ�����ƌ����A�G�X����V�����̕�݂����o���ƃx���`�̂����ɒu�����B��݂��w���ĐΌ����ƌ����A����ɉ��ϐ��̕r�����o���Ė���̎�Ɉ��点���B
�u�܂��A�Ό������ł��������̂ɁA������ґ�Ȃ��̂��v
�u����A���ŎG�݉��̑O��ʂ肩����ӂƌ���ƁA�Ό����u���Ă���̂��ڂɓ�������ł��B�������˓I�ɔ�э���Ŕ������݂܂����v
�u���Ȃ����ȂǁA�w���g���ŐΌ������K�ŏo�Ă���Ƃ�������Q�ĂĂ�������A�Ƃ��ɔ����Ă܂������v
�@��c�͖���̘b�ɏ��Ȃ���A�����Ȏ���݂������Ǝ�n�����B
�u����͏o����Œ��َq�ɏo���������ł��B�c��Ղ��Ă��܂����v
�@��c�͂��������ďƂ�����������ƁA�}�ɐ^�ʖڂ���������ɂȂ��āA�������݂�悤�ɐ�����߂Ęb���������B
�u���́A���̂܂��̓��j���ɍ_��N�����܂����B�덆�^�����͂̋@�֕��Ƃ��Ĕz�������܂����Ƃ̂��Ƃł��v
�u�_��c�c�����͂Ɂc�c�v
�@��c�͂��̂��Ƃ����ɒm�点�邽�߂ɁA����������̂��ƌ������B����ɂ͐����͂̂��ƂȂNJF�ڂ킩��Ȃ����A���悢��_����O�Y�̂悤�ɉ����C�̐�n�֍s����������̂��낤���Ǝv�����B
�u���肪����܂ŁA���ƈꎞ�Ԃ�����̂��A�����ւ����ȁA�������̗����łȂɂ��H�킹�Ă���Ȃ����Ȃ��A����ς�ʖڂ��낤�ȁv
�@�ҍ����̑��z���Ɍ������̗������ق߁A��c���Ƃ茾�߂��ęꂢ���B�c�ɒ��ɂ��Ă͒������A�������⊄�B���قɈ��݉��Ȃǂ��������ԉw�O�̈�s�́A���̐푈���n�܂�܂ł̓}���K���z���ړ��Ă̎R�t��̌@�v�A�z�Β����l��Œ��Ԃ��������Ă����Ƃ��낾�����B
�@��c�̙ꂫ�ɊO�Ɏ������ނ�������́A�ꌬ�̊��B����������o�Ă��鐔�l�̒j�����̂Ȃ��ɁA�����̍���̎p�������Ĕ��˓I�ɐg���Ђ��ĉB�ꂽ�B���葤����C�t�����͂����Ȃ��̂����A��c�Ƃ���Ƃ��������ɒm��ꂽ���Ȃ��Ǝv���ӎ��������������̂��B
�u���肩��݂āA���̘A���̓}���K���z�̒����l�����肾�ȁv
�@��c���ނ�ɖڂ��������炵���A�ڂ����ƙꂢ���B�Ȃ����삪���̂悤�Ȑl��Ƃ���̂��A����͂�����x���z���ɂ悭�݂�ƍ��R�l�̎L���̎p������B���Ԃ����Ȃ̐ڑ҂����̂��A�ނ�͂���Ƃ킩��Ԃ���Œk���Ȃ���w�O�̍L�������A�}���K���z��ςݏo���������ݐ��̕��֕����Ă����B
�u���̎��߂ɗ����Ŏ������߂�̂́A�����������R���i�C�̉��b�ɂ��������Ă���A���Ȃv
�@��c�͖���̎����Ś������B�����Ȃ������́A�ӂƒ��ٓ̕���H�ׂȂ��܂��������Ă��邱�ƂɋC�Â��āA��܂̂Ȃ�����ٓ��̕�݂����o���Ɩ�c�ɍ����o�����B
�u���́A��낵��������A����H�ׂĂ��������܂��v
�u�����A�\��Ȃ��̂ł����A�悩�������A���ꂶ�ቓ���Ȃ����Ղ��ċD�Ԃ̂Ȃ��őՂ����Ƃɂ��܂��v
�u���t����̔����тƂ��Ђ��������ŁA�p����������ł����v
�u���̂Ƃ���O�H���H���ŎG������H���Ă�l�ɂ́A��ѐ�̂��y���ł���v
�@��c�͕ٓ��̕�݂����ƁA�G�X�̂Ȃ��ւ��܂��Ȃ�����������Ɍ������B
�@���Ԙb�����ĉ߂��������ɁA�₪�ĉ����Ԃ����������B��c�������������ƁA����͂�����x�w�Z�ւ��ǂ낤���A����Ƃ����łɏ��Ȉ�@�֊�蕗�ז�̏��������Ă��炨�����ȂǂƎv�Ă����Ȃ�������Ă���Ɓu���コ��A�w�Z�ւ����Ȃ���v�Ɛ���������ꂽ�B�w�܂ōz���^�т����A�ӂ����э̌@��ւނ�����̋��Ԃ������猩�m��̒j�������B�j�͈��؏W���̎҂ŁA�w�Z�܂ŏ悹�Ă��Ƃ����̂ŁA���Ȉ�@�ւ͂��̎��ɂ��邱�Ƃɂ��ď���Ă������Ƃɂ����B
�u�J�}�X�\�ܕU�����x����ɁA��\�U�ɑ��₵�Đς߂��Ƃʂ�������B�����̓z��A�悤���ׂ����o�����ƁA���������ݎԂɏo���邾���ςݍ��ނ��肶��v
�@���𑀂�Ȃ���A�j�͑O���ނ����܂܂Œ���͂��߂��B
�u���������A����������ƌ����ƁA��n�ł͕���������q���Đ���Ă���A�����ƒ�͂��o�����ƁA�����������Ɖ���������B���R�l��̎L���͂�Ȃǂ́A�䍑�ׂ̈��A�ׂ��������Ԃ�w�Z�̐��k�ɎԂ̌㉟������������悢���ƁA�L���͂�������̍���͂�������̓z��ɃL���^�}�����Ă����Ƃ邩��Ȃ��c�c�v
�@��s�b�����Ȃ���A�j�͎v���o�����悤�ɋ��̐K�Ɍy���ڂ����Ă��B
�@������A�o�Z��������́A�Z��̂Ƃ���ŗ����킹���N�z�̏����t�Ɖ�����B�݂��Ɉ��A�����킵�����ƁA����͕����Ȃ������ɁA���Ȍ[���Y���x�@�ɕ߂܂����Ǝ��ł��������B
�@��������̖₢�����ɂ��A�a�c�̊X�͂��̘b�Ŏ������肾�ƌ����A����͂���ȏ�͒m��Ȃ��̂�����ł��܂����B�Z�ɂɓ���Ɩ���͘L�����s���������k��Ɉ��A��Ԃ��Ȃ���A�܂������p�������ւނ������B�����Ƃ����Ɗw�Z�̎g���œa�c�֏o�����Ă���p�����Ȃ�A�ڂ�������m���Ă��邩���m��Ȃ��Ǝv�������炾�B
�u���ł��@���搶���A�w�Z�̋ΘJ��d��������Ȃ��ꂽ�Ƃ��A���ꂪ���I�����Ƃ��ʼn����x�@�̓����ۂ̌Y�������ĘA�s����Ă����͂����炵������v
�@�p�����͒���Ȃ���A��Δ��̖�ʂ���~�ɂ̂����}�{�ɓ��𒍂����B
�u���A���ꎄ�������Ă����܂�����v
�@���ꂪ�Z�����֎����Ă������̂ł��邱�Ƃ�m�����́A�}�{�ɓ����݂��̂����~�����ƍZ�������������B
�@�Z�����ւ����Ɠo�Z���Ă��鐶�k�߂Ă���̂��A�Z���͓�����ɔw���ނ��Č����g�܂ܑ��ӂɗ����Ă����B
�u������������܂��v
�@����̈��A�ɐU��������Z���́A�������Ƃ�������Ŋ��ɂނ����֎q�ɍ������낵���B���オ�������Ȃ�����Ȍ[���Y�������ɘA�s���ꂽ���Ƃ������o���ƁA�Z���͓r�[�ɋ�X������������B
�u���̂��Ƃ͈�ؘb���ȁA�w�Z�Ƃ͊W�Ȃ����Ƃ���v
�u�Z���搶�A���͏��Ȉ�@�̐搶�ɂ́A�����Ƃ����b�ɂȂ��Ă���܂��B�����܂ɂ�����āA���Ԃ߂̌��t�̈�����������v���܂��B�����ɂł��f�������v���܂����A�������炦�܂��v
�u�Ȃ��A����͐�ɂȂ�Ƃ���A�킵�Ƃĉ@���Ƃ͗F�l�̂Ȃ����Ⴊ�A���ƂȂ����҂Ɋւ�邱�Ƃ͂ł���B�������A���܂͂���p�����ɐ������̂͑����Ƃ��̂킵����A�y���Ȃ��Ƃ����������瑺����킵�̗��ꂪ�ǂ��Ȃ��v
�@�Z���͖���̊����������C�ɂ܂������Ă��B�Z���̗\�z�O�̌����ɖ���͈�u���t�����������̂́A����ň���������킯�ɂ͂����Ȃ������B
�u�ł����A���̂��т͉�����������k��A��Ă�����������ł��B���̂Ƃ��@���搶�́A����Ȓ�w�N�̐��k�܂Œ�����J����Ƃɏo�����ĂƁA���{��ɂȂ����A�������ꂾ���̂��Ƃł��B������A���Ƃ͂Ƃ������̎��̕s���ӂ���ł��v
�u�킩���ЂƂ���A��������������ꂽ�҂̉Ƃɏo���肷��ƁA���܂͂ւ��������Ă���Ƌ^���邾���ł͂��܂�A����Ȑl�Ԃ������ɂ��Ă������̂��Ɗw�Z�̐ӔC�ɂȂ�v
�u�c�c�c�v
�u�������A������Ȉ�@�ɂ͋ߊ��ȁA��҂ɂ�����Ȃ牀���̌S���a�@�ւ������Ƃ���A�킩�����Ȃ��v
�@�Z���͂��������Ė���̟��ꂽ�����݂̒����ЂƂ����T��A�����ݒ��q���������܂ܐȂ𗧂��A�ӂ����єw���ނ����ӂɗ������B
�@���̓����ی�ɂȂ�Ƒ��X�Ɩ���͊w�Z�����Ƃɂ����B�������؏W���Ƃ͔��̓a�c�w�ɂނ��āA�D���グ������̖h�Ђ����Đl�ڂ��͂���Ȃ���}�����B�Z������͂��������n���ꂽ���̂́A�q���q�►�̗��q�̂��Ƃ��v���ƁA����͂ǂ����Ă������Ă������Ƃ͂ł����A�l�q�����ł����ɂ������Ƃɂ����̂������B
�@�a�c�w�̏���M���������Ă���Ƃ���ʼnE�ɐ܂�ċ���n��ƁA��������ܕS���[�g������c����ɂ����ď��X�X���������ԁB�����̑�ŏĂ����������Ƃ͐V�������ĕς���Ă��āA����ɂ͂��̂Ԃ�X�̕��͋C�����ƂȂ��悻�悻�����Ȃ����悤�Ɏv�����B�s����ɏ��Ȉ�@�̌������݂��Ă���ƁA���̂܂ܕ\���炢���������̂��A�q���q�ɂ�������܂��ǂ�Ȍ��t�������悤���A�ȂǂƎv�Ă����Ă����^�т��݂��Ȃ�B
�u�v���搶��Ȃ��ł������v
�@�Ăю~�߂��ĐU������ƁA�r�����̓X�悩��a�q�̕�e���菵�������Ă���B���オ�T�֊���Ă����ƁA����͉䂪�q�����b�ɂȂ��Ă������q�ׂ����ƁA���Ȉ�@�ւ����̂��A�Ɛu�˂��B�������Ɠ�����ƁA�Ƃ�ł��Ȃ��Ƃ���������āA�s���Ă͂�����ƌ����B���Ȉ�@�̏����܂ł�������}�������āA�����ӂ��ƋA���Ă������炵���B
�u���������̃A�J�̎���̂ƁA�悤���̐l�����������Ă���͂��āA���炢���Ƃǂ���B�Ȃ��ɂ͐𓊂������肷��l�������āA�\�̃K���X�˂��f�@���̑��K���X���݂Ȋ����Ă܂���v
�u����ȍ������Ƃ��c�c�v
�u�킽���͉@���搶�̂��l�����炵�āA���Ȃ��Ȗڂɑ���Ȃ�����قǁA�������ƌ���͂����Ǝv�킵�܂ւ�B���ǒN�ǂ��x�@�ɍ����ɂ����͂�����ǂ��Ȃ��v
�u�����b�ɂȂ��Ă���@���搶���A�킴�킴�ʕɂ����l������Ȃ�āc�c�v
�u�����Ȃ������h���c�̎����ɍڂ��Ă��܂������A�܂��ɔ��I�Ȍ�����������̂�������ʕ�悤�ɂƁA����ɂ��̓��͑ҍ������A����ǂ��������܂��łȂ��c�c�v
�@�X�̑O��j���ʂ肪����A������ɂނ����ڂ̉s���ɘa�q�̕�e�͍Q�ĂČ��B���̂��Ɩ���Ɂu�������A��ɂȂ���������낵�����v�ƌ����A�����ɋ�����悤�ɓX�̉��ֈ�������ł��܂����B
�@���ǂ̂Ƃ���A����͏��Ȉ�@��K�˂邱�Ƃ��A�q���q�ɉ���Ƃ����킸�ɗ������邵���Ȃ������B��@�̑O��ʂ�Ƃ��A�Ȃ��̗l�q���M�������l�̋C�z�͂Ȃ��B�����Ɖ��~�̉��Őg�������A�����Ƒς��Ă���ɈႢ�Ȃ��q���q�►�̗��q�̂��Ƃ��v���ƁA����̋��͂����悤�̂Ȃ����ӂ̔O�ɂ���ꂽ�B
�@���k�̕�e�̌������Ƃ���ɁA����ꂽ�K���X�˂̔j�Ђ��܂��U������܂܂ŁA�ǂɂ͔��⍑���Ƃ��̕��������n�ʼn��菑������Ă����B����͏��Ȉ�@�̂܂���ʂ�߂���ƁA�������瓦���悤�ɑ��𑬂߂��B
�@�w�O�̏W�����͂邩�ɉ�������Ɣn�ԓ����O��ēc����ɉ˂��钾������n��ΐl�a�蓻�̓o����͂������B�₪�Đ�̋G�߂�����A���̓����͏t�܂Ől���t���Ȃ��Ȃ�B�����t�ɖ��܂�}����M�\�˂̂Ƃ���܂œo���Ă��āA����͗����~�܂��Ĉꑧ�����B
�@����̏o�����͂��ׂĂ������̐ӔC���A����Ȏv��������ɒ��߂Ă����܂ŕ����Ă����B�����̂��܂�Ɍy���ȍs���ɂ��A�@���搶���肩���̉Ƒ��܂ł�s�K�̂ǂ��ɓ˂����Ƃ��Ă��܂����̂��B���̂Ƃ��A�����Ɏc�炸�������J����ƂɎQ�����Ă���A���k�ɉ���Ȃǂ����Ȃ����������m��Ȃ��B����̂��Ƃ�u�˂ɁA���Ƃ�����Ȉ�@�ւ��������肵�Ă��Ȃ�������A�������Ȃ��������낤�Ɂc�c�B
�@���ɂ͐��k�������鎑�i�͂��납�A�l�̍K���ȉƒ�܂ł�D������Ă��܂����̂��B
�@�M�\�˂̂܂����琔���R�̕��ɕ��݊���đ����������낹�A�͂邩�����Ɋ�̊Ԃ�D���Đ����������������Ă���B���ʂ̏��Ȃ����̎����ɂ́A���̊�₪�����藧���i�́A����ɂ݂�n���E���v�킹�Ďv�킸�g��␂ށB��u��ῂ����đ̂��܂��ɂ̂߂肩�����Ƃ��A�ݎ�����܂�Ă����ƈ����߂��ꂽ�B
�u�o�M�̂ǂ������v
�@���B����吺�ɉ�ɖ߂��ĐU��Ԃ�A�����ɐl�e�͂Ȃ��B���܂̐��͎O�Y�́A���₽�����ɎO�Y�̐��������A�悤�Ɏv�����B�M�\�˂̂����肩�炩�A���������Ɛ���̂悤�ɗ����t�������N�k�M�̑�̂����肩�炩�B�ڂ𑖂点�Č��邪�l�̋C�z�ȂǂȂ��A�X�̎}��点�ēn�镗�̉����肾�B
�@�\�z�����Ȃ������ɋC����������ł��܂��Ă����Ƃ͉]���A����Ȏ�C�ɂȂ��Ȃ�āA�ǂ������Ƃ�����B�����ƎO�Y���A�z�Ȃ��Ƃ�����ȂƎ���ɂ�������B����͎����Ɍ����������Ȃ���A�ڂ�X�̉��Ɍ�����ƁA�ؗ��̍��Ԃ�D���Ĕ����e�������B�ꂵ�ċ삯�Ă����B����̓M���c�c���苎�锒���e��ڂŒǂ��āA����͂��܂ł������������B
�@�����x�@���ɍS������Ă������Ȍ[���Y���A��ꃖ���o���Ďߕ����ꂽ���Ƃ��A����͗Ƃ̖F�����畷�����ꂽ�B�F���͔��T�̎g���Ŗ��d�Ȃǂ��A�l�ڂ�����ĉ^��ł����̂��B
�u����ۂǂ�����蒲�ׂ����ǂ������Ȃ��A���Ȃ��ȗ��h�ȕ����璆�����{���炯�ɂȂ��Ă��A��ǂ����B����ŕ\�̗��������݂āA�h��ɂ�肨��̂��A�Ə��Ă����₵���Ƃ��B�̂̐���������l�ǂ��Ȃ��v
�@�F���͂��������u���̂��т͑剜���܂̂��S�����ɁA�@���搶�������܂��A�ǂ��낤���ӂ���Ă�������v�ƕt���������B����ǂ̌��Ŕ��T�͖���ɂ͉�����炸�A���Ȃ̉Ƃɑ��ĖF���ɋC�����̕i����͂������Ă����Ȃǂƒm��A�����������̏����Ɩ���͖��Ȋ��S�������̂������B
�@�[���Y�ߕ��̒m�点�ɖ���́A�Z���⍕��ɂ͓����ŏ��ȉƂ�K�ꂽ�B�q���q�ւ͎�y�Y�ɁA��c���������Ďg��Ȃ��ł������ϐ��́A�ւ��܃R���������Q�����B
�@���������ƖK�ꂽ����̊���݂āA�[���Y�́u���C�ł���Ƃ������v�Ƌt�ɖ₢������̂������B
�u�搶�A���̂��т͎��̌y���������l�тɎQ��܂����c�c�v
�u�Ȃ��ɁA���ꂵ���̂��ƁA�b�����Y���܂��|�������̐܂�ɂ́A�����˂̉��������ɉ��x���߂���Ȃ������B����Ƃ��͍Ȏq����Ƃ̎q�Y�}�܂ł����������āA���~���ɂ���͔̂n�Ǝ������݂̂�������Ƃ��A����Ȃ��̂ő����ł��Ă͉b�����Y���܂����ǂ�Q������ȁv
�@�[���Y�͂��������č����ɏ����B���ꂪ��������S�����邽�߂̂��̂ł���ƕ������Ă��Ă��A����͋C�������v���������B
�@���a�\��N�̔N�������ĎO�w�����n�܂�ƁA�Z�ɗ��R�̊J����Ƃ͐ϐ�𗝗R�ɏt�ɂȂ�܂ňꎞ���f���ꂽ�B�����ɍ����Ȑ��͋ߋ��ɓ_�݂���}���K���z�R�ցA�j�q�͑I�z��z���J�}�X�ɋl�߂��ƂɁA���q�͑I�z�ƃJ�}�X��҂ލ�Ƃ̕⏕�ɓ������ꂽ�B����Ŗ���̎��O�N���Ȃǒ�w�N�́A�z�Δ����̋��ԁi�Ƃ����Ă��唪�Ԃ����Ɉ������j�̂��߂ɓ��H�̐Ⴉ����Ƃ�A�⓹�ł̋��Ԃ̌㉟���ɓ�������邱�ƂƂȂ�A�������ΘJ��d���ƂȂ��Ė���̊뜜�͌����ƂȂ����B
�@�ɂȂ�Ɛ��{�́u�����w�Z�ߓ��펞����v�����z���A�`������N��\��Ɉ���������ꂽ�B�����Ȃ�Ƃ܂��܂��A����ɕK�v�Ȍv�Z�╶������C�����Ȃ��܂܂ɁA�Љ�֏o�Ă������k���������m��Ȃ��B�������A�w�Z�ɔF�߂��Ȃ����Ƃ��K������A�w�Z�̕��j�ɋt�炤�ƌ�������߂��邱�ƂɂȂ�A����͑傢�ɔY�B�������t�ɑ��k�����������Ă��A���Ȃ��͑�p�����Ȃ���A�����܂ōl���鎖�͂Ȃ��A�Ƃɂׂ��Ȃ������B
�@�������߂�����́A��K��K�v�Ƃ��鐶�k�����ɖ����\�������o�Z����悤�ɌĂт������B�����L���̖ڂ𓐂݂Ȃ���A�J����d�ɐ��k�𑗂�o���܂��́A�͂��Ȏ��ԂɎ��Ƃ���낤�Ǝ��݂��̂��B���ɂ���Ė��������̏�������A�|���Z�̋����o�������Ă��Ȃ��҂ɂ́A���炷��ƑS��������܂ʼn��x�����킹���B����ɂ͊���Z�Ȃǂ̖������₩���ʔłō����Ă����Ă�点���肵���B
�@���̂܂܂ł����ƌܔN���ɂȂ����ɕ�d�����������āA�����ł̎��Ƃ��قƂ�Ǐo���Ȃ������m��Ȃ��B�o������Ȃ��܂܂Ői���������k�́A�����Ǝ��c���ꂽ�܂܂ɂȂ��Ă��܂��B���ꂾ���͉��Ƃ��Ă������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�Ƃ����v������������������s���ɋ�藧�Ă��B
�@�Ƃ��낪�\�����߂�������A�����̂悤�ɏ\�������o�Z�𑣂������k�����ŕ�K�����Ă����Ƃ���A�����Ȃ�퓬�X�������L���������Ă����B����܂łɂ��L���́A��������イ�w�Z�Ɋ���o���Ă������A�O�w���ɂȂ��Ă���͍Z�ɓ����䂪���̊��舕�����悤�ɂȂ��Ă����B
�u�����A���܂��A�����ʼn������Ƃ���v
�@�j�͂����Ƌ��d�ɗ�����ɋߊ��A�ɂݐ�����Ɣ��Γ{��悤�Ɍ������B
�u�͂��A�����͊w�Z�ł�����A���Ƃ����Ă���܂��v
�@����͌����Ԃ��Ȃ���A����̊���݂߂��B�L���͉����������������A���̐����`���Ŗ�����ɂݕt����������点�ċ�������o�Ă������B�L�����h���h���Ɠ��ݖ炷������������A����͂ق��Ƃ��Ȃ�����A�L���̉����ȑԓx�ɋB�R�Ƃ��ĉ�����ꂽ���Ƃ������ł��ӊO�Ɏv�����B
�@���炭�����ē���ւ��ɍ��삪����Ă����B
�u�܂�����Ȃ��Ƃ�����Ă���̂��A�����l���Ă����ł��v
�@����͋����ɓ���Ȃ�A����Ɍ������ęႦ���B
�u�����搶���肢���܂��B���Ə\���A������T�Ԃ̂������ڂ��ނ��Ă��������܂��B����������̎q���������ꂼ��s����ȋ��Ȃ����Ƃ�������������Ǝv���܂��v
�u����nj�������킩��̂��Ȃ��A��X�͂��ɂ���Ȏ��𗊂�ł��Ȃ��B�搶�������͑�T�ɂ��Ă����ȁA�Z�����l���g���ׂ�v�����v
�u�搶���������Ȃ�āA����܂�ł��c�c�A���玄�͎t�͊w�Z���o���킯�ł͂Ȃ����A������Ƃ͕�����܂���B�ł��A���߂đS�����|���Z�̋��⊄��Z�̊�b���o���Đi������悤�ɂƁA���ꂪ��p�����Ƃ��Ă̎����A����t���̎q��ɂ��Ă��邱�Ƃ��Ǝv���Ă��܂��B���ꂪ�搶�����������Ă���Ƃ���������ł����v
�@�����������ƌ��ɂ����Ƃ��A�t�ɖ���_�ɋ�藧�Ă��B
�u�������Ă���Ԃɂ��A��n�ł͌������퓬���s���Ă���B�����ł����A���̐���������������߂ɉ�X��l��l�����̊��𗬂��˂Ȃ�Ȃ����ɁA����ȗ����͂�����낵���B����Ƃ����コ��A���v���̉Ɩ�����Ă�肳��ĉ������肩�v
�u����Ȃ�āA����ȁc�c�v
�u���̔�펞�ɁA���ł������i���ςׂ݉𑝂₵�Ċ撣���Ă���B�킩������A�����ɐ��k���d�����ɎQ���������ł��ȁv
�@����̌�����o�����Ƃ������t�ɋ�����́A�������������Ă����ʂȂƒ��߂邵���Ȃ������B
�@���Ԃ̌㉟���ɂ́A�O�N���ȏ�Z�N���܂ł̒j�q���k�������������ꂽ�B���Ԃ͉��䂩���A�Ȃ��ė��邱�Ƃ�����A�ԍ����������Ă���ė��邱�Ƃ�����B���̋��Ԃ��O�l���㉟������̂����A�l�N���͊w�Z�̂܂�����a�c�w�̉ݕ��W��܂œ�L���]��̓��̂��S�����邱�ƂɂȂ����B�����͒Z�������̊Ԃ͉I�Ȃ������A��x�������z���˂Ȃ�Ȃ������ɁA���H���z��̏�ɕ~����Ă��邽�߂ɓ������z�̒��_�ɂȂ�B�ʏ�̐ςׂ݉ł��A���͟��𐂂炵�Ȃ��瑧���r�����ł��������B
�@���R�ɂ��ĐϐႪ����ΐႩ����Ƃ���s���čs���A�Ȃ��ɂ͒��߂�G�点�ė₽���ɔ��ׂ��������Ă���q�������B����ɂ߂�����͗p�������֘A��Ă����A��Δ��ňߕ����������g���Ƃ点���肵���B�������^�����L���ȂǂɌ�����u���܂��̂悤�Ȃ̂�����������ɂ���̂��v�Ɠ{�肠������n���������B
�@����̏��q���k��́A�u���̋��ɐw����āA���C��҂ލ�ƂɎ��g�B�S�����C�Ȃǂ𗚂��Ă��鐶�k�͐�����قǂ����Ȃ��āA�قƂ�ǂ̐��k���m�C����������A���Ԃ̌㉟�����n�߂Ă���Ƃ������̂͘m�C�͂����炠���Ă�����Ȃ����炢�������B������������̂Ȃ��Řm�C��҂ނ̂��K�n�����҂����Ȃ��̂ŁA���̎�w�炪���ŕ҂ݕ��̎w���ɂ���Ă����B
�@�F���̏��[�R�g���������Ă���Ă��āA��e�ɋ�������m�������炢�Ȃ牽�Ƃ��҂ނ��Ƃ��ł��邪�A�Ƙb������Ɂu�킵��݂����ȂA�w�Z�ւ��̂������ɂ���āA�����p���������킢�Ȃ��v�Ƒ傢�ɏƂ��̂������B
�@�l���ɂȂ�V�w�����n�܂�ƁA����͂��̂܂܌ܔN���̒S�C�Ɏ����オ��ƂȂ�A�����ɍ����Ȃ̏��q�ٖ̍D��S�����邱�ƂƂȂ����B���͂⍑���w�Z�ɂ����鋳���s���́A���������w�Z�����̖��ł͂Ȃ������B
�@���オ�������͎̂L���������Ƃ��āA�䂪���̊�Ŋw�Z�ɏo���肵�n�߂����Ƃ������B
�u���̍z�R�ł͔я�̘d����T���Ƃ�A���܂��Ȃ玗�������B�ǂ����A�������v
�@�L���͖���Ɗ����킹�邽�тɁA���̂悤�Ȍ����������Ă͑�ɏ����B�Z���͎L���̑��X�����ԓx�ɂ����ٔF���A����ɂ������Ă̓y�R�y�R�Ƃ���l���T�ڂɂ����ꂵ���āA����珗���������̕�����̂点�Ă����B
�@�܌��Ȃ��ɂȂ�������ΘJ��d���̒��A�ꎞ���ڂ���j�q���k�͎L���̎w���̂��Ƌ��Ԃ̌㉟���ɂ����A����͎O�N���ȏ�̏��q���k�����ƂƂ��ɍZ�ɗ��̊J�����ɂ����B�����̌v��̔��������J���ł��Ȃ������X�Βn�̔��ɂ́A����ł��挎�Ɏ펪���������q�}����̉���o���Ă����B���Ӗ��Ƃ��Ă��q�}�́A���Ƃ��Ɠ��n�ɂȂ��������̂ł���A�����ɂ��͔|�o���҂����炸�����͍Z���̗��݂ŗג��̔_�ъw�Z����w���ɂ��Ă�������肵���B
�@�w�N���Ƃɋ敪�������ꂽ���̐��ɉ����āA���k�����ɍ������ĎG���������Ă����Ƃ��������B�p����������点�āA�X�Βn�̔��̍��Ԃ��삯����Ă����B
�u�v���搶�A���߂̖�c�Ƃ����邨������d�b���������Ă���܂��ŁA���������Ă�����₷�ȁv
�@���������I���Ȃ�A���Â������r�����̏�ɂւ��荞��ł��܂����p�����ɗ�������A����͐��ݕt���ʂ悤�ɑ����ɋC��z��Ȃ���A�}�Ζʂ̔��̊Ԃ��Z�ɂւƋ}�����B
�@�}�ɂ܂������Ȃ̂��A�����͏o���̋A��ɗ���������̂��B��c�����̂���Ȏ��Ԃɓd�b�������Ă���̂͏��߂ĂŁA����͂��ꂱ��v�����߂��点���B�d�b�@���ݒu���Ă���Z�����̑O�܂ł���ƁA�Ȃ��ŎL���̘b�����������B���ȃ��c������ƈ�u�S�O�������A��c���d�b���Ŗ��オ�o��̂�҂��Ă���Ǝv���ƈӂ������Č˂��J�����B
�@�����Ɋ���ނ����Z���ƎL���ɁA����͏����Ȑ��Łu���݂܂���v�ƒf��A�ǂ̓d�b�@�̖T�ւ�����b����Ƃ��Ď��ɂ��Ă��B
�@��c�͖���̐����ƁA���܂��炷���ɕ��߂ւ��Ă���A�Ɩ���̓s���Ȃǖ����������悤�Ɍ������B��c�̘b�ł́A�_����ʏ㗤�����o�Ė�c�̂Ƃ���ւ����Ă���炵���B�_��Ȃ�A����܂ł̂悤�ɁA���Ɏ��Ƃ֖߂��Ă������ɂ䂭����A�ƌ����Ƃ���ł͑ʖڂ��A�_��N�͋A�͂���܂ł̎��Ԃ��Ȃ�����A���܂��痈�ė~�����A�Ƃ����B�ǂ����Ă����������Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��Ɛu�˂�ƁA���Ȃ�������ƌ�����邱�ƂɂȂ�ƌ������B
�@�Ȃɂ���c�̘b���Ԃ�ɐؔ����������āA�ꉞ���ނ̋����肤�Ă݂܂��Ɠ������B��c�́u�K�����Ă��������B�����Ƃł���v�ƔO���������ēd�b������B
�@��b��������ĐU������ƁA�d�b�ł̉�b���Ă����炵���Z���ƎL����������݂߂Ă���B����͍Z���ɖ�c����̘b�������܂�Řb���āA���������ɑ��ނ̋���\���o���B
�u�Z���A�����������ƂȂ狖���o���Ă��ׂ��ł��ȁv
�@�ӊO�Ȃ��ƂɁA�Z������ɎL���������Ђ炢���B
�u��N�����悢��䍑�ɕ������Ƃ��������킯���A�s���ĐS�����Ȃ�����Ă���ȁv
�u���́A����͂ǂ��������Ƃł��̂�납�v
�u���͗��R������ȁA�C�R�̂��Ƃ͏ڂ����͂Ȃ����A���ʏ㗤�����o��̂͂��悢���n�ւނ������炾�B�Z���ԂȂً̂͋}�o���Ȃ̂��낤�v
�@���̎q���A�_���n�ւ����A����ƍZ���Ɍ��݂Ɏ������ނ��Ȃ���b���L���̘b�ɁA����͌��t���������悤�ɖ����ŗ��������B
�u���������A���コ��A���܂��畑�߂֍s���Ȃ����B�ؕ����Ă����悤�ɂ킵����w�ɗ���ł����v
�@�ŋ߂̗��s�����ŁA�ؕ����Ă���Ȃ����Ƃ�����ƕ����Ă͂������A�L���̘b�ɍZ���͂���ȋC�z��܂ł����Ă��ꂽ�B
�u�����A��N�̂��Ƃ͑��ł͐�ɒ���ȁA�ǂ��ɒ����邩�킩���̂��v
�@����q�ׂĕ�������o�Ă������Ƃ������ɁA�L���͌����������Ō����Y�����B
�@����̏�����D�Ԃ́A�V���߂̉w�ɐ��ߑO�ɒ������B�D�Ԃ���~��āA���D���̌������Ŏ���ӂ��c�̊���݂��Ƃ��͐��������Ăق��Ƃ����C�����������B��c�͓d�b�������Ă���A����Ȃ炫���Ƃ��̋D�Ԃł��邾�낤�ƁA�\�������Č}���ɂ����A�ƌ����Ĕ��B
�u���́A��������ǂ����Ė�c����̂Ƃ���ւ��������ƁA�Ă��Ă���܂����v
�@��c�ɘb�������Ă���ƁA�����Ȃ��납���ŖډB��������Ė���͈�u�����łȂ��B
�u�n�n�n�A�o�����b���Ԃ��Ȃ��v
�@��𗣂���ĐU������ƁA�����ɍ_��̏��炪�������B
�u�_����A�����A�ӂ����Ă���ɂ��A���A������ƌ������ɔw���L�т��Ȃ��A����肾���Ԃ��Ȃ��Ă��Ȃ��́v
�@����͖ڂ̂܂��ɗ��������̍_����A������Ƌ��������߂Č��߂��B
�@��c�͓�l���w����o�X�ɏ悹�A���͂���̒◯���ʼn��肽�B�\�ʂ肩����ė����֓������Ƃ���́A��K���Ă̂��������Ɉē����āA���̉Ƃ̓�K���c�͉��h�����Ă���Ƃ������B�_��͉��x���K�₵�Ă���悤�ŁA���|�����ʗl�q�Ō��ւ�����Ă����B
�@���B���ʼn��ɂł����V�̕w�l�́A��i�Ȋ����������B���Ζʂ̖�����݂�ƈ��z�ǂ��}������A��c�ɕ����ɓ痿���̏������ł��Ă���ƌ������B���Ƃ��畷������c�̘b�ł́A�Ǝ�ł��邱�̕w�l�́A�E�ƌR�l�������v�B���ςŖS������Ă���́A��l�ł��̉Ƃ�����Ă�����̂��������B
�u������ʂɈ�̔z�����������̂ŁA������ɗ���ň�c�q������Ă�������B�܁A���������킯�ŁA�����̂�����ɏ�����𗊂�ł������Ƃ����킯���v
�@����ԑ�̐^�ɒu�������ւ̂����ɂ�����ꂽ�y��ɖ���ς��Ă��āA��c�͍ؔ��ł܂�M�̈�c�q����荞�݁u�����Ȃ����ǁA�܂�����Ă���������v�Ɩ���ƍ_��ɍ���悤�Ɋ��߂�B���炭���āA�ǂ������ɓ��ꂽ�̂����̌܍��r���܂Ŏ����o���Ă����B���オ��芷���̈����w�ŁA��������齂��Ă���̂����Ĕ����Ă����̂����o���ƁA��l�́u�������v�Ɛ��𑵂��ċ����Ă݂����B
�u��c����ƈ�x�A�c����ň��ނ���������������Ȃ��v
�@�Ĕт̑���ɁA������̏�Ɉ����̂���齂����։^�тȂ���A�_��Ȃ������݂��݂Ƃ��������Ō����B
�u�s�����A�����ƍs�����A�����Ă������A�l�̏����͂킩���Ă�����ǂȁv
�u�o����������A���̎��M�ߏ肳���Ȃ�������A��c����͐l���I�ɕ���Ȃ��̂Ɂv
�@�^�ʖڂ���������Řb���_��ɁA����Ɩ�c�͊�������킹�Ĕ����A�_������ď��̂Ȃ��ɓ������B�K������w�l�̐������āA��c���Ԏ���Ԃ��Ɖ����Ă�ł���ӂ����B�u�����s���v�ƍ_��g�y�ɍ��𗧂��āA�Ƃ�Ƃ�ƊK�i�݂Ȃ炵�ĉ���Ă������B
�u���́A�_��͐�n�ւ����̂ł����B���ʏ㗤���Ƃ����̂͂��̑O�Ԃꂾ�ƕ������̂ł����v
�u�ܓ�����܂��ɁA�_���Ɛ����̂��߂ɍ_��N�̏�͂��h�b�N���肵���̂ł��B���̏ꍇ�͒ʏ�̓_���ł͂Ȃ��������̂ł�����A�O�q�֏o�Ă����̂��ƒ������܂����v
�@�_����𗧂��������݂āA�����ւ���܂ł����ƕ����Ă����v����₢���������ɁA��c�͌��t��I�тȂ���W�X�Ƙb���B
�u���������_��N�̏㗤��m��A���������m�ŁA���Ă�������킯�ł����c�c�v
�@�ĂъK�i�݂Ȃ点�č_��߂��Ă����B
�u�����A�킴�킴���ǂ�������炦�Ă��ꂽ�A�����͎|�������Ȃ��A�����̓o���o���H�����v
�@�_��͎�Ɏ������唫�ɐ��������ǂ���A���������y��ɓ���n�߂��B���̎q�����炢�̊Ԃɂ��A��l�тāc�c�A�C�R�a�肪�����ɂ��A�����ς��ɒj�̕��͋C����킹��_����A����͎�ɂ��锢���~�߂Č�����B
�u���ꂿ���ɂ��A����Ă��悩�����̂Ɂc�c�v
�u��ނ������A�����㗤������ȁA�D�Ԃ̉����ɎO���Ԃ������邵�A�w�ɒ����Ă��瑐���܂œ����z���A�����ŕ����Ă��l�\�����B�������l���Ԃ̊O�o�ł͂ƂĂ�����Ȃ���v
�u�_��߂�����ڂ��݂������Ă��˂ƁA���ꂿ�������ʂɍ���Ă����݂������v
�u�ڂ��݂��A���ӂ���̍�����ڂ��݂͓V����i������ȁv
�@�܂��A���ӂ��낾�Ȃ�āA��e�������炳�������Ƃ��ɈႢ�Ȃ��ƁA����͂܂����_�������B
�u�o�����A���݂�������ǂȁc�c�A����ς��߂Ƃ����c�c�v
�u�Ȃ��́A���������āc�c�������Ȏq��Ȃ��A�v
�u�_��N�A���̍ۂ��A���ƂŐS�c��ɂȂ��悤�Ɍ����Ƃ��������������v
�@����܂Ŗق��Ďo��̉�b���Ă�����c���A���Ȃ���_��������������B
�u�o�����A�ق�܂ɓ{��ւv
�u�Ȃ�Ŏ����{��Ȃ�����́A�j�炵���͂����茾������ǂ��Ȃ�v
�u�o�����A�I�b�p�C�������Ă���ւv
�u�����c�c�v
�@���̎q������A�����Ȃ�Ȃɂ������o���̂�A����͕Ԏ��ɋ����Ă�����̊�����Ԃ������Ȃ��B
�u���̂���A�Ȃ�△���ɂ��ӂ���̃I�b�p�C���v���̂�A�O���Ԃ�V�̂���ɁA���ӂ��낪�I�b�p�C�����܂��Ă���̂��݂āA�������̃I�b�p�C������Ԃ������Ȃ��Ǝv�������Ƃ����������ǁA���܂܂����Ɏv�����B�o�����̃I�b�p�C�Ȃ�A���ӂ���̃I�b�p�C�ƈꏏ��Ǝv�����ǁA����ς肠�����Ȃ��c�c�v
�@�_��̐^���Ȋ፷���ɁA����͌˘f���Ȃ�����ނ̊肢������A��X�̐S�c��ɂȂ邩������Ȃ��Ƃ����C�������B�T�ł��̗l�q���݂Ă�����c���A�Â��ɍ��𗧂���������o�čs�����B���̔w�����K���ɏ������Ƃ��A����͂���̏�ɒ��������̋��𗼎�ŊJ�����B
�@��l�̎q�����Y�Ƃ͂����A�܂��܂��e�݂̂�����[�������炱�ڂ�ł��B
�u�o�����c�c�����̂��c�c�v
�@�o��Ƃ͂����n�߂Ă݂������̓��[���Aῂ������Ɍ������Ă����_��͂����ƕ@�����[�ɋ߂Â���B
�u����������A���ӂ���̓����������A�o�����A������ƐG���Ă��������v
�@���オ�����ƁA�_��͋��鋰��E�����[�ɋ߂Â��A�G�ꂽ�r�[�ɓd�C�ɂł����Ă�ꂽ�悤�Ɏ���������߂��B�u�����ƐG��v����ɑ�����č���x�_��̎肪���[�ɐG���B
�u�����āA�����Ă̖݂݂����ɏ_�炩����B����A���ӂ��덡�N�̖݂��ǂȂ�������A���N�͉����x�ɂŋA���Ă������ǁA�e���͂��̒ʂ肨�o�����鑼�͉�������l�Ԃ�A�O�ł͂܂������₵�Ȃ��c�c�v
�@�A�z�A���̎q�͉��������Ă�̂�B�ِ��ɑz���������邱�Ƃ��A���̔���m�邱�Ƃ��Ȃ��A��n�ւ����킪����ɂ͕s���������B����͂Ƃ����ɍ_��̓��𗼎�ŕ����A�����̓��[�ɉ������Ă��B
�u�_��A���ꂿ���̃I�b�p�C��A�z���v
�@�����Ȃ�����[�ɉ��������A�_��͖ʐH�炢�Ȃ������������Ɋ܂ށB
�u�o�����L���A�I�b�p�C�̖��āA����ς肦�������Ȃ��v
�@���Ɋ܂���𗣂����_��́A����g�������ęꂭ�B����ȍ_��̊���A����͂����Е��̓��[�Ɉ���������܂܂����B
�u�������̃I�b�p�C���z���A���ꂿ���̃I�b�p�C��v���Ă����ς��z���v
�@�����Е��̓�����܂܂�������́A�����z�������ɓ݂��ɂ݂������Ȃ���_��̓��ł邤���A�o�Ƃ��ĉ������Ă��Ȃ����Ƃ������ɔ߂��������B�������܂ꂸ�ɁA�ӂ����э_��̖V�哪������������A���[�ɋ������������B
�u�_��K���҂��Ă����ł�A�҂��Ă��Ȃ�A�˂�����m�����ւ�Łv
�@���[�ɉ������Ă��đ����ǂ��ꂽ�_��u�킩�����A�킩������o�����v�Ɗ���˂���Ȃ��猜���ɓ����Ă����B
�@�_��Ƃ̎��Ԃ́A�A�b�Ƃ����Ԃɉ߂��Ă������B����͖�c�ƂƂ��ɁA�A������_����c��̂܂��܂Ō��������B�ʂ�ۂɍ_��͖�c�ɐ[�X�Ɠ��������āA����܂Ő��b�ɂȂ�������q�ׂ����Ɓu�ӂ��Ȏo�ł������肢���܂��v�ƌ����āA���ڂŖ���𓐂��ăj�����Ƃ����B
�u�܂��A�_����v���̎q�͉������������́u���݂܂���A����Ȃ��Ƃ��v�˘f���Ȃ���l�т������c�͏��Ď����B
�u�o�����A�e���Ƃ��ӂ���𗊂ނ�ȁv
�@�_��}�ɖ���Ɍ�������A�^�ʖڂȊ�ɂȂ��Č������B
�u�{�E�Y�����ӂ��������ɔC���Ă�����ƁA��ɍs���Ă���A��e�����Ă��ȉ��z��v
�u�_��A���܂��ɂ���Ȃ��ƐS�z����āA�����l���Ă����v
�@���o�팖�܂̌����ɂȂ�̂��v���U��Ȃ���A�_��A��Ɏ��ʂȁA�����Ċ҂��Ă����ł�A����͌��ɂ͂����Ȃ����t���A���̓��ʼn��x������ł����B
�@�_��͖�c�Ɩ���ɉE����������Čh������A���̂܂܉c��Ɍ������ĕ����Ă������B�q���ɒ����Ōh�������ƁA�_��͂��̂܂ܐU��Ԃ邱�Ƃ��Ȃ������Ă����A�₪�ĉ��l���̐������ɍ������Č����̉A�ɉB��Ă��܂����B
�u�l�̂Ƃ���֗���ƁA�悭�b�ꂿ���̂��Ƃ������Ă����Ȃ��B����ō_��N�͂Ȃ��Ȃ��D��������v
�@��c�͐V���߉w�܂Ŗ���𑗂��Ă���铹������A���オ���Ƃ̕�e�̂��Ƃɗa���Ă���b����A�_��C�ɂ����Ă����Ƙb�����B
�@�_��펀�̌������炳�ꂽ�̂́A�Ă��I���ɋ߂�᱗��~��̓��̌ߌゾ�����B���Ƃ���̓d��Œ�̐펀��m��������́A�Q�����������̓��̗[���̋D�Ԃɏ����Ƃɂނ������B
�@�w���瑐���̏W�����߂����ē����z���鍠�ɂ́A���łɗ[�ł������Ă����B���������������̂悤�Ɉ�l�œ����}���ł���Ƃ��������A��납��_����]�Ԃł���Ă��āA��я��ƌ�������A�ǂ������Ĕ�я�������̂́A��я�肻���˂ē�l�Ƃ��h��ɓ]��œ��̐^�Ō��܂ɂȂ������Ƃ������B���傤�Ǔ����Ȃ����Ă���A���̂����肾�����B�d���������Ƃ��ɂ́A�Ȃ����܂����ڂ��Ȃ������̂ɁA�_��Ƃ̂��܂��܂Ȃ��Ƃ��v���o����āA�����Ȃ������͖j��`���܂��ʂ������Ƃ����Ȃ������B
�@�ˑR�Ɍ��������ݏグ�A����͂��̏�ɂ��Ⴊ�������j���B�ӂƊ��������ƑO���ɔ����e������B�܂ł����ޖڂ��n���J�`�Ő@���A�悭�݂�Ɣ����e�͎O���[�g�������ɂ��āA����������Ƃ݂߂Ă���B�M���c�c���͓�l�̒�������Ă��܂������B���܂����Z�����������߂��݂͂悤�킩��͂��B���͂��̔߂��݂��ǂ�������悢�̂��A�M���c�c�����Ă�����c�c�B
�@����̑i���ɁA�����e�͂����Ƃ���������߂Ă������A���̂����T�b�Ɣ����������������Ǝv���ƁA�����J��ڎw���ĕ����n�߂��B�M���҂��āc�c�B�Ăт����ɐU��Ԃ�A���オ�����オ���Ă��邫�o���ƁA�ӂ����юO���[�g������̋������Ƃ��Đ�������B
�@���Ƃɖ߂�Ƒ��V�̏����ōQ�����������͋C���������A��e�͎O�Y�̂Ƃ��̂悤�ɐQ����ł��܂��Ă͂��Ȃ��������A�⍜�̖T�ɍ��荞��ł����B��̑O�ɂ����ƁA�⍜���҂��Ă���͂����Ƃ������Ă���炵���B
�u�_��͐����͂ŊC�̒�ɒ���ł���Ƃ����ɁA�Ȃ��Ă����ɂ���������̂�v
�@����̊���݂Ă����Ȃ肻�������āA�ӂ����іق荞��ł��܂����B����͍Ւd�̔��̔�����Ɏ��A�����Ɨh�����Ă݂�ƃJ���J���Ə��������������������B
�@�䌴�_��@�֕����A���a�\��N�����\������������m�ɂĐ펀���N�\���A�����Y����ꂽ���Ђ̕��������߁A�����Ŏv���苃�����Ԃ��A�s�v�c�Ɵ��ꂽ�悤�ɗ܂͏o�Ȃ������B
�@�_��̑��V����ꃖ�����܂肪�o�����\���̎n�߁A���������w�Z�ɂ����Ă͋��t�̂������ŁA������Ƃ����������������Ă����B���̔N�̉ĂɎn�܂����s�s������_���ւ̍����w�Z�̊w���a�J���A���悢�悱�̊w�Z�ւ�����Ă���Ƃ����̂��B�Z���͏������߂ĘA���̂悤�ɑ�����֏o�����A�E����c������܂������̂悤�ɂ����ꂽ�B
�@�a�J����������ė���̂͂��Ȃ̂��B�s��̊w�Z�̐��k�ƎR���̊w�Z�̐��k�ƁA���܂��ꏏ�ɂ���Ă�����̂��A�w���͍����ɂ���̂��ʁX�ɂȂ�̂��A�ʂɂ������������Ȃ��B�t���Y���ĕ��C���Ă��鋳���͉�������̂��A�a�J�w�������̏h�ɂ͂ǂ��ɂȂ�̂��A�ȂǂƁA����͊w�Z�����ʂ�������l���邾���ł��������o���B
�@���̓������̐E����c�́A����̎��Ԃ��O�\���߂��Ă��I��낤�Ƃ��Ȃ������B�����͔����Ȃǖő��ɂ��Ȃ��҂܂ł��A�����̍���ɂނ��ĕs���ȋC������^����Ԃ��Ă����B�����̂��ƂȂ���A�ǂ��܂ł����Ă����X����̎���ƁA�Z���⍕��̗v�̂Ȃ��ԓ���焈ՂƂ�������́A���p�̂���U������Ă����ƍ����������B
�@�ꎞ�Ԗڂ��痠�R�̊J�����ɏ��q�̐��k���������Ă��āA����͗l�q�����ɔ��������Ζʂ̓����̂ڂ��Ă������B
�@���̏t�Ɏ���������q�}�́A���k�����̔w��قǂɂ��Ȃ��Ă��āA�e�w�傭�炢�Ȏ��������ɂ��Ă���B���k���������������q�}�ɁA����Ƃ����Ă����Ƃ��Ȃ��A���������ɂЂƂ����܂�ƂȂ��đ��ނ�������Ă����B
�u����Ȏ�����̂������ŁA�ق�܂ɔ�s�@����Ԃ̂�납�v
�@�w��̐��ɐU������ƁA���Ƃ�ǂ��Ă����̂������̂Ȃ��ł͍ł��N���ŌÂ����炢�鏗�������A�܂����q�}�̎�����ŐG��Ȃ���ꂢ�Ă���B�u�搶�c�c�v���k�����ɕ������Ă͂ƋC��z�����ɁA����͋��x�̋ߎ����K�l�z���ɖڋʂ��ނ��Č��������߂��B
�u�v���搶�A�s��ł͋ΘJ��d���邢���Ă��A�R�������c�ނ��Ȃ��Ƃ���ʼn������܂����A�����ł͐��k�͋����ɂ�����J����d�ɓ�������Ă鎞�Ԃ̕��������̂ɁA�s��痈���a�J�w���Ƃł͊w�͂̍����啪����Ǝv���܂��v
�@���オ�ޏ�����A�搶�ƌĂ��͎̂n�߂Ă̂��Ƃ��B��قNjC�������A���h���Ă���ɈႢ�Ȃ������B�����̉�c�ō��삪�A�a�J�w����{�Z�̊w���ɕғ�����ƌ��������Ƃ��A���S���Ă���炵���B
�u���玄���w�͂̍��͂���Ǝv���܂����A�s��ł��Z��₿����Ƃ����n�ɁA��Z�����A���Ă���ƕ����܂����������ɁA�ΘJ��d�������炠��܂����v
�@����͓����Ȃ���A�����ł��[�������������������Ă���Ǝv�����B
�u����ɂ���̂͊w�������Ȃ��A�l��a���R�Ȃ��ƈꏏ�ɂ��Ă���ĕ����܂������ǁA��̂ǂ��Ȃ�܂����납�v
�u�����c�c�v
�@��i�Ɛ����Ђ��߂Ě�����Ă��A����ɂ͕Ԏ��̂��悤���Ȃ��B
�u���̎����A���ꂩ��ǂ����܂��̂��v
�u����������Ǝ����Ă���A���������̂��Ĕ_�w�Z�֎����Ă����ƕ����Ă���܂����ǁv
�@�b���ς�������ɁA����͏����z�b�Ƃ��ē��������A�v���Y�ނ��Ƃ͂��Ȃ��������B
�@�w�Z�W�҂��肩�A�����F���C�𝆂݂ɝ��a�J�w���͏��a��\�N�������Ă�����Ă��Ȃ������B����͎����オ��ŁA�Z�N���̒S�C�ɂȂ��Ă����B
�@�a�J�w���́A�������Ă������悤�ɑ�����J���̎��@���w���̏h�����ɂ��Ă��A����Ȃ�Ɏ��ꏀ���͂Ȃ���Ă͂����̂������B����ȂȂ��A�l���̐V�w�����n�܂�ƁA�����Ȃ̐��k�͏��q���܂߂ēS���ې����e�n�̍H��֘J����d�̓������n�܂����̂��B����������������ւ̕t���Y����A�����Ɋw�Z�𗯎�ɂ��邱�Ƃ������Ȃ�A�ő��܂Ƃ��Ɏ��Ƃ��ł���ł͂Ȃ��Ȃ��Ă����B
�@���R�̊J�����ɂ͍��N���q�}�̎�����������A������̐E����c�ɂ����č��삩��Z��ɒY�Ă��q��݂����Ă��Ȃ��ꂽ�B
�u���łɌ��틳��[�u�v�j�ɂ��A�����w�Z�����ȈȊO�͈�N�Ԃ̊w�ƒ�~�����߂��ꂽ�B�{�Z�ɂ����ẮA����܂łɂ����X�w���̘J����d�������Ȃ��Ă������A��ǂ̏d�傳�ɉ�����ׂ�����Ȃ�J����d�Ɏ��g�݂����v
�@����͂����O�u�������Ă���A�Z��̍L��ɒY�Ă��q�������炦�A���k�ɒY�Ă���������l���ł���ƌ������B�^����ɎL�����^�ӂ�\�����A����Ɂu�٘_�͂Ȃ����v�ƈꓯ���݂킽�����B���̈Ј��I�ȑԓx�ɁA�Z�����ق�����������ŒN���٘_�Ȃnj����镵�͋C�ł͂Ȃ��B
�@��w�N�ɂ����Ă��A���Ƃ��Ă���̂͐V���w�̈�N������O�N���܂łŁA����ȏ�̊w�N�̐��k�����́A�V�w�����n�܂��Ă���́A�قƂ�ǖ������J����d���ƂȂ��Ă����B������Ȃ�ł����Ƃ�������Đ��k�ɒY�Ă���������ȂǁA����ɂ͂���Ȃ��Ƃ��䍑�̂��߂ɕ�d���邱�ƂƂ́A�ǂ����Ă������Ȃ������B���̋��t�����݂͂Ȃ������ł�����ŁA�ًc�⎿��Ȃǂ���l�q���Ȃ��B����͂��ꂾ���͌����Ă����˂ƁA�ӂ������ĐȂ��痧�����B
�u�����搶�A�Y�Ă��͂���Ȃ�̌o��������̂ł͂���܂��B���k�ɒY�Ă���������ȂǁA���ꖳ�����Ǝv���܂��B����łȂ��Ƃ��}���K���z���^�ԋ��Ԃ̌㉟���ŁA���k�����͔��Ă��܂����ǂ���ł͂���܂���v
�u���������Ƃ�̂��A���܂��͂��v
�@����������L����������ɂݕt���ē{��ƁA���삪�Q�Ăč��������ĕ⑫�������B
�u���R�A�Y�Ă��ɂ����ẮA�{�E�̎w�����肤����ł��v
�u�����搶�A���̌����Ă��邱�Ƃ́A�����������ƂƂ͈Ⴂ�܂��v
�u���������ɂ����A����͂��A���̐ӔC��ł�B���܂ł��̏��������Ă����̂��A�������z�R�̔яꏗ�Y�ɂł��Ȃ�v
�@�֎q���R���ė����オ�����L���̌����ɁA���̏����������͎�������߂Đ̂悤�ɐg���났�����Ȃ��B�L���̓x�����\���ɁA�܂����A�Ǝv�����̂����܂܂Ŗق��Ă����Z��������ƌ����Ђ炢���B
�u���ꂼ��ӌ�������Ǝv�����A��ɐ\�����悤�ɁA�w�Z�Ƃ��Ă��푈�����̓��܂ŁA��������z���Ď��g��ł��������v
�@�����ƎL���̊���M���A�Z���͂ӂ����ђ��Ȃ����B����͋�����݂Ԃ����悤�Ȋ�Řr��g�݁A�����ւ̎��ɂނ��܂܂��B
�u�ꉭ�̋ʂɂȂ��ď����ɂނ����ēˌ����Ȃ��Ⴀ�Ȃ�ʎ��ɁA���܂��̌����悤�ɁA�̂�т�Ǝ��Ƃ�����Ă���ꍇ�����v
�@�L���͂Ȃ�������ɓłÂ������A����͔�������߂Ėق��ĕ����Ȃ������Ƃł��̏��ς��邵���Ȃ������B
�@���̐E����c�ł̈ꌏ�́A�����o���Ă��甋�T�̒m��Ƃ���ƂȂ����B�L��������ɑ��Ė\����f�������ƂɁA�v���Ƃ���M�����Ɣ��T�͌��{�����B���T�́u���߂��߂Ɩق��Č����Ă������v�ƁA����ɂ�������U�炵���B
�@���T�͂������ɑ����ƍZ���ɏ��Ȃ𑗂���A�L�������������w�Z����Ǖ�����Ɣ������炵���B�v�����Ă͂��Ă��A���̒n�ɂ����Ă̋v���Ƌ�S�N�ɂ킽��u���̗��j�́A�l�X�̂Ȃ��ɉB�R�Ƃ����e�������������Ă��āA���̌ւ肱�������T�̂��ׂĂł������̂��B
�@�v��ʔ��T�̓{��ɋ��������삪����Ă��āA�����̐ӔC���Ɠy�����������ɂЂꕚ���Ęl�т����ꂽ�B���T���̖ʂ�ۂ����Ǝv�����̂��A���̈ꌏ�͗��������̂������B
�@���̊Ԃɂ�����̒�Ăɂ��Y�Ă��q���A�قƂ�ǔ��ɍk���ꂽ�^����̋͂��Ɏc����Ă����L��ɑ���ꂽ�B�����̒Y�Ă����Ƃɂ��Ă���j���A�q���肩��̎w���ɌĂꂽ�B�u����Ȃ�ŒY���Ă�����납�v�^���悷�鋳�������ɑ�����u�����ȁv�Ǝ���X���Đ��Ԏ���������肾�����B
�@�܌��̏��߂̐E����c�ɂ����āA���̂��ь��z���ꂽ�펞����߂ɂ��čZ�����������Ȃ��ꂽ�B������ċ����̍��삪�����A����ǂ͉����͂��܂�̂��ƕs�����Ȗʎ����̋����������܂��ɘb���n�߂��B
�u��ǂ̏d�傳���ӂ܂��āA�̋ʂƂȂ��Đ��퐋�s�̔C�����܂��Ƃ����ׂ��A���ǂ̗v���ɉ����Ė{�Z�ɂ����Ă����}�Ɋw�k���̌������}����܂��B�w�k���͊e�Y�ƌ����͂Ƃ��Ċw�������邱�Ƃ��ړI�ł���܂��v
�@���łɒY�Ă���Z��؉��ɉ����ă}���K���A�����Ԃ̌㉟���ȂǁA���k���̘J�͂Ƃ��ē������Ă���ł͂Ȃ����B����͋��������������Ȃ�����A����Ő��k�炪���Ƃ��鎞�Ԃ͂܂������Ȃ��Ȃ��Ă��܂����ƁA���߂̐S���ŕ��������Ă����B
�@���̓��͓��j���ŁA������^�Ă��v�킹��z�C�������B���Ƃ̕��e����_��̕�����Ă��̂ŁA���̖@�v�������Ȃ��Ƃ̗t�����͂��Ă��Ė���͑����J�֏o�������B
�@���Ƃł͋v���U��ɕ�e�̊���݂����q�̉b�ꂪ�A������Â��Ă���Ǝv������A�T�ɂ�����Ă��Ȃ��̂ɖ���͎��]�����B��e�ɗa�����ςȂ�������A���c�ꂳ��q�ɂȂ�͎̂d���̂Ȃ����Ƃ����A�����������̎q�A�{�E�Y�{�E�Y�Ƃ����ĉb��̂��Ƃ��C�ɂ����Ă���Ă����Ȃ��A���܂���ɍ_��̗D�������Â�Ďv�킸�܂����B
�@������ꑫ�x��Ė�c������Ă����B���ߊC���c�ɂ����_������Ɛ��b�ɂȂ��Ă������Ƃ������ĕ��e���m�点�Ă����炵���B�₪�ėב����炫���A���@�h�̑m���ɂ��@�v������s��ꂽ�B�_��̐^�V������́A�O�Y�̕�ƕ���Ō��Ă��Ă����B��e�͂Ȃ��Ȃ��̏����ƖݕĂł����炦���ڂ��݂��O�ɋ����āA�Ȃ���������������킹�Ă����B
�@��Q���I���Ă̋A�r�A��������F��肸���ƒx��ĕ����Ȃ������͌�����ׂĕ�����c�ɁA���܊w�Z�Ői�߂��Ă���w�k�����̂��Ƃ�b���������B
�u����Ǎ����Ȃ̐��k���A�H���֓������邱�ƂɂȂ�ƕ����܂������ǁA�����ȂƂ����Ă��܂��q���ł��B�댯�Ȏd������������̂ł��傤���v
�u�����Ȍ��ꂪ���邩��Ȃ��A��������g���̘A�������Ă��Ă��A���ۂɐ�͂ƌĂׂ�̂��^��Ɏv���Ȃ��v
�@��c�͂��������Ă���A��i�Ɛ�����߂Ęb���n�߂��B
�u���������̘b�����A���̐푈�͂��������͂Ȃ��C������v
�u�푈���I���c�c�̂ł����c�c�v
�u���܃h�b�N���肵�Ă���͂̏��Z���畷�����b���Ȃ��ǁA��a�����ƁA�C�R�̂Ȃ��ł͂����ς�̉\�炵���v
�u�ł���a�́A�ȒP�ɂ͒��܂Ȃ��ƕ����Ă���܂����c�c�v
�u���D���Ƃ��Ă͂����v���������A���Njߍ��h�b�N���肷��͂̂��ꂩ������������A�悭�����܂��ɂ����܂Ŋ҂��Ă����Ǝv�����炢�ȂB����ɓ������n�ߒn���s�s�܂ł��A�G�@�̑�ґ��ɂ���P�����ƕ����ƁA���łɓ��{�̋�͓G�̎蒆�ɂ���Ƃ����v���Ȃ��v
�@�n�߂ĕ�����c�̘b�ɁA����͌��t���o�Ȃ��B�w�Z�̎w���v�̂ō��삩��w�����ꂽ�ʂ���A���k�����ɘb�������Ƃ��v���o���B
�@��a�͐��E�ő�ɂ��Ė��G�̕s����͂ł��B��U��a�̎�C�����A���\�@�̓G�@���̗t�݂����ɐ�����Ԃƌ�����Ƃ��u�傫���Ȃ�����C�R�ɍs���āA��ɑ�a�̏�g���ɂȂ��ēG�������ς�������Ă��v�ƌ����Ėڂ��P�������j�̎q�������B���̖ڂ̐F���A�Z�����̋w���Ƃ��Ă��ƌ������Ƃ��̍_��ɂ��܂�Ɏ��Ă��āA����͈ȗ����̘b�k�ɂ͂��Ȃ������B
�u�����푈���I���ƁA���{�͂ǂ��Ȃ�܂��v
�u���̐푈���I���Ƃ������Ƃ́A�܂���{�������邱�Ƃ��Ӗ�����B��������Γ��R�ɓG���̌R��������Ă���A����Ȃ��ƁA����܂œ��{�l�̒N�����o���������Ƃ̂Ȃ����Ƃ�����ȁA�ǂ��Ȃ�̂��z�������Ȃ���v
�@��c�͂��������A���L���ď����Ȗ̗t���ς��������Ċۂ߁A��p�ɐO�ɋ��ނƏ��w�Z���̂́i�̋��̔p�Ɓj��t�ł��B���̂��덑���w�Z�ł͉S��Ȃ��Ȃ����������v�X�ɒ����Ȃ���A��c���������푈���I��邱�Ƃ͓��{���푈�ɕ����邱�ƂȂ̂��A���{���푈�ɕ�����c�c�A���͂₻��͖���̗������z���Ă��āA���R�Ƃ������҂̂悤�Ȃ��̂ƕs���Ƃ����̒��Ō���������肾�����B
�@�Z���ɂȂ��āA���������w�Z�w�k������������āA����͋����ł̎��Ƃ��A���k���ǂ̘J������ɎQ�������邩�ɓ���Y�܂��邱�ƂɂȂ����B
�@�Y�Ă��̌����o���ɁA�����Ȃ̏㋉���ɍ������āA�l�N���ȏ�̒j�q���������ꂽ�B��Ԃ̗q�̔Ԃ́A�����L���̊ē̂��ƂŁA�����Ȃ̒j�q�����ł����Ȃ��Ă����B�o���オ�����Y�́A�w���ɂ����j�Ɍ��킹��ƁA�ƂĂ��o�ׂł���㕨�ł͂Ȃ��������A�Y�̗ǂ������͖��ł͂Ȃ��ƁA����͋��ق��Ă����B
�@����̏��q���k�͓S���̐��H�킫��A���H���Ȃǂ̋n�ɑ哤��A���邱�ƂɂȂ����B���͂⋳�t�̒N��������̎v�l���Ƃ߂����ɁA���X�Ɩ��߂���鎖���ɖفX�Ə]�����B����ƂāA�����̐��k������������ɖ����Ɋw�Z�ɖ߂��Ă���̂��A�����肤�����������B
�@�����ɓ����đa�J�w��������Ă����B�������J���̎��@��j���ʂɏh�ɂɂ����a�J�w�������́A�c�ɂɂ����Ε������ς��̐H�����ɂ�����邾�낤�Ɗ��҂��Ă����ɈႢ�Ȃ����A�����̂��߂ɓ�������̒j�肪���Ȃ��Ȃ��������ɂ́A�ނ�̉����ȐH�~���������̗]�T�͂��łɂȂ������B
�@���̒r�̌���ɂ��Ă��Ȃ��Ȃ������́A���̎�ӉZ�܂ł����ꂽ���́A����Ȏ����͂����Ă��\���������͂Ȃ������B���l�N�����A�c�����Đe�ƕʂ�Ă����a�J�w����s���Ǝv���Ă������炾�B
�@����ɋ����������S�z�����s��̊w���Ƃ̊w�͂̍��́A����قǖ��ɂȂ邱�Ƃ��Ȃ������B���łɒ�w�N�������āA���ƂȂǂȂ��̂ɓ�������Ԃł��������炾�B
�@����ȂȂ��ŋ��������̔��Ăɂ��A�w�Z�̌��ւ킫�ɑ傫�ȃJ�}�h�������A��N�ɍZ��Ȃǂ̍؉��Ŏ��n�����Ï��������Đ��k�ɐH�ׂ����邱�ƂɂȂ����B�J�}�h�ɐ�������͋v���Ƃ̑䏊�ɐ������Ă������̂��A�w�Z�����T�ɗ��ݍ���Ŏ������܂ꂽ���̂��B
�@��������͖����̂悤�ɉ��V���̑劘�ɂ��������ŁA����������Ă�������������������A�a�J�w����͈��������オ��܂ő劘�̂܂������͂�œ������Ƃ����Ȃ������B
�@����Ȃ�����̂��ƁA�a�J�ł���Ă����O�N���̏��̎q���A�}�ɋꂵ�݂������ƈꏏ�ɂ������k���m�点�Ă����B���k�ƂƂ��ɕ��C���Ă����S�C�̏������Ɩ��オ�삯����ƁA�����ɂ��ƒn�ʂ�]������ċ����Ă���B�u�Ђ���Ƃ�����`�t�X��Ȃ���납�v�ȂǂƐ�y�������炪�����Ȃ��A�����Ɉ�҂֘A��Ă������ƂɂȂ�A�p�����ɗ���Ń����J�[�ɏ悹���B
�@���オ�E�����ɂ�������ɂ��̂��Ƃ�`���A���܂�����Ȉ�@�֘A��čs���Ƃ������Ƃ���A����͓r�[�Ɍ�������������B
�u�������͂�����B�����̌S���a�@�֘A��čs���Ă���v
�u�S���a�@���ƋD�Ԃ̎��Ԃ�����Ĉꎞ�Ԉȏ�͂�����܂��B�q�����ꂵ��ł���̂ɂ���ȗ]�T�͂���܂���B���Ȉ�@�֍s�����Ă��������v
�u���Ȃ͔����A����ȂƂ�����k��A��Ă������Ƃ͂Ȃ��v
�@����͂͂����������ɒc��ŕ��𑗂�Ȃ���A������ɂݕt�����B���k���ꂵ��ł���̂ɁA����Ȗⓚ�����Ă���Ԃ͂Ȃ��ƁA����������������ɐE���������Ƃɂ����B
�@���҂ƂƂ��ɖ��������������J�[���A�p���������]�ԂŌ����ďo�����A�t���Y���̋������ʂ̎��]�Ԃł��Ă����B���オ���Ȉ�@�ւ����悤�ɗ��ނƁA�������ւ͍s���Ȃƌ����Ă���Ƃ݂��A�p�������S�O���Ă���l�q���B���̂����ꂵ��ł������k�̋���������݁A�ڂ��Ă���B�S�C�̏������͂������남�낷��Ȃ��A�w�Z�̎w���ɔw�����ӔC�͎�������������ƁA����͏��Ȉ�@�֍s�����Ƃ��咣�����B�p�������������Ƃł͂Ȃ��Ǝv�������A����̈ӌ�������ď��Ȉ�@�֎��]�Ԃ𑖂点���B
�@���Ȉ�@�̕\�܂ł���ƁA�\�˂͕߂�ꂽ�܂܂ŁA�q���o���肵�Ă���悤�ɂ݂��Ȃ��B
�u�搶�A�ǂ��Ȃ��ꂽ��v
�@�U������ƁA�r�����̓X�悩��a�q�̕�e������̂������Ă���B��܂��Ȏ����b���ƁA��e�́u�݂�ȕ\������ė���������Ă͂�łȁv�ƌ����ė�����ɗ����Ĉē����Ă��ꂽ�B
�@�����ɐf�@���։^�ѓ���Ă���A�҂��ƎO�\���قǂ��ĉ@�����Ȃ��֓���Ƃ������B�w���������ʊ�ɂ͉��C���̔����~�~�Y�̂悤�ȉ�忂��Ă���B���ɉ������ς��l�܂��Ă����Ƃ������Ƃ������B
�u����͌�����ł����̂��B������܂��Ă��邩��b����������傩��R�Ȃ��Əo��邩��h������悤�Ɂv
�@�@���̓N���]�[���t�̐��ʊ�Ɏ��Z���Ȃ���A���������x����Β����j��Ď�x��ɂȂ�Ƃ��낾�����ƌ������B����̓z�b�Ƃ���Ɠ����ɁA���k���������Ă悩�����Ƃ��̎��͐S�ꂩ��v�����B�t���Y���̋����͈��S���炩�����Ă���B�\�����͔��ƌh������Ȃ�����A�������藠������f�Ă��炢�ɂ���҂����\���邱�Ƃ�m�����̂�����ɂ͊����������B
�@�w�Z�ɖ߂�������͍���ɁA���Ȉ�@�Őf�Ă��炢�A���������Ŏ�x��ɂȂ�Ƃ��낾�����ƌ���ꂽ���Ƃ�����B����͖ق��ĕ����Ă������A�w���ɏ]�킸�ɏ��Ȉ�@�ւ��������Ƃ́A���k�̖��������������Ƃ������Ă��A���ʂə�߂邱�Ƃ��Ȃ������B
�@���ꂩ�琔�����o�������̂��ƁA����͏��q���k�̓����݂ċC�ɂȂ�A�����낤�Ƃ悭����Ɣ��̖тɂт�����ƁA�Ӗ����݂����Ȃ̂��t�����Ă���B�t���Y���̏������́A�l�̗����ƌ��������A����͌���̂��n�߂Ăł������B
�@���ꂩ��͏��q���k��͏\�l����g�ň��ɕ�����A�������ł����Č݂��ɑ���̔��̖т��������ƂŁA�l�̗��̏���������̂������̓��ۂɂȂ����B����͑��̏��q���k�X�Ɏ������邷���������߂āA�w�O���X�X�݂̂Ȃ炸�����ɂ܂ŏo�����Ď�肻�낦���B
�@�l�ɂ��Ŕa�̓A�b�Ƃ����Ԃɑ��S�̂ɍL�܂����B�N�������a�ɔY�܂��ꂽ���A���オ�w���g���Ŏl�\�K���o���čw�������a��蕲�́A�܂����������ڂ��Ȃ������B
�@���������̓��̗[���̂��ƁA���オ�w�Z����߂��Ă���ƁA�v�����̏�ɔ��T�������B
�u����A���܂����w�Z����a������Ă��邩��A����ȕs�l�Ȃ��Ƃ����ȂȂ��v
�@���T�͖�����݂�Ƃ��������Ȃ�A������E���������p�ŁA�E�����������ʂɌ����Ĕh��ɒ@�����B���h��O����l��{�C�ɂ��锋�T�ɂ��Ă��̊��D�́A��قǂ̉䖝�̖��ł������ɈႢ�Ȃ��B
�u����A���܂��������Ŕa�����Ƃ��ȁA�Ƃɂ͓��邱�Ƃ͂Ȃ��Łv
�u�剜���܂��A�ቜ���܂�ӂ߂���C�̓ł����B�a�J�����܂��Ƃ鎛�֍s���Ă݂Ȃ����A�R��ɂ܂Ŕa�����˂Ă܂��łȂ��v
�@���T�Ɍ����Ė��オ���f���Ă���ƁA�\���[�g�����藣�ꂽ�Ƃ̋��̂�������A��ЂƂɂȂ����F����������@���Ȃ��狩�B�u����A�͂悤�a������v���T�̈ꊅ�ɖ�����d���Ȃ��A�����E���������p�Œ��߂�@�����B�����Ȃ萅�������ĐU������ƁA���̊Ԃɂ�����Ă����R�g�����A����̉������p�Ɍ��Ƃ�Ă����F�������̏ォ��˂����Ƃ����炵���B����ɂ͔��T��������������A������䂪���ƂȂ���A�������Ȃ����D�ɒp�����������������ł����Ă��܂����B
�@����Ƃ������a�ގ��̖��Ă͂Ȃ��A�̂Ɋ����a�����Ƃ������肾�Ă͂Ȃ������B������̂��Ɩ���͐��k���������āA�w�Z�̂܂��𗬂��쌴�ɘA��Ă����B�����Ő��k�𗬂�ɉ����ĕ����A���߂�E���Ő�ʂɌ������ĐU�蕥���A���ɂ͗��Ԃ��ĖD���ڂɂ���a����Œׂ����B���܂₱��͖����̓��ۂŁA�J�̓��ȊO�͍s�����B
�@���̓����a�J�������܂߂Đ��k�𗬂�ɉ����ĕ����Ȃ���A����͒j�q���k�̓��������ۂ����ɂȂ��Ă���̂ɋC�t�����B����͂܂�ō������ɓ��Ă��悤�ɁA���炪�����ۂ����ɂȂ��Ă���̂������B�a�J�����ƂƂ��ɕ��C���Ă��������t�́A��ᝂ��ƌ����B�b�ɂ͕����Ă��������ꂪ��ᝂȂ̂��ƁA����͐V���ȓ��ɒ��ʂ��ė����������B
�@�����Ŗ���͊w�Z�ɔ����Ă������蓮�o���J���ŁA�j���̐L�ѕ���ɋ߂����������邱�Ƃ���n�߂��B�ۊ���ɂ��������R��������Ă��闬���Ő���Ă��A�����ܕ��Ԃ������̓��������������B���Ȉ�@�̉@������A��ᝂ�ꀂ����率�O���ɂ��Ă�̂��悢�ƕ����Ă����̂����H�����̂��B
�@�Ƃ��낪�����̐��k�����łȂ��A��N������Z�N���̒j���̓������邱�ƂɂȂ�A���ɓ�\�l���̓�������ƉE�肪���Ďw�������Ȃ��Ȃ����B�ʂ̋����ɑ���ƁA���͂��キ�o���J���̐n���є��������Ȃ����߂ɐ��k���ɂ������B�_��ƂŒb�����r���߂�ꂽ����́A����ܐl�ƌ��肵�Ċ��邱�Ƃɂ����B
�@����Ⴀ������菰���̏��[�������Ƃ�A�ȂǂƎL���Ȃǂ̉A�����悻�ɁA����͐����Ԃ����č����Ȉȉ��̒j�q���k�̓����������Ɗ������B
�@�����\�ܓ��͈��؏W���ł́A�~�̎{��S���{�̓��ł������B�����Ƃ������˂��͓c�ʂ��ł����A�b���̂Ȃ��ŋ������悤�Ȑ�̐��������W���̑S�Ă��x�z���Ă����B
�@�v�����~�̈���ɓ��ł́A���߂������Ĕ��T�Ƌ撷�̌፲�q���M���ɁA�N��肩��q���܂ŏW���̎҂�������荇���āA�{��S���{�̓njo�����s���Ă����B�F�ɍ������č���̊炪���邪�A�l�N�O�Ɉ���ɓ��̖T�ɌI�̕c��A���A����哌���푈�����I�Ɩ������Ă���́A�K���F�O�Ə̂��Ė��N���̓��ɂȂ�Ƃ���Ă���̂��B
�@�قǂȂ��njo�̏��a�����݁A�፲�q��̔��łƂꂽ���Z���F�ɐU�镑���Ă���Ƃ��������B�w�Z�̗p�������Q���������삯����ł����B
�u�����搶�A�푈���I������炵�����ŁB����֏��p�ł�������A���Ƀ��W�I�œV�c�É��̂����ŕ������������Ƃ��炢�����ǂ����A�����搶�͂܂����m���Ȃ��Ǝv���A�m�点�ɎQ���܂����v
�@��C�ɒ���Ɨp�����́A���̏�ɂւ��荞��ł��܂����B�N�������q�ɐ������ēn���ƈ�C�Ɉ��݊��������ƁA���̎�@������芾�Ő��𗁂т��悤�Ȋ��@���Ă���B
�u�ő��Ȃ��Ƃ��ʂ����ȁA�����̎��ɓ������炱�̍��ɂ���҂݂Ȃ��ǂ��Ȃ�A���̘A���̓A�J�̎��₢���āA�F�����ɂ���邼�v
�@�N���̐��ɁA��ɕԂ����悤�ɒj�������p���������͂B�Ȃ��ɂ͋������݂͂���������̎҂�����B�u���W�I�̂���Ƃ͂Ȃ��̂��v�����藧�A���𐧂��č��삪���ԁB�፲�q�傪�����J���u�Ƃɂ���ɂ͂��邪�A�^��ǂ���Ă��ăE���Ƃ��X���Ƃ������̂���c�c�A�����ѐ^��ǂ͋��ւ����Ă������Ƃ��v�ƌ����Ԃ��B
�u�R�₨�܂���B����Ō����Ƃ�܂����������v
�@�p�����͌����ɂȂ��đi���邪�A��ÂɎ���݂����Ƃ���҂͂����A���߂��̂��ڂ̂܂��̐��Z�̈�����ɂƂ��Ă��Ԃ�����B����͂��̑������݂Ȃ���A�Ƃ��Ƃ����{�����������A���ꂩ��ǂ��Ȃ�̂�납�A��c�̌����Ă������Ƃ��v���A�����悤�̂Ȃ��s���ɕ�܂ꂽ�B
�@�����Ԃ��߂��Ă��A�F�͂܂�����ɓ��ɕ��S�����悤�ɍ��荞��œ������Ƃ����Ȃ��Ȃ��A�ω��o�������锋�T�̐��������悤�ɔ�s�@�̔����������Ă����B�u��P���v�N���̐��ɊF�͑������ɂȂ��ċ�����グ��B�����s����@�̂���L���L���Ɖ����������Ɍ��Ȃ��璈���Ă���B�u�`�P���T�����v�N���������A�@�e�̓A�b�Ƃ����ԂɏW���̏��ы������B
�@��̂����肪���������Ȃ������Ǝv���ƁA��l�̎q�����삯����ł��Ĉꖇ�̎�����q���q���ƐU���Ă݂����B�u����A����Ȃ���E����Ȃ��A�x�@�ɘA��Ă�����邼�v�q���̐e���吺�Ŏ������B
�u����܂āA�����G�̓`�P��Ȃ��v�q���̎肩��r����������j�����сA�����ނ�ɐ��������ēǂ݂������B
�u�����ɍ����A�C�R�͍~�����Ă��A���R�͖{�y����Ɏ������ݓO��R�������v�ǂݏグ��ƒj�͈�����ꂽ���ʂ��F�̕��ɂނ��Ă݂����B
�u����ς�����͉R����v�N���������ƁA�F��Ăɂǂ����邩�ƌ፲�q��ɒ��ڂ���B
�u���R�����Ȃ��ȓ`�P���T�����イ���Ƃ́A�É��͗��R�̑��ɂ��点����Ƃ������Ƃ����B�䂪�v���ꑰ�ɂƂ��Ă͕����̗��ȗ��̏d�厖����A�����͈���f�����Β��G�̔����b�����Y���܂̂��̌��ɓD��h�邱�Ƃɂ��Ȃ�v
�@�፲�q��͂��������ċ�����グ�Ă�����債�����ƁA�F�����n���ċ��B
�u���ꑰ�̎��ׂ����́A�V�c�É��ƂƂ��ɂ��邱�ƂȂ�A���̓`�P�ɉ����ēO��R��̏���������̂���v
�@�w�����ƂȂ����፲�q��̌��t�ɁA�F�͖{�y����ɉ����ׂ��퓬�̏������n�߂��B�፲�q��̐w���������ɓ��͎Q�d�{���ƂȂ�A��ɂ͒|���̑����������܂ꂽ�B���I�푈�ł͔T�ؑ叫�������O�R�̑_�����Ƃ��ĕ��M�����Ă��t�̘V�l�́A�펀�������q�̋w����ƁA���p�̑��c�e����ɋ삯�����B�������̒j�́u�G�̃^���N�������炱��𓊂����ĖڂԂ��ɂ���B���łɑ��͏Ă��쌴�ɂȂ��Ƃ�炵���ŁA�z��͏㗤�����炱���܂ł����ɗ����v�����Ȃ���Ǔy�����n�߂��B
�@�W���̓��肭���Ɉʒu���鈢�ؐ_�Ђ̂�����́A�v�܂̌��̂悤�ɋ����n�ԓ�������ŕБ��͎R�����蔽�Α��͈��ؐ�̗��ꂾ�B�^���N���ꗼ�Â����ʂ��A�G�̐N�U�������~�߂�ɂ͂��������Ȃ��ƁA�G�R���}�������_�Ƃ��Ă����ɐw�n��z�����ƂɂȂ����B
�@�F���͉ƕ�Ƃ������鑄����Ɉ��������Ă��邵�A����͋v���̑����玝���o�����炵���e��������߂ɂ����A�Ȃ�����o�ዾ���Ԃ炳���Ă���B�j�����͂��ꂼ�ꂪ�A�v�����~�̑��̒������̒ꂩ����{����A����T���o���Ă͎�Ɏ����W�܂����B���̂������������A�|���̑��̂Ȃ����玩���ɍ������������̂��I��Ŏ�Ɏ����n�߂��B
�@�F�̕������������̂����v�炢�፲�q�傪����ɓ��̂�������w�������������B�������̗������Ǔy���܂�߂Ă����A�G�̃^���N������Ă�����`�����߂����Ă���𓊂�����B����ɗ������������^���N�́A�n�b�`���J���ēG��������o�����Ƃ����|���ŏP���B��l�͖ڗ�����A�D�c�q�𓊂�������͎q�����g���ƌ������B
�u�q���ɁA����Ȋ�Ȃ����Ƃ�������킯�ɂ͂�����v���X�ɋ��ԏ������Ɂu�{�y����͔N��肩�珗���q�����A�F���퓬������v�N���������Ɓu�������A�����Ă��~�܂ނ̈ӋC����v�j�����͔M�ɕ������ꂽ�悤�Ɉ�l�������B�q��������e�́A��l�ɍ������đ�����q��Ɂu��Ȃ����瑁���Ƃ֖߂�v�ƁA�܂��Ɍ���ʂ悤�ɉ䂪�q���Ƃɒǂ����n�߂��B
�@���̑��R�Ƃ����v�����~�ցA���������ݏ��̏������Ƃ��Ȃ��Ă���Ă����̂́A�Ă̗z���܂������[���̎l�����낾�����B�ٗl�ȋ�����Ԃ̂Ȃ��ŁA�����͍��̃T�[�x�����K�`���K�`���炵�A�����́u�F�Â܂�A�Â܂�v�ƘA�Ă��Ȃ��爢��ɓ��̂܂��ɂ���Ă����B
�@�����͎�芪���F�ɁA�W���̗l�q���ċ삯���Ă����ƌ����A���{�̖������~�����A�V�c�É�����̂����t�ɂ����������������Ƃ����߂ē`�����B�N�������t�������R�̂悤�ȐÂ����̂Ȃ��A�����́u�푈�͍����ŏI�������v�Ƃӂ����ъF�����n���Č������B
�@�͂��O���Ԃ��炸�ň��؏W���̑����͏I�������A���̏�ŕ����������Ȃ��ꂽ�B�|���͒�̋��ɐς܂�A���⑄�͂ӂ����ё��̒������̉���ɓ������܂ꂽ�B
�@�V�w�����n�܂�A�߂ǂ������Ȃ��܂܋㌎�ɂȂ����B����ȂȂ��ŁA�l�X�̂������ɐV���ȉ\���Ȃ���Ă����B���悢����{�ɏ㗤�����A�G�̌R��������Ă���Ƃ����̂��B�፲�q��̌Ăт����ŁA����ɓ��ɂ͏W���̎҂��W�܂��Ă����B���ɏh������a�J�����̑�Ƃ��āA����ė�������̊���������B
�u�ČR�͓��{����������₵�ɂ����߁A�j�͐��܂ꂽ������̐Ԏ��܂ŃL�������������B�܂��ĕ����㗤�������ȂƂ���ł́A�Ⴂ���͓z��̉a�H�ɂȂ���߂ɒj�̊��D�������Ƃ邻�������v
�@�߂Ă������̍H�ꂪ�Ă��Ė߂��Ă����Ƃ����j���A�፲�q��ɂނ����Đ^���Ȋ�Ői���������B
�u�ĕ��̂��͖���������炤�Ă��֖҂ł��ŁA���Ƃ݂�ƌ����̂��Ƃ��߂܂��ėːJ���邻������v
�@�N����������ƁA�s���Ȏv�����ꋓ�ɕ����o�������ɁA�F���v���Ɏv���ɒ��肾���đ��R�ƂȂ����B�����Ō፲�q��̒�Ăɂ���āA�����Ƃ������Ԃɔ����Ă̏��q���̉B��ꏊ���A���Đ퍑�̂���v���ꑰ�̎R�邪�������Ƃ����R�̒��̏�ՂɌ��߂�ꂽ�B
�@�Ƃ��낪�A�����ɖ�肪�������A���̖{���ɏh������O�\���̑a�J������̂��Ƃ��B���ݐ���H���̂��Ƃ܂ōl����ƁA�ƂĂ��ʓ|���݂������̂ł͂Ȃ��A�Ƃ����̂��ꓯ�̎v���������B
�@����͋v�����~�̗��R�Ȃ�A�Ȃ�Ƃ��O�\�����炢�̎q�����B�����ꏊ�����邩���m��Ȃ��Ǝv�����B����\���o�ĉ����ɏo�����������A���삪���ǂ��Ă����B
�@�W���������낹���n�ɂł��Ƃ��A�����Ȃ�J�I�����̂������������Ă�œK�̏ꏊ���ƍ��삪�������B
�u�����搶�A�ĕ��͂���ȍ������Ƃ�{���ɂ���Ƃ��v���ł����v
�@����͏��w�Z����ɋ��F�Ɩ����Ɋςɂ������č��f��w�I�[�P�X�g���̏����x���v���o���A����ȑf���炵�������ʐ^�����鍑�̕������A�\�̂悤�ȕ|�낵����������̂��Ƌ^��Ɏv���B
�u�d�����Ȃ��A���ĂΊ��R������Α��R�ł�����ȁv
�u�܂����R���Ȃ�āc�c�����搶�͈ȑO�A���̐푈�͐��킾�Ƃ�����������ł͂���܂��v
�u���コ��A���Ȃ��͉����킩���Ă��Ȃ��B�L���͏��[�q������e�ʂ̏��q���܂ł��A�ǂ����̎R���ɉB�����ƕ����܂��B�G���̌R���ɐ�̂����̂́A�ǂ̂悤�Ȃ��̂Ȃ̂��A�嗤�̐����o�����Ă��������炪��Ԓm���Ă��邩��ł��v
�u�c�c�c�v
�u�푈�͏����Ȃ���ΈӖ����Ȃ��B���{�����߂đ��R�ƂȂ����̂ł��v
�u�c�c�c�v
�@�O�Y�c�c�_��c�c����͑��R�̕��Ƃ��Đ�n�ŎႢ���ʂɂ����Ƃ����́B����͂������܂ꂸ�ɁA��l�̒�̖�������ł����B
�@�ǂ����炩����̎��ɋD�Ԃ̋D�J�����������A���[���̋���������Ƌ߂Â��A���s�w���������s���̋}�s��Ԃ����R�g���l�����o�Ă���B�������グ�������Ȃ���A�R�Ȃ̑�z��̊ɂ₩�ȃJ�[�u��o���Ă��鍕���@�֎ԁB�ڑO��ʉ߂��Ă����@�֎Ԃ̃L���u����A�g�����o���Ė���Ɏ��U��͍̂_��ł͂Ȃ����B�X�q�̊{�R���������Ί���z�X�����A������܂���ۖڂɂ��݂�B
�@�_��A���@�֎m�ɂȂ��ĔO��̋}�s��Ԃɏ斱�ł������ˁA�悩�����Ȃ��A���߂łƂ��B�@�֎Ԃ̎��ɘA�����ꂽ�ꓙ�q�Ԃ̑����炱����������Ĕ��ނ͎̂O�Y��Ȃ��́A���̎q�ꓙ�Ԃɏ�����肵�āA������q�̏����ƂɂȂ����Ƃ����́A�݂邩��ɍ�Ƃ̕��e�ɂȂ��āA����Ɉ̂����Ɍ��E�܂Ő��₵�āc�c�B
�@�����Ƃ����܂ɗ�Ԃ��ؗ��̂Ȃ��ւ��������āA�ӂ����щ������Ȃ������悤�Ȍ������䂵���ꂪ����ƍ������芪���Ă���B
�u�����搶�A���܂̋D�Ԃ������ɂȂ�܂������v����̌��t�ɁA����͉��b�Ȋ�����Ė�����݂��B
�u�������������Ƃ������̂ł��A���̕t�߂ɓS���Ȃǒʂ��Ă͂����v
�@���܂̂͌��A����Ƃ����͖��ł��݂Ă����̂��A�˘f������̌��ɍ���̎肪������B
�u���コ��A�ĕ����i�����Ă�����A�v���Ƃ͌R����`�̎c��Ƃ��Ă��ʂɂ������A�ǂ��Ȃ邩�킩��܂���B���コ��A���܂̂����ɖl�ƌ������ċv���ƂƉ����̂ł��v
�u�Ȃ����̂悤�Ȏ������������̂ł����A����Ɏ��̂悤�Ȏ҂Ɍ����ȂǂƁc�c�v
�u�����������̏o�����̈�߂́A�ނ����b�����Y������Ƃ���A�����Ƃ����̕����́A�����S���邱�Ƃ͂Ȃ��Ǝv���܂����A����Ɋw�Z�̐��k�������W�c�ʼnb�����Y�̕�ɎQ�q�����A�ǂ�����R����`�ł��B���܂����l�́A�v���Ƃ̎������炠���������������v
�@�����Ȃ��납��������߂��A�g�����ł��Ȃ�����̓����̋����������č���̎肪�N������B���̂Ƃ��ˑR�ɑ���|���������ׂ����悤�ȉ��������B�����Ė��ォ�痣�ꂽ����̓`�F�b�Ɛ�ł��������B�݂�ƁA�\���[�g�����藣�ꂽ�ؗ��̂Ȃ��ɐl������B�j�������Ă��ĉ�����������l���܂ł͂킩��Ȃ��B
�u�Y�Ă����A����Ȏ��ɓۋC�Ȃ��v
�@����̐���w��ɕ����Ȃ���A����͕K���ŏb�����삯���肽�B
�@�R����߂��Ă���ƈ���ɓ��ɂ͂܂����l�̎҂������B�����ɖ���̂��Ƃ�ǂ��č�����߂��Ă����B����͉��H��ʊ�ŁA���R�̒Y�Ă������Ă��邠���肪�悢�ƌ፲�q��ɕ������B
�u�����͂�̌���������ɒY�Ă��q�͂Ȃ��킢�A�������̓n�[�̖����ĒY���Ă��ɂ͂ނ�����v
�@����̘b���Ă����j���A���b�Ȋ�Ŏ���X�����B
�u�l�a�蓻�̒��゠����܂ł����Ƃ�����A�ڂ̑O�̎G�ؗт̂Ȃ������炢�����ő����Ă������Ⴊ�A���̌����Ȕ����������ς͘b�ɕ������S�ۂɈႢ�Ȃ���v
�@�T�ɍ��荞��ł���j�����̉��C�Ȃ���b������̎��ɓ������B�����������̂��A������鍕�삩�瓦���Ă��ꂽ�̂��A�_���O�Y�̌����M���������̂��B����̓M�����삯�����Ă��������낤�A�������݂������������̎R�̗Ő������߂��B
�@�㌎�̔����߂��Ă��A�O�g�n��ɐ�̌R�͌���Ȃ������B���������w�Z�ł́A���k��͍Z��؉��ł̈��@���A�H��̎��n�ɐ����o���Ă����B�ΘJ��������Ă��������Ȃ̐��k�������߂��Ă��A���łɒ�w�N���k��̍z�Έڑ����Ԃ̌㉟�����I��̓������ɒ��~����Ă����B���������Ƃ炵�����̂͂Ȃ��A���̓������n��������̊Ï��������Ē��ɐ��k��S���ɐH�ׂ������B
�@���̓��̗[���̂��ƁA���オ�Ƃɖ߂�Ɩ�c����莆���͂��Ă����B�莆�͕����̉������J������Ă��āA���{�������Ƃ��L���p�����̈�����ꂽ�Z���n�����\��t���Ă������B����͎n�߂Đ�̌R���A�ԋ߂ɒm�邱�ƂɂȂ����B
�@�莆�ɂ́A�C�R�H���͉�̂���邾�낤�A�g�̐U������l��������A�����̋��ǂ����Ė��������̕���������������肾�B�ȂǂƔ��Ώ�k�߂��ď�����Ă����B
�@��̂ǂ��Ԏ������������̂��ƁA�v�Ă����Ă���Ƃ���ɍ��삪����Ă����B����͎l�N�O�ɁA����������ɓ��̘e�ɐA�������I�̖̂���ƌ����̂��B�哌���푈�����I�ƁA����L�����ؕЂ����������đ��łւ��܂��Ă���B���܂ł͌I�̖��[�g�����鍂���ɂȂ��āA���߂đ傫�ȃC�K���R�Ȃ��Ƃ��Ă��āA�Ȃ��ɂ͒e���������C�K���犌�F�̌I�̎����̂����Ă���̂��������B
�u�����搶�A���N�ɏ��߂Ă悤���Ȃ��Ǝ������܂����̂ɁA�Ȃ�����̂ł����v
�u���̌I�͌R����`�̂��ƂɐA�������̂ł�����A���R�ɐ�|���˂Ȃ�܂���v
�u����ȁc�c�A�l������ɂ����Ă�ł��邾���ŁA��ȂǂƌI�����z�ł��B����Ȃɂ悤���C�K�����Ă���̂Ɂv
�u�哌���푈�����I�ȂǂƁA��̌R������Ă��Ă��̎���m��A�I�̖�A���������͌R����`�҂Ƃ��ĕ߂炦���A�ǂ�ȏ����������m���v
�@����͂ǂ����Ă���ƌ�������A��Ɏ����������I�̊��ɓ��Ă��B��l�̂���肪�����������̂��A���T���o�Ă����B�ފ݂ŕ�Q��������ɁA�ЂƂ���傫���ېV�̗�m�b�����Y�̕�����҂��ɓ|����Ă��āA�����̂Ƃ��딋�T�̋@���͍ň��������B
�u����͂�A���̉��~�̂����ɂ�����̂́A����{�ł�����ɐ邱�Ƃ͂Ȃ��B��̒j���I�̖؈�{�Ńr�N�r�N���Č��ꂵ�������v
�@���T�̈ꊅ�ɍ���͌I�̖̔��̂���߁A������̌R������Ă��Ă��������A�������Ƃ�ق��Ă��Ăق����A�Ɩ���Ɣ��T�ɉ��x���O�������ċA���Ă������B�u�����Ƃ����낤�҂��A�̂�����������̂��v����o�Ă�������̌��p�ɁA���T���Ƃ茾�̂悤�əꂢ���B
�@�\�����ɂ͊��������w�Z�ɂ��Ă����a�J�w���炪�����グ�Ă������B�Z�������Ƃ��A���l���̒j�q���k����𗣂�Č��������̖T�ɋ삯���u�搶�܂����������Ă��炢�ɂ��邵�v�Ƃ���̐�������ŋ��B����̓V���N����a�Ɗi���������X���ڂ݂āA���ݏグ����̂��������Ȃ���V�哪�ł��B
�@���̂���w�Z�̋��E���̂������ł���\�������ꂾ�����B�v���͌R����`�̏ے��ł��邩��A���オ����Ɛ�̌R������Ă����܂�ɁA�w�Z���܂��R����`�𑱂��Ă���Ǝv���A�ǂ�ș�߂������邩�킩��Ȃ��A�Ƃ��������e�������B
�@��p�����Ƃ��ĕ�E���Ă���ܔN�]��A����͎���������Ƃ����������Ƃ��v�����B��l�̒j�����t���������Ă����\�ꌎ�̎n�߂ɁA�Z���Ɏ��\���o���Ă��̓��̂����Ɋw�Z�����Ƃɂ����B����ł��Z����o��Ƃ��������ďo�Ă����N�z�̏����t�������Ǝ����Ś������B
�u���܂����猾�����ǁv�ƑO�u�����Ĕޏ��́A��w�����n�܂�ƎL�����A�v���͌R����`�̏ے�������A���̏��𑁂����߂�����A��̌R��������w�Z�������A�ȂǂƍĎO�Z���ɐi�����Ă����ƍ�����ꂽ�B���܂̖���ɂ́A�ނ炪�����������Ƃ��A���͂�ǂ��ł��悢���Ƃł������B
�@�U��Ԃ��Ē��߂�ƁA�Z�ɂ̗��R�ɂ͎��n����鎖���Ȃ��Ȃ�A�L�ѕ���̃q�}�����ɗh��Ă����B�ق�̏����܂��܂ł̎������A����ɂ͉R�̂悤�Ɏv�����B
�@���̓��͌ߌ�̎O������ɋA�������́A���˂Ă���l���Ă����A��c�̂��Ƃւ������S���ł߂��B�ꌎ�܂��Ɏ莆�������Ƃ��ɂ́A�����݂ȕԎ��������ďo�������A���̎������c�ƂȂ��J�����Ă݂����Ǝv�����B�����A�q�����̏����c������Ă���邩�ƁA�����̕s�������������A�����������Ȉ�@�̉@������u���ꂩ��͐V�������̒��ɂȂ�A�����K���ɂނ����ē˂�����v�Ɨ�܂��ꂽ�̂��v���o���āA���܂̐S�̎x���ɂ����B
�@�葁���g�̉��̕i���܂Ƃ߂�ƁA���Ђ̒�����炦�Ĕ��т̈���т�����A���T�ɕʂ�̈��A�Ȃǂ��悤���̂Ȃ�A�����~�߂���̂͂킩���Ă���̂ŁA�����Ǝv�������ق��Ă������Ƃɂ����B�o�����Ɍ��Ɋ����Ă������花���卪�̑����A�����炩�����G�X�ɉ������݁A�c���ɏo�Ă��鑺�l��Ɗ�����킳�ʂ悤�ɐl�a�蓻���z���邱�Ƃɂ����B
�@�Ƃ̒���ʂ蔲���悤�Ƃ����Ƃ��A�F��������o�����B
�u�ቜ���܁A���ւ��߂�ł������B��������ڂ������A��₵�āA�߂��Ă��Ă�����₷�ȁA�킵��������肢���܂��Łv
�u����܂ő剜���܂̂��Ƃ́A�킵��ł����b���܂��ŁA�ǂ������̂ɋC���Ă��čs���Ă����ł₷�ȁv
�@���Ƃ���o�Ă����R�g�����A���������ċ���ꂽ��݂����ɍ����o�����B
�@�Ȃ�Ƃ������ƂȂ̂��A���łɎ����̍s�����@�m����Ă����Ƃ́A�\�����ʎ��ɂ��̏�����U���ׂ����t���o�Ă��Ȃ��B��ꂱ��ł͉Əo�ɂȂ�Ȃ��ł͂Ȃ����B��݂����A�u���A�͂��v�ƌ����Ă���A���Ƃ��Ԃ̔������Ԏ����Ǝv�����B
�@�ŋ߂͋D�Ԃ̍��݂悤�������ƕ����Ă����̂ŁA�������Ȃ��Ƃ����̗�Ԃ̂��鎵������܂łɂ͉w�ɒ�������ŋ}�����B������߂��čM�\�˂܂ł���ƁA�����Ȃ�l�e������ē����ӂ������B�ǂ��������ŐQ�Ă����炵���B���Â����������ɃQ�[�g���������A�퓬�X�������j�́A������ł͌������Ȃ��炾�����B
�u�˂�����A�H�����������Ă�����߂���ł���v
�@�j�̂Ԃ����Ȍ������ɁA���|������������͎G�X���爬��т��o���č����o�����B�j�͂�قNj������̂��A�Ђ�������悤�ɂ��Ĉ���т����Ƃ��̏�Ŗj����n�߂��B����͂��̂܂܂������Ƃ������A�j�������ǂ��ł��Ēʂ�Ȃ��B
�u�����牽���H���ĂȂ������B�������Ŗ��E�������킢�v
�@�A�ɉ������ނ悤�Ɉ�ڂ�H���I������j�́A�����Ɩ���Ɏ����𑖂点�Ęb���������B�j�͎���������̕������ł���ƌ����A�ł̔����o�������Ƃ��ď��l���牖�I���d����ċA��r���Ŏ����܂�ɑ����ĎI��v������Ă��܂����ƕ����邩���Ȃ��l�q���B
�u���͍��Ɣ炾���ɂȂ��Ė��т�f�r���A����Ɩ߂��Ă����A�������Ă���Ɨ��݂��B�����̂�́A�����Ō������Ă����s�ŕ߂܂����炱�ꂾ�Ƃʂ����₪�����v
�@�j�͖���Ɍ���������������˂������Č������B
�u���͌���̓J�l�͂Ȃ��A�w�ō~��āA�����H�������ƕS�����̌˂�@���Ă܂�����A�O�N�܂��ɂ͊��Ă̐��ɑ���ꂽ�䍑�̗E�m�����܂��ᕨ����A�Ƃ��낪�悤�A�ǂ̉Ƃ���������g�����A����������̂��Ȃ��Ȃ�H�����͏o���˂����Ƃ�v
�@�j�͈�C�ɒ���A��ڂ̈���тɂ��Ԃ�����B
�u�˂�����A������́v
�u�c�c�c�v
�u���������A��������F�����l����������B�|�P�b�g�ɂ͂��̂悤�ɎႢ���[��K�L�̎ʐ^���K�������Ă�ȁv
�@����͒j�Ɩڂ����킹��̂�����āA�낫�����ő����j�����������Ă����̂�҂����B
�u���j�ɂ���Ď��z�������ȁA��������Đ����������Ɛ�ӂɊ������悤�A�����Ȃ胏�j�̔��̈ꌂ��H��������A���j�͑��������������Ȃnj����������˂��A�I�R�Ɖj���ł����₪�����B�Ղ��Ղ��Ɨ�����Ă�����̂����āA���͐�ɐ����Ċ҂��Ă��A�c���֊҂��ĕ���t�т�H���܂ł́A����ȂƂ���Ŏ���łȂ���̂��ƌ��߂��B���т̂Ȃ��ŁA��N���̂��������̊���q�܂��ɂ悤�A�����炪��ǂ��ɂ��߂��ė����B�����ł�������Ă����͂�����܂��Łv
�@���������ƒj�́A���オ���ނ܂��Ȃ���т�����A�����̋����𗼎�Ŋ������B�����o���̓��[�ɒj�̕E�ʂ��߂Â����Ƃ��A�e��������悤�ɒj��������ֈ����|���ꂽ�B��l�̎�҂�����̂܂��ɗ����Ă���B�u�O�Y�A�_��v���オ���Ƃ��A�����オ�����j���O�Y�ƍ_��ɔ�т�����A���ꍞ�܂O�l�̎p�͊R���ɏ������B
�@�������Ȕߖ��������Ė��オ��ɕԂ�ƁA�ڂ̑O�ɔ����e������B�u�M���A���肪�Ƃ��v����̘b�������ɁA�M���͑傫�Ȕ����T�b�ƈ�U�肵�ĕ����o���B�R���͌��������ŁA�j�͐▽�����Ǝv����B���������ł������Ă��āA����͐���s����̔����e��ǂ��đ��𑬂߂��B
�@�������肫�����Ƃ���ŒJ��ɂ�����ۖ؋���n��A�c�ނ̂��������ēc����ɂ����钾�����܂ł����Ƃ���Ŗ���͗����~�܂����B
�u�M���A�������v��A���܂������܂ł��B�҂ł�����c�c�v
�@����͎��L���Ă����ƃM���̓��ł�ƁA�ӂ����ѕ����o�����B��������n��I���U������Ď��U��ƁA���̌������Ō����锒���e�̓T�b�Ɣ���|���ė[�ł̐X�ւƋ삯�Ă����B
�@�n�ԓ����}���قǂɁA�₪�ĉw�O�̏W���̓��肪�����Ă����B����͂����Ȃ茻�ꂽ���������ċ�����c�̊��z���Ȃ��瑫�ǂ�𑬂߂��B
|