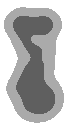| 腕時計を見ると、まだ19時を少し過ぎたばかりだった。綿矢りさの『蹴りたい背中』でも買おうかと思い、会社を出た。
昨日は、私の所属する部署が主管する会議のひとつでちょっとしたアクシデントがあり、その続きが翌日16時から開かれることになった。部門間調整と資料の準備で、帰宅したのは日付の変わる間際だった。風呂に入りすぐに寝たので、第130回の芥川・直木両賞の受賞者を知ったのは、一月十六日のNHKの朝のテレビであった。
出社し、いつものとおりにノートパソコンを立上げ、グループスケージュール、ノーツの掲示板、メールと順次チェックしていくと、社長御自らのEメールが届いていた。「例の延長再試合」的会議を中止する旨が書かれてあった。担当者に善後策を指示した後、総務部の元部下に確認すると急きょ東京出張とのことであった。こんなことは日常茶飯事で、最近では徒労感すら起こらない。
そんな訳で久しぶりに19時台に退社することになった。難波の「ジュンク堂」にでも行こうかと思った。
私が勤務する九階建の社屋は谷町筋にあった。背後には生玉神社の森と沢山の寺々とホテルがある。難波に行くには、上本町まで戻って近鉄に乗るか、谷九から千日前線の地下鉄に乗る方法がある。どちらも所要時間は十五分程度である。急がないとき、私はいつも歩くことにしていた。男ひとりでネオンが眩いホテル街を抜け、石畳の源聖寺坂を下り、日本橋の電々タウンを横切る行程は、ゆっくり歩けば半時間を要したが、日ごろの運動不足解消を兼ねて比較的よく歩く。
空腹だったので、途中で吉野家に立寄り、ちょっとだけ米国のBSEが気になったが、並の牛丼とけんちん汁を食べた。
道具屋筋を通り「ジュンク堂」についたのは20時だった。「なんばグランド花月」前の広場は中学生ぐらいの若い女性で溢れていた。数人単位で円陣を組むように地べたに座り込んだ水溜りのような人塊があちらこちらにできていた。一心になって携帯でメールをしている少女が、各集団に必ずいた。
私はタグボートのように彼女らを迂回しながら「ジュンク堂」の店内に入った。
綿矢りさの『蹴りたい背中』は売切れだった。同時受賞の金原ひとみの『蛇にピアス』も同様だった。[購入ご希望の方は、ただ今カウンターでご予約受付中]というPOPが吊られていた。
直木賞は元々興味はなかったが、今回の江國香織は以前から気になる存在だった。彼女の受賞作『号泣する準備はできていた』は、正面の話題本コーナに平積されていた。そこも人集りしていたので、女流文学コーナの方へ行った。本棚にあった五冊のうちの一冊だけが初版だったので、それを買うことにした。ついでに保坂和志の『カンバセーション・ピース』とW・Gゼーバルトの『アウステルリッツ』も買うことにした。合わせると五千円以上になったので、JCBで支払った。それからエスカレータで二階に上がり、文庫コーナで川上弘美の『おめでとう』を、こちらは現金で買った。消費税込みで四百二十円也。
実は、綿矢りさの『蹴りたい背中』を<今日>買おうと思ったのには、理由があった。
『せる』65号の原稿の締切り日が一月二十日で、私はそれにエッセイを書くことになっていたのだが、まだそれができていなかった。本日十六日は金曜日で、今日購入すれば土日で何とか纏められるだろうと、胸算用したのだ。題名はすでに決まっていた。『若いってお好き?』であった。
去年暮れの喫茶「田園」での編集会議でエッセイを担当することになったとき、私にはすでに構想がひとつあった。
それは友人から郵送されてきた彼女の若い知人T・O氏の『短編集』についての批評に、自分の若いころのエピソードを織物のように編み込んだ文章になるはずだった。
表題は『Same color birds』で、書出しは、
『これらの言葉たち、B5版245頁の水色のハードカバーの本に印刷された言葉たち、十二の短編、四百字詰め原稿用紙で十枚から五十枚程度の作品として、今、僕の前にある言葉たちは、かつて僕が四半世紀ほど前に『カイエ』と名づけたコクヨ製のキャンパスノート、寒い冬の夜に僕が衝動的に焼き捨ててしまった十数冊の淡いブルーのノートの中に<いた>言葉たちだ。』
であった。
正月休みと成人の日の三連休にトライしたのだが、例のごとく「草」稿だらけの「藪」状態になってしまい。ピンチヒッターを探していたところなのである。
という訳で、綿矢りさの受賞作が入手できないと困ってしまうのです。だが、彼女が2001年に書いた『インストール』は2001年に読んでいた。
私にはミーハー(たぶんバレているだろう)とへそ曲りが共存していて、原則としてベストセラーは、作者が存命中は読まないことにしている。数十万、数百万の人間が、同時に同じ行動パターンをとるということは、不自然なことに思えるのだ。しかし、話題になる前に読んでしまったときは、仕方ないこと、不可抗力として諦めることにしている。『インストール』も同様だった。偶然に書店で目にしたとたん、すぐに買い、すぐに読んでしまった。そういう条件反射的行動が私には時々生じる。その反応基準は至極単純だった。作者が「若くて可愛いい女性」だった場合である。最近では、『停電の夜に』のジュンパ・ラヒリ。昔、スーザン・ソンタグに夢中になったことがあった。<アメリカ前衛芸術界のナタリー・ウッド>彼女は1933年生まれだから、現在70歳のおばぁーちゃんになる訳だが、ブックカバーに印刷された肖像写真は、今も若くて綺麗だ。彼女の評論集『反解釈』、『写真論』や短編集の『わたしエトセトラ』は、今でも時折、断片的に読み返すことがあるが、正直に言えば<ハプニング論>の真意は,未だによく分かりません。
今朝のNHKの『おはよう日本』に出演した綿矢りさの対応は、私に好感を与えた。
たぶん、ディレクターの指示だと思うのですが、女性キャスターが、彼女が<19歳>であること、三十七年ぶりに丸山健二の<23歳1ヶ月>を抜き、芥川賞の<最年少受賞者>になったことに関するコメントや質問をする度に、彼女は一瞬、戸惑い気味の寂しそうな表情をした。マスコミ各社から同じ質問ばかりされて<うんざり>というより、それはママに叱られた小さな女の子の半泣き顔に近かった。その仕種を垣間見たとき、私は三つのエピソードを思い浮かべた。
その一つ目は、十年ほど前の新入社員研修の打上げ会でのことであった。突然、総務部長のK氏が、泣き出したのだ。当時私は新任の人事課長だった。まだ、直属の上司であるK氏のことをよく知らなかった。どちらかといえば、彼は自己主張のないYESマンだと思っていた。
彼は嗚咽しながら新人の前でこう言った。「一週間の入社時研修で少しは社会人らしくなったが、未熟なままの君たちを、いけずなクライアントや心のちんまい輩どもの生息する厳しい世間の荒波に放り出さなければならないと思うと我輩は涙が止まらん!」
K氏が泣き上戸だと知ったのは、随分経ってからのことだが、私がこの人を好きになったのは、あの出来事があったからだ。その日、二十四人のニューフェースたちが浮かべた表情が、私には、どこか<今日の綿矢りさ>と似ているような気がしたのだ。
十年が経ち、かつての新人たちも今では十一人しか残っていない。K氏も二年前に定年退職した。
ともかく<未熟なままの旅立ちに幸あれ>、である。
二つ目のエピソードは、幼友達のNのことだ。彼のことを思い出すとき、私は、いつも<才能>あるいは<早熟>について考える。
Nと私は同じ公立の小・中学校に通ったが、彼と親しくなったのは六年生からで、その後、Nは高専、私は普通高校へ進むとともに、私が市内から郊外へ引越したので、彼と犬コロのようにつるんだのは四年間のことであった。
基本的に彼は秀才だった。同級生七百人中いつも彼は二番だった。一番は和代という女の子で、彼女は中学の三年間で一度だけ三番になったことがあった。そのときもNは、たしか二番だった。
私が、Nの<才能>に感服したのは、勉強ではなかった。彼の家は小さな町工場で、一階は工場で二階が住居となっていた。家中どこにいても油の臭いがした。それでも一人っ子の彼は、自分専用の勉強部屋を持っていた。その四畳半のうす暗い部屋には、不釣合いな感のするソニー製のポータブルラジオと足踏みオルガンがあった。
彼はラジオから流れてくる曲をその場ですぐにオルガンで弾くことができた。それが仮にその日はじめて聞く曲であった、としてもだ。当時の私には、それは魔法のように思えた。
卒業の日、彼が「君、勉強をしないのはしかたないとしても、本を読む楽しみは知った方がいいよ」と言って三冊の本をくれた。『三四郎』と『シャーロック・ホームズの事件簿』と『若きドン・ジュアンの冒険』であった。
折角の好意にもかかわらず、私がそれらの本を読むことになったのは、三年後のことであった。
Nが自殺したのだ。
それは私が高校三年の初冬だった。布施のニチイに買い物に行った母が、偶然、そこでNの母親と出会い聞いてきたのだ。
まさか『万延元年のフットボール』の<僕の友人>のようにお尻の穴に胡瓜を突っ込むまではしなくとも、<自分の友人>が首を吊って死ぬとは、若き日の私には、想像することすらできなかった。
「君はいいな。自分の好きな道に進めることができて。僕は、本当は音楽か、文学をやりたいんだ。」そろそろ進学の方針を決めなければならなくなったある日、彼がぽつりと呟いたのを思い出した。高専に進んだのは、彼の父親の意思だったのかもしれない。その時の彼の顔つきが、<今日の綿矢りさ>そっくりだった。
<努力しなくても得られるもの>と<努力しても得られないもの>の存在を、私はそのとき始めて自覚した。
最後の三つ目の出来事が、二十四歳で『短編集』を出版したT・O氏のことだ。
この短編集は、十二編の短編で構成されているが、十番目の『花』という十枚ほどの散文詩のような小品だけ、文末にわざわざ括弧書きで(この作品は中学二年生の時に書かれたものです)と注記されていた。つまり『花』は、彼が<14歳>のときに書いた作品という訳である。他の作品には、制作年齢は表記されてはいない。
つまり<14歳>、これが彼のアイデェンティティなのだろう。
T・O氏に欠落しているのは、<いけず>で<心のちんまい>他者の存在への認識だ。彼の作品の世界は、自己完結している。他者への配慮が欠如しているテキストを小説と呼んでいいのだろうか……
<若いことへの拘り>ある種の<選民意識>と<若いことへの逡巡>の間には、もしかすると、あまり距離はないのかもしれない。
私には、未知のT・O氏が<今日の綿矢りさ>と同じ、ためらいがちな微笑がよく似合う若者のような気がするのだ。
『若いってお好き?』って聞かれたら、おじさん的には「YES」であるが、『若いって素敵?』と問われたら、些か微妙な問題が絡み即答できない。
昨今、漸く景気動向にも明るい兆しが見え始めてきたが、出版界もまだまだ厳しい状況にあるのであろうか。今回のダブル<最年少受賞>は、販売促進の手段としては、新鮮で話題性もありそれなりの効果は期待できるであろう。当分の間「モー娘」的現象が続くであろうが、<若年層>がCDを買うように小説を、しかも純文学(?)を買いつづけるとは到底思えない。
私がマーケティング担当者だったら、長期展望の視点からやっぱり少子高齢化を考慮して、ターゲットは<我ら熟年層>に絞り込むのだが……
いらぬお節介であろうか。
|