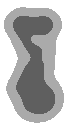|
私は、これまで北海道には二度ばかり出かけたことがあるが、本州では、仙台以北へは足を踏み入れたことがない。ぜひ一度、東北地方に行ってみたいとかねがね思っていた。しかも、どうせ行くなら冬がいいと思っていた。賢治、光太郎などの詩の中に出てくる東北地方の冬の厳しさを、ぜひ一度、味わってみたいものだと思っていたからである。しかし、その機会にはなかなかめぐまれなかった。
機会など待っていては永久に来ない。何とか無理をしてでも行くしかない。そう決心して、今年、行くことにした。しかし、いざ行くとなると、なかなか日がとれない。さまざまな行事が入ってきて、まとまった休みが取れないのだ。それでも、あれこれと工面して、ようやく二月の末に日を取ることができた。しかし、職場の大学には、観光旅行のため休暇をくれとは言えない。それで、ぜひ集めたい資料があるので休暇をくれと申し込んだ。また、そのためにははっきりとした訪問先を指定しなければならない。そこで、花巻と遠野にした。花巻市には私の興味をひく宮沢賢治の記念館があること、遠野市には柳田国男の「遠野物語」の研究所があることをガイドブックで知ったからである。それに、花巻は、大阪空港から一日二便、直行便が出ていて、わずか一時間と少しで行くことができる。通勤時間よりも短い時間である。
とはいえ、やはり東北地方は遠い。時間的に言えば、職場に行くよりも短い距離なのになぜだろうか。
距離感は、そこに行くのにかかる時間によるものではないかと思っていたのだが、どうもそうではないらしい。もちろん、地図による観念的な距離感も影響しているだろうが、それよりも、その土地への馴染みの強さがかなり影響しているのではないか。例えば、私で言えば、和歌山市と天理市とでは、天理市のほうがはるかに遠く、姫路市と津市では津市のほうがはるかに遠い。やはり、東北は、私にとってはまったく未知の土地なので、したがってきわめて遠く感じている。
さて、その東北に、二月二十七日から三日間、旅に出かけた。
伊丹をたって一時間もするともう岩手の上空である。向こうには雪を抱いた雄大な岩手山が見えた。下を見降ろすと雪があるが、すべてを覆っているというわけではなく、田圃の畦道が見える。しかし、驚いたことにどの田畑もほとんど真四角で、碁盤目模様に整然と区切られている。しかも広い。後で聞いた話であるが、岩手の田畑はほとんどが一町歩で、きちんと区切られているそうだ。私も田舎育ちであるが、私たちの村では、田畑は入り組んでいて、畦は曲がっている。同じ面積の田畑などは全くない。日本の田畑とはそんなものだと今の今まで思っていたのだがみごとに覆った。まるで、外国の風景を見ているようだ。しかも、その中のところどころに、赤色のスレート葺きの農家が点在している。古い農家風の家など一軒もない。サイロのある北海道の家とはまた違っているが、関西の田舎ともまた違う。宮沢賢治の詩や童話の中に出てくる西洋風の風景が現出しているようだ。もちろん、当時は、今とはまったく違ったものであったろうが、あの西洋風の雰囲気が決して違和感がなかったのではないかと思えてくる。岩手を、賢治はイーハトーブと名づけたが、それが、当時でも、それほど違和感がなかったのではないか。
空港を降りて、まず最初に、宮沢賢治記念館に行こうと思ったのだが、花巻空港から花巻市に行くバスがなく、また、宮沢賢治記念館も市内からかなり離れたところにあるので、タクシーを拾った。
記念館は、どこにでもよくある記念館と同じで、とりたてて印象に残るものはなかった。ただ、直筆の手紙や原稿があって、その中の彼の文字が、少し丸みを帯びたもので、たいへん丁寧に一字一字が書かれていて、その中に温かみがあるように思えた。
また、例の「雨にも負けず」の詩が書かれている手帳の切れ端もあって、それを見ていると、詩を書いている作者の生々しい息吹が感じられた。
印象的と言えば、それよりも、タクシーの中で、運転手さんから聞いた雪印の工場のことのほうがおもしろかった。おもしろいと言えば、ずいぶん不謹慎だが、花巻にも雪印の工場が二つあって、それが閉鎖され、たくさんの人が首を切られ、また、あまり産業のない市にとっても大きな打撃なのだと盛んに言っていた。
たとえ、中心から遠く離れた土地であっても、時代の出来事は、すぐに直接影響を与えるものだと、実にあたりまえのことながらつくづくそう思った。
宿は、豪華ホテルが集まっている花巻温泉ではなく、ホテルが一軒しかない大沢温泉を選んだ。というのは、この温泉には宮沢賢治も高村光太郎もよく訪れたという露天風呂があるという記事を読んだからである。また、自炊の湯治客用の部屋もあり、湯治客もたくさんいると聞いたからである。彼らはどのようにして湯治を楽しんでいるのか知りたかった。もし可能ならば私も一度そんな長逗留をしてみたいと思い、それが可能なのかどうかを確かめようという思惑もあった。
私の泊まった山水閣というホテルは、近代的なもので、部屋も美しく、いわゆる一流の観光ホテル、つまり、宴会付きの団体旅行を見込んだ、どこにでもあるホテルであった。ただ、客は冬場のためか、少なかった。ホテル専用の送迎バスが、東北新幹線の新花巻駅と東北本線の花巻駅の両方に立ち寄ったが、乗客は、私一人だけであった。しかも六つもあるホテル専用の温泉は二四時間利用可能なのだが、私が入ったときには、広い湯船には私一人しかいなかった。一人で気持ちよく温泉に浸かっていると、一瞬、王侯貴族にでもなったような贅沢な気持ちになったのだが、次の瞬間、持ち前の貧乏性のためか、これでホテルがやっていけるのかと心配したり、こんなのだから、一人あたりの値段が高くつくので、もっとホテル代を安くして、多くの人が旅を楽しめるようにできないものかと考えたりした。ここもまた、一点豪華主義の日本人気質にのっかかったただの観光地であったことが残念でならなかった。
現在、日本人の旅は、職場・団体の慰安旅行か、日頃の罪ほろぼしのための家族旅行か、恋人とエッチをするための旅行か、そのいずれかである。ひとりで行きたいところへ行くといった本来の旅の在り方がきわめて少ない。また、そうしようと思っても、そのための施設がない。あるいはそうしたいと思う魅力的な場所がない。
それはさておき、いったい自炊による湯治場はどうなっているのかと気になり、食事を運んできた女性従業員に尋ねてみた。宿は、豪華ホテルと地続きの別棟にあり、廊下で行けるとのこと。値段は一泊三千円からいろいろあるとのことであった。温泉風呂は、ホテルの宿泊客はどの風呂にも入れるが、湯治客は、露天風呂と、もうひとつ、薬師の湯と言われている大浴場のみとのことであった。
翌朝、露天風呂に入るため、別館への廊下を突っ切ると、行き詰まりに重い鉄の扉があり、それを押すと、一気に冷気が頬を撫でた。ホテルにいると暖房のため、冬であることを忘れてしまっていたが、自炊の湯治場に出ると、やはり今は冬であることに気づかされた。湯治場には暖房がない。そこには自然の冷気、自然の気温が広がっている。寒かった。しかし、むかし、といっても、十年ほど前まではエアコンなどなかった。今日でも、我が家は、暖房はいつもストーブによっている。だのに、一瞬、この寒さに耐えられないと思ってしまったことが情けなかった。東北の冬を味わいに来ていながら、ちょっとした寒さにたじろいでしまうとはどういうことか。しかし、しばらくそこに佇んでいると、その寒さにも少しは慣れてきた。廊下の横には、八畳ほどの広さの板の間の部屋があり、それが店になっていて、果物や野菜、ひものや調味料などを売っていた。自炊のための食料品店である。中年の女性がいて、お客さん相手に明るく話している。何の会話かわからないが、いかにも親しげである。長く逗留すれば、店の人とも親しくなるのは当然だろう。毎年来ていれば、いっそう親しくなる。店の店員と客という関係を越え、人と人の付き合いができるのではないか。
そんなことを考えながら歩いて行くと、片側にいくつかの日本間の部屋があって、その中には小さなストーブや電気ごたつが置かれている。部屋の隅には小さなテレビもある。そこに、湯治客のおじいさんやおばあさんが座っている。
とつぜん、炊事場のほうから、お盆に何かを載せたおばあさんが部屋の前までやってきて、中の人に声をかけている。中からおばあさんが顔を出すと、持ってきたものを突き出し、挨拶をしている。会話の言葉を正確に知ることはできないが、今、自分が作った朝食のおかずをお裾分けに来たようだ。昔、よく見た光景である。まだ、こんなことが残っていたのかと感激しながら、露天風呂へ向かった。
露天風呂は、今や都会の風呂でも大流行だ。私の町にある大浴場にも露天風呂はある。しかし、ここでの露天風呂はそれとは違う。都会の風呂や温泉ホテルの露天風呂は、屋内の温泉から、露天風呂へと入っていく。したがって、脱衣場は屋内にある。しかし、ここはそうではない。脱衣場は簾二枚に遮られ、露天風呂の中にある。したがって、言うなれば屋外で裸にならなければならないということである。
朝の冷たい空気の中で一枚一枚衣服を脱いでいると、その都度、寒さが身体にしみてくる。ようし風呂に入るぞ、と何だか気合が必要になってくるが、衣服を脱ぎ終わって、さっそく湯船につかると、それが一気に解消され、今度は、今までとは対照的に何とも言えぬやわらかな温かみに包まれる。今までが寒かっただけに、それがいっそう衝撃的に感じられる。
前には、清流が流れ、河原は雪で覆われている。それらを見ながら、ゆったりと湯に浸かっていると、これらはすべて自然の贈り物であり、自然を深く味わえることが人間にとっての最大の贅沢ではないかと思えてくる。
露天風呂に入って後、今日の予定である遠野に向かうことにした。 遠野に行くには、賢治が「銀河鉄道の夜」のモデルにしたという、現在のJR釜石線に乗らなければならない。この線は内陸部の花巻から太平洋岸の釜石や宮古を結ぶ路線で、普通列車で遠野までは約二時間弱の距離である。
また、この路線の起源は、内陸部と海岸部を結ぶ「軽便鉄道」がもとであるとどこかの本で読んだことがある。だが、その中の、「軽便鉄道」とはいったいどういうものか解らない。そこで、駅のホームにいた駅長風の職員に「この線路の起源は軽便鉄道と聞いたことがあるが、いったい軽便鉄道ってどんな鉄道なの」と尋ねてみた。職員は怪訝そうに私を見て、「いや、知りません」と答えた。私はがっかりした。今勤めている自分の仕事場の起源さえ知らないなんてと思った。これは、後ほど、遠野駅でも同じことだった。そんなことは今の仕事には何の関係もないというふうだった。しかし、特に観光に力を入れているJRにしてはおそまつではないか。今までに一度も乗客に尋ねられたことがないのか。軽便鉄道と言えば芥川の「トロッコ」にも出てくる。トロッコの主人公は軽便鉄道の敷設工事を見に行ってトロッコに乗せてもらうのだ。
因みに、帰ってきて早速辞書を引いてみた。軽便鉄道とは、「けいびんてつどう」ではなく「けいべんてつどう」と読むのだそうで、「軌道が狭小で、小型の機関車、客車を使用する鉄道。一九一〇年(明治四三年)から一九一九年(大正八年)まで、鉄道敷設法によらないで建設した鉄道」とあった。釜石線はそういう鉄道として始まったのである。
この線にはおもしろいことが一つあった。それは、遠野までの駅のすべてに(遠野以降もそうだと思うが)二つの駅名がつけられているということだ。例えば、岩根橋駅はベルゴイコント、増沢駅はラクダヴォーヌ、遠野駅はフォルクローロと言ったふうに。カタカナの名前はすべてエスペラント語である。フォルクローロとはエスペラント語で民話という意味だそうだ。そうして、釜石線はまた、銀河ドリームラインとも名づけられていた。
遠野は言うまでもなく柳田国男の「遠野物語」で有名な場所である。行くにあたっては「遠野物語」を読んでおいたが、どれもこれも不思議な話である。もちろん、民話はほとんどが不思議な話であるが、この民話は何も子供向けに話されたものばかりではなく、大人たちの中で、まことしやかに語られていたものも集められている。
解説によれば、柳田民俗学の大きな目標が、常民の深層に潜む神のイメージをとらえることにあるとされているが、この「遠野物語」を読むと、昔のひとの日常を超えたものへの豊かな感受性が伝わってくる。明らかに、彼らは日常的なものを越えたものを感じとっていた。また、それができる能力を持っていた。しかし、私たち近代人は、すべて明るさの中でしかものが考えられなくなった。自分のまわりの闇の魅力や神秘性を感じとれなくなった。その分、心が貧しくなり、深さを失った。遠野物語にあるような話は、現在では、みんなリアリティーを失い、民話としてしか受け取れない。それが、私には悲しかった。
着いた日には、タクシーを二時間ばかり借り切ってガイドブックに載せられているようなめぼしい観光地はまわったが、これと言って印象に残るものはなかった。どれもこれも観光用につくられていて、昔、自然の中にあったときの力を失っている。
ただ、タクシーの運転手さんは、三十五、六の女性で、なかなかテキパキとしていて、乗客にはたいへん親切で、彼女といろいろと話をしたことが一番こころに残った。
例えば、美しい川の縁を通ったとき「このあたりの川の水は美しいですね」と感嘆の声を漏らすと、「でも、この水も水道には適さないんです。浄水施設ではたくさんカルキを入れ、飲み水はカルキくさい水しか飲めないんです」と言った。「
なぜ」と聞いたが、その的確な答は返ってこなかったが、おそらくは、春や夏にかけて農作物に使われる農薬か何かの関係ではないかと思った。こんな美しい水まで汚染されているのかと思うと、環境汚染はすごいスピードで進行しているのだと改めて恐ろしさを感じた。さらにまた、「私も若いときは都会に憧れ、外に出ていたんです。でも、やっぱり都会には合いませんでした。結婚して、一生住むとなると、親兄弟、親戚のいる生まれ故郷が一番です」とも言っていた。
それを聞いて、先日、日本語の抜群に上手な中国女子留学生に「日本人と結婚するつもりはないのか」と尋ねてみたことを思い出した。彼女は、即座に「そんな気はない」と答えた。「日本の男性は嫌いか」と言うと、「そんなことはないが、やっぱり結婚相手は中国人がいい」とのことだった。また、「日本で就職するつもりはないのか」と尋ねると、これも即座に「ない」と答えた。自国で日本語の生かせる仕事に就きたい、これが彼女たちの願いである。
生まれ育ったところで暮らすことが幸福の一つの条件だとすると、多くの日本人はそれを失っている。私もその一人だ。第一、生まれ育ったところがどこか、その場所さえ設定できない。小さいとき、いろんなところで暮らした。生まれたところでは数年しかいなかったらしい。それはどんなところかさえわからない。母親に尋ねてみても、彼女もはっきりとしない。それから、各地を転々とした。父を亡くしてから、比較的長く暮らした母の生まれ故郷をいちおう私は故郷と定めているが、それも、小学校三年のときに移り住んだところなので、子どもたちの中では「他所」ものとして扱われ、「地」のものとは考えられなかった。母親にとってはそこは故郷であったが、私にはたまたま来たところでしかなかった。親戚などはたくさんあって、半ば故郷的ではあるが、真の故郷とは思えない。あの場所をどうとらえればいいのか、今でも私は戸惑っている。
だから、故郷がはっきりしている、あるいは故郷のある人たちとは、根本的なところで異質なものを感じてしまう。もし、故郷で住むことが幸福の条件ならば、私のような故郷を持たない人間には、最初からそれがすでに失われている。私は故郷喪失者ですらない。もともと故郷などというものがなかったのだから。
次の日は、自転車をレンタルして、自分で遠野をまわろうと考え、駅近くのレンタル屋さんを二箇所ばかり尋ねたが、冬場は自転車は貸してはいないとのことだった。冬に遠野などを訪れる物好きはいないらしい。
しかたがないので、歩いてまわることにした。まあ、町を味わうにはそれが一番だろうと、重いカメラをリュックに背負って出発した。道の両脇にはかなりの雪があったが、道にはすでに雪はなく、日が照るとかなりの暖かさだ。今年は例年になく暖かさが早くやってきたと、宿の女将さんが言っていた。例年なら、今が一番寒いはずなのにと。
まず、最初は、この旅行の目当ての一つであった「とおの昔話村」と、それに隣接する「遠野物語研究所」を訪れることにした。「とおの昔話村」には、柳田国男や折口信夫が投宿したという「柳翁宿」や酒蔵を改造してつくった「物語蔵」、それから、前述した「遠野物語研究所」がある。それに、晩年の柳田国男が住んでいた住居も東京から移築して建てられてあったが、それには入ることができなかった。
ここもまた、展示されているものにはほとんど印象に残るものはなかったが、朝九時の開門早々に行ったためか、広い敷地内には私一人しかいず。古い昔の家の中に一人で佇んでいると、時空を一気に駆け戻ったような気がした。と言っても、このような家で、私も何年か実際に生活したことがある。もちろん、私の生活した家は、昭和の初め頃に建てられたもので、村の親戚が、疎開してきた私たちのために、二階の屋根裏部屋を貸してくれたのであったが、その家は昔風の大きな家だったので、そこで見ているものとあまり変わらなかった。それで、「ああ、こんなふうだった。ああ、こんなものがあった」と懐かしさがこみ上げてきた。例えば、外からの光で、金属のように輝いている丸太の腰掛け、板の間に置かれている、黒色にわずかな朱色が含まれている重重しい家具、黒々と光っている、家族が食事をする板の間。奥の客間には、光を柔らかくして取り入れる障子がある。それらはみんな美しい。今の家は、使えば使うほど汚くなっていくが、昔の家は、使えば使うほど味が出てきて美しくなる。
特に、奥の一間には豪華な雛人形が飾られていたのが印象的だった。その豪華さが、部屋の雰囲気にぴったりとあっていた。それは昔、この家に嫁いできたお嫁さんが持参したものなのだろう。あるいは、かわいい女の子ができたので、お嫁さんの両親が孫のために贈ったものなのだろうか。しかし、なんとなく、それにまつわる人々の思いや姿が伝わってきた。きっと、このような旧家にお嫁に来た人はたいへんだったに違いない。
さて、次に「遠野物語研究所」を訪れようと思ったのだが、そもそもそれがどういうものかも知らずに来た。よくそういうものが、記念館に敷設しているが、ちょっとした本が並べられているに過ぎないものが多い。まあ、そんなものだろうと思って来た。それで、玄関にいる職員に、「遠野物語研究所も見せてもらいたいのだが、どうすればいいの」と尋ねてみた。「研究所に寄られますか。では、ちょっと電話をかけて、先生がもう出てきておられるか尋ねてみます」と言って電話をかけ始めた。私は戸惑った。へえっと思った。これは困った。別に、「遠野物語」にさほど興味があるわけではない。先生って、どんな先生がいるのか。先生に会って尋ねたいことがあるわけでもない。しかし、私の戸惑いとはおかまいなしに彼女は話をつけている。
「今からお客さんがひとり行かれますのでよろしくお願いします」 こうなれば行くしかないと思い、本館を出て、向かい側の小さな建物のドアをあけた。
すると、普通の研究室の二倍ぐらいはある広い部屋があり、図書館のように、まわりに本棚があって、本がぎっしり置かれている。それに、資料などが入れられている戸棚や整理棚があり、パソコンやファックスなどが置かれ、研究室的な匂いが漂っている。壁には大江健三郎の顔写真が載っている「柳田国男と現在」と書かれたポスターが貼られている。
それを背にして、誠実そうな六十歳ぐらいの研究員がいて、立ち上がって私を迎え入れてくれた。また、窓際には三十五、六の女性のスタッフが仕事の手を休めて、お茶を入れてくれている。
見も知らない土地に来て、丁寧に挨拶され、お茶までごちそうになるとは思いも寄らなかった。不思議なものだ。いつもなら、どうってことのないただのお茶が、いいしれない人間の温かさを与えてくれる。
「柳田国男の『遠野物語』を読んで、一度、遠野へ来てみたいと思ってやってきました」 と言って、案内されたソファーに座った。
「私は、この市のものではなく、隣村のものですが」
相手は市文化財保護委員の肩書きのある名刺を差し出した。 「研究委員の誰か一人が必ず研究所につめていて、遠野物語研究所を訪れる方のお相手をしています」ともつけ加えた。
私は、差し出されたお茶を飲みながら、とりとめのないことを尋ねてみたりした。 「どうして、遠野にこれほどまでに昔話がたくさんあるのでしょうか」
「それはよく尋ねられる質問ですが、未だにわかっていないんですよ。たぶん、交通の要所であったため、各地からいろんな話が入ってきたのではないですか」
「ここは、昔は、岩手でも一番にぎやかなところであったと、駅の立て看板に書いてありましたが、そういうところだったんでしょうか」 「そうなんです。ここは、昔は、県の中心だったんですよ、……」
こんなふうな会話がなされた。
しかし、私は、会話の中身よりも、このようなことを会話していることがうれしかった。日頃、旅に出ても、ほとんど事務的なことしか現地の人とは話をすることはないが、このような、事務的なことを越えた話ができて、旅にはこんなことがあるのだと、大きな発見をしたような気がした。
三十分ばかり話し込み、パンフレットなどを土産にもらい、そこを出た。 まだ、時間がたっぷりある。それで、町中を歩くことにした。
道には陽が燦々と降り注ぎ、かなり暖かさを感じる。この岩手でも今年は春が早くやってきたようだ。冬を感じるためにやってきたのに、春に出会ってしまった。
道の両脇には雪の山がまだ残っているのだが、陽の温かさはまったく春のものだった。道には人通りはなく、陽だけがやたらにぎやかにはね回っている。遠くの山もくっきりと見える。そうして、町のどこかからか、「はーるになれば、しらこもとけて、どじょっこなあど、ふなっこなあど、春がきたよとうたうべな、……」という曲が流れてきた。その曲が、まったく、この状況に合っていて、これが、東北の春なんだ、と何度も立ち止まり、道の両脇の雪、遠い山、青い空を見回した。
歩いていると、ところどころの商家の門口に「どうぞ、お雛様をみてやってください」という看板が目に入ってくる。向こうから歩いてくる人が、その家の前で立ち止まりながら、中へ入っていく。
そういえば、先程訪れた「とおの昔話村」でもらったパンフレットの中に、「遠野町屋のひなまつり」というのがあったことを思い出した。そこを出るときに、職員の人が「お雛さんに興味がおありならぜひ行ってみてください」と言っていた。
それほど雛人形を見たいわけではないが、一度、どこかの家に入ってみようかと思った。
ちょうど歩いている左側に、昔風の宿屋のような建物があった。しかし、それはつい先頃建てられたのだった。壁は真っ白だし、かわらも黒々としている。木も新しい。しかし、家構えは昔風のスタイルである。しかも、それは薬局だった。
こんな薬局もあるのかと見ていると、その横の町屋風の建物は銀行だった。ええっと驚いてしまったが、考えてみると、薬局はこんなふうな建物でなくてはならない、銀行はこんなふうな建物でなくてはならないときまっているわけではない。我々の頭がかってにそう考えているに過ぎない。
薬局の家の横には「お雛様見物の方はこちらへ」という看板が立てかけられている。二、三人の中年のおばさんがそれを見て、薬局の裏側のほうへ歩いていく。私も、彼女らの後にくっついて、裏側にまわると、通用口のような玄関があり、ドアを開けると二階へ昇る階段があった。おばさんたちは、靴を脱いで楽しそうに二階へ上がっていく。私も彼女たちの後に従った。二階に上がると、壁面には大きなのれんが三つ、壁一杯に飾られている。どうも、それは、古い順らしい。最初のものはもう半分ぐらいちぎれている。しかし、屋号はみんな同じものだった。どうも、宿屋ののれんである。きっと、この家は、昔、宿屋だったに違いない。それが、今は薬局をしているのだ。しかし、古い町並みを残そうとして、昔のままの建て方で家を新築したのだろう。
私の前を登っていったおばさんたちは、この家の奥さんらしい人と挨拶を交わしている。どうも、知り合いらしい。本当にうれしそうに、明るい声で何か喋りあっている。昔の同級生か、それとも趣味の仲間か。
彼女たちは決してお雛さんを見るためにやってきたのではない。彼女に会うためにやって来たのだ。お雛さんはここを訪れるための口実。雛祭りとは昔はきっとそんなものだったのだろう。お雛さんを飾ることで、他人がその家を訪れやすくし、それをきっかけに、ひとびとが楽しく交流する。今、そのような接触の場がない。他人の家はよほどのことがないかぎり訪れない。みんな、家の中に他人を入れることを嫌う。そんな社会の風潮に逆らうように、このような企てを復活させた遠野の人たちはなかなかのものだと感心しながら、奥に飾られている古い雛人形を眺めていると、「どうぞお茶でも飲んでください」と後ろから声をかけられた。振り返ると奥さんが私に笑いかけている。
「どうぞ、お茶でもあがってください」
座布団を私のほうに送りながら、きゅうすでお茶を入れている。
私も思わずほほえみながら、昔、林間学校で、子どもたちがいっせいに食事をするために使ったような低いテーブルの前へ近づき、その前に座った。 「ここへ、どうぞ、お名前を」
彼女は芳名帳を差し出した。いつもなら、字が下手なこともあって、そこに名前を書くのに抵抗感を感じるのだが、そのときは違った。いそいそと書いた。
「大阪から! ずいぶん遠いところからわざわざおいでくださって」
「遠野に一度来てみたいと思って!」
「岩手ははじめてですか」
「ええ、でも、案外近いですよ、飛行機で一時間とちょっとですから。仕事場へ行くよりも時間がかからない」
笑いながらそう言った。それは、単なる実感のない言葉ではなかった。岩手は、私の中で、以前よりもずっと近いものになった。
「どうぞ、どうぞ、これ、おあがり下さい」
彼女は、今度は、お皿に入れた桜餅を差し出した。家ではそんなものを食べたいと思ったこともない。たとえ前に置かれても食べなかったかもしれない。しかし、先程の仲間に対するのと同じように、私に接してくれたことがうれしかった。私は遠慮なくいただいた。
「薬局としてはずいぶん家のたたずまいが変わっていますね。驚きました」
一番強く思っていたことを口に出した。
「そうですか、今度、建て替えたのですけれど、町並み保存に協力しまして、市も、ずいぶん援助してくださいました」
自信に満ちた声だ。
「なかなか、ユニークでいいですよ、こんな薬局は全国でもおたく一軒しかないでしょう。漢方もやっておられるので、ぴったりですよ」
お世辞ではなく、本心で褒めた。 「私の女房も、大阪で薬局をしているんですが、そりゃ、狭い店で、人が四、五人も来られたら、いっぱいなるような狭いところで、いつも息がつまりそうだと言ってます」
実際は、豊中市の薬局に勤めているだけなのだがそう嘘をついた。
「そうですか、大阪で」
「漢方も少しはおいていますので、土曜日にはたびたび講習会に出ていきます。なかなか奥が深くて難しいと言っています」
「このあたりのお客さんは漢方がおすきな人もたくさんおられるので、うちは、ずっと前からそれには力を入れています」
こんな話をしていると、また、新しいお客さんが階段を登ってきた。奥さんは、その人たちに歓迎の言葉をかけている。
私は、お礼を言って、立ち上がり、再度、雛人形のほうへ歩いていった。赤い絨毯の上の人形たちは、心もち、私のほうを向いてほほえんでいる。
そこを辞してから、その後、列車の時刻まではまだ少し間があったので、駅近くの観光協会経営の土産店の片隅で、ボランティアの語り部さんから昔話を一対一で聞かせてもらった。もちろん、無料である。「遠野物語研究所」の活動の一環として、「語り部教室」が開かれていると先程研究所を訪れたとき聞いていたが、そこの生徒であるとのことだった。ここでもあたたかいもてなしを受けた。語り部さんから、やわらかな声で昔話を聞いていると、まるで私が小学生になったような気がした。冬の夜、いろりを囲んでおばあさんからそんな話を聞いている東北の昔の子どもたちの姿が思い浮かんでくる。家族全員に見守られて、子どもたちの心はさぞかし安らかであったことであろう。わたしもまたほっとしていた。
列車の時刻が近づいてきたので、残念ながら、二話しか聞けなかったが、帰りの新花巻行き急行に乗り込んでからも、心が豊かであった。当初の目的である、冬の遠野を味わうことはできなかったが、十分、満足していた。こんなに現地の人と語り合えた旅は初めてであった。旅とは本来こんなものだとしきりに思った。大勢でバスに乗って、あちこち見学するのも悪くはないが、一人で、ぶらりっと知らない土地を訪れ、そこで、現地のひとと一期一会の出会いをする。これが旅の醍醐味ではないか。
|