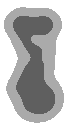
「せる」というグループは、ほとんど個人的な付き合いはしない。原稿を出し、編集会議で、編集委員の批評を受け、再度書き直し、編集委員が雑誌を作り上げ、それを合評会で批評し合う。それ以外の付き合いはしない。だから、記憶に残る出来事などはそのことの中でしかない。ただ、そのことを通しても、幾人かのことは記憶の奥に残っている。
まず、鬼籍に入った人は、私の知る限り、三名である。魚田申、木辺弘児、清水康雄である。三十七年間で三名というのは少ない方だと思う。ということは、出発はみんな若かった。年齢のいっている者で三十代半ば、多くは二十代であった。
鬼籍の人々はすべて私の中ではやはり記憶に残る人たちである。まず、魚田申氏だが、彼は和歌山市在住であり、印刷業をなりわいとし、市内ではかなり顔のきく人物であった。和歌山大学出身で、空手部の監督を引き受けていた。純文学志向の多い「せる」の中では、どちらかというと、エンターテイメントの作品を書いていた。
個人的な付き合いはしないと言ったが、その中で、彼とは一番個人的な付き合いをした。というのは、私が四十五歳の時、大学の教師として、和歌山市へ赴任した。和歌山の土地のことはまったくわからないばかりか、和歌山には知人など彼以外にはいなかった。だから、何かにつけて彼を頼りにし、面倒をかけた。
彼にはよく飲みに連れて行ってもらった。ブラクリ町の居酒屋や和歌山駅近くのバーで文学のことや、地方政治のことなどを話題に飲んだ、といっても酒の弱い私はもっぱらおいしい料理を食べる方であった。
世話になったことで覚えているのは、大学が市内の中心地である城の近くから、駅からかなり離れた山の上へ移転したときのことである。私は駅からミニバイクで大学に通うことにした。駅の近くにバイクを預かってくれる施設がオープンしたので、これ幸いと申し込みに行った。ところがすでにいっぱいで受け付けてくれなかった。置き場所がなければバイクは使えない。置かしてくれるところを提供してくれるひとはいない。私は途方に暮れた。
彼に何とかならないかと連絡した。彼はすぐに誰かに連絡し、明日から施設に置けるようにしたからと電話で伝えてきた。ありがたかった。助かった。また、そのことで、彼の地方での顔の広さを認識することになった。以後、六十歳でミニバイクを使わないようになるまでそこを利用させてもらった。
さらに、国語関係の先生方で雑誌を作ることになった。だが、その費用が少ない。何とか印刷代を安くしてくれるところがないかと頭をひねっていた。そこで私は彼に頼んでみようかと言い、彼に泣きついた。彼は快く引き受けてくれた。そのことで私の評価も上がり、雑誌作りでは大きな顔ができた。
木辺弘児氏は文学学校の教室では確か半年間、私のクラスにいただけだったと思う。
だが、とてもいい作品の書けるひとだと思い、彼と北山和希氏を「せる」に誘った。彼ら二人は1980年の四号に作品を載せているがそれらは、私のクラスにいたときに書いていた作品である。彼がその時載せた「コンビナートの火」は彼の多くの作品の原点であり、私には彼の作品で最も印象に残る作品である。残念ながら、その作品は彼の後ほど出版された作品集のどこにも収録されていない。私は、今でもあのような作品を書いてみたいと思っている。おそらく、その時、同時に掲載された北山和希氏の「絵本の周辺」が雑誌「文學界」に転載され、それに屈辱感を覚えたせいかもしれない。ただ、四号で「文學界」に転載されるような作品が出たことで会員たちは大いに自信を深めた。
木辺弘児氏が七号に載せた「水果て」が芥川賞の候補になり、俄然、世間の注目を浴びたが、二年後、木辺氏が「文學界」に載せた「月の踏み跡」が二度目の候補になり、同時に津木林洋氏が名古屋に本拠を置く雑誌に書いた「贋マリア伝」が直木賞候補になった。芥川賞、直木賞、両候補に「せる」の同人がなるという快挙に我々は大いに盛り上がり、居酒屋で前祝いと称して、祝宴を挙げた。
清水康雄氏も私にはたいへん大切な人であった。彼は私の作品の最もよき理解者だったと思っている。彼は昨年亡くなった。それで九八号で追悼のエッセイを書いたばかりであるのでここでは詳しく書かないが、彼は一号からの参加者で、百号をともに祝いたかった。それができず、残念で仕方がない。
その他「せる」から消えた人で印象深い人を挙げれば、森山(内田)美紗氏である。一号から会の事務を一手に引き受けてくれた人で、現在日本の代表的写真家の一人、森山大道氏の姉である。非常に美人で和服などのモデルにもなったり、また、繊細で緻密で気配りの行き届いた人であった。彼女は途中から俳句の方に転換したのだが、彼女の所属した会の主宰者である坪内稔典氏に会ったとき、非常にいい人が入ってくれた、会として大いに助かっていると礼を言われたことがある。
山本孝夫氏も印象に残っている。確か岸和田市の在住で生まれもそうだったと記憶している(因みに私も岸和田市出身である)。実家は農家で、非常に素朴で農家の匂いのする好人物だった。高校球児で、会員時代はマラソンにのめり込んでいた。関西空港の輸入物に関わる仕事に携わっていたが、兄が農業を継いでいて、実家の農業を手伝っていたようである。氏はどちらかというと私小説ふうで、農業の様子を描いたものが秀逸であった。当時あった農民文学賞に応募するようにと勧めたが彼は出さなかったようである。氏は、会社の仕事で重要部分を任されるようになり、「せる」を離れたが、後ほど、ひょんなことで、その存在を知ったりで、いまだに細々とであるが関係が続いている。
彼といっしょに入会した当銘広子氏も印象に残る。酒が好きで、純情で、屈託がなく、大らかで、非常にユニークな女性であった。後ほど、川崎彰彦氏の「黄色い潜水艦」に移ったが、その明るさが印象に残る。
女性ではもうひとり、忘れてはならない人がいる。それは泉りょう氏である。私が、文学学校のチューターを夜間部から昼間部に移って、クラスを形成する人が変わったのを機会に「あべの文学」というグループを作ったのだが、その事務関係を長らく引き受けてもらった。なかなか芯のある、それでいて、繊細な感受性の持ち主であった。私とは会の在り方を巡って何度か衝突したが、衝突することはいいことで、お互い、自分の立ち位置をはっきりさせる契機になる。作品では六一号に載せた「迦陵頻のように」が秀逸であり、最も印象に残っている。
また、幼なじみの男性との関係に執念を燃やす女性を描いた斎藤貴子氏、前衛的な作品を描く、森田薫氏、はまなかきみ氏など、まだまだたくさんの人が印象に残っているが、極めてローカルなことなので、この辺で筆を止めておく。去られた人の健康とご活躍をこころからお祈りする次第である。